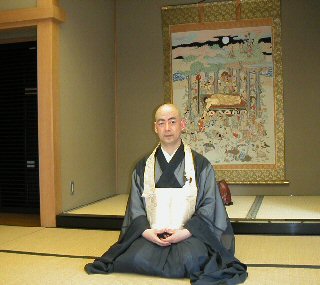
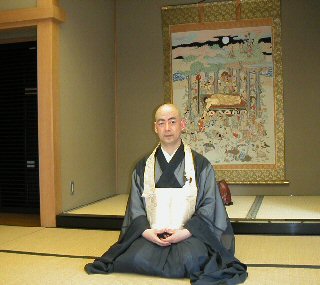
四祖大醫道信禪師は五祖に問う、「汝何姓」
「姓」は「性」にも聞こえ四祖は單に名字を聽いているのではない。おおよそ祖師方といえば名前を尋ねるなど世間話をするはずがない。だから五祖も「姓は有り、常の姓にあらず」と答える。
道元禪師は言う、「何」は「是」なり
要するに「何」が「是」だと言うのだ。「何」は「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ」と問い答えを要求する。しかしながら「何」には答えがない。答えのない、理解する以前の「今」が「是、本來」だというのである。
「言葉は月をさす指である」
私たちは「何は是なり」の指す先を見なければならない。
「何」もいらない・・・・・・・
潙山があるとき横になっていると、弟子の仰山がやって來た。潙山はあわてて壁に向かって坐した。仰山は、私は和尚の弟子なんだから、取り繕わなくてもよいでしょう。
潙山は、今見た夢の話をするから聞きなさい。仰山は近寄って聽こうとした。潙山は、この夢を占ってみないか。
仰山はたらいに水を持ち、手拭いを添えてきた。潙山は洗面し終わってしばらくすると香嚴が來た。
いま仰山と一通りの「神通」をなしたところだ。なかなかのものだろうと潙山は香嚴に言った。
香嚴は、隣で聽いて知っていたという。潙山は香嚴に、それでは何か言ってみなさい、という。
香嚴はそこで一杯の茶を持って來た。
潙山は賞賛していった、二人のの「神通」「智慧」は佛弟子の舎利弗や目犍連よりもすぐれている。
この話が正法眼藏神通の巻にあるが正法眼藏の中で屈指のいい話である。落語の八っつぁん、熊さんにたとえてもよい。香嚴禪師は差し詰め与太郎というところだろうか。香嚴禪師は博覧強記の人と言われたが紆余曲折して30年におよぶ艱難辛苦の末に道を得た。30年を經てめでたく「与太郎」になったのだ。
釋尊言(のたま)わく「一切衆生、悉有佛性」。
一切の衆生にことごとく佛性が有る、という。普段に「一切」というとき、私たちは「一切」の範囲を考える。だから僧は趙州に「狗子に佛性有りや也た無しや」と問うのだ。犬にはあるか、蟲けらには有るかと。
しかしながら佛語である「一切」は範囲がない。どこまでも「一切」なのである。その「一切」に「ことごとく佛性が有る」というとき「佛性」という言葉は言葉の限定する力を失い、意味を失う。それが佛語なのだ。そして「月」をさす指なのだ。佛語は意味を探るものではない。ともに佛語の先の「月」を觀ようというのである。
芙蓉禪師は言われる、
「又況んや活計具足し、風景疎ならず。華は笑むことを解し、鳥啼くことを解す。木馬長えに鳴き、石牛善く走る。天外の靑山色寡く、耳畔の鳴泉聲無し。嶺上猿啼いて露中霄の月を濕おす。林間鶴唳いて風淸曉の松を迴る。春風起こる時枯木龍吟じ、秋葉凋みて寒林花を散ず。玉階苔蘚の紋を鋪き、人面煙霞の色を帶ぶ。音塵寂爾にして、消息宛然なり。一味蕭條として、趣向すべき無し」。(行持 下)
一日粥一杯の芙蓉禪師の會。それでも花は咲き鳥は啼く。世間の音塵も届かずその様子は自然そのものである。一條の靜寂に求むるものはない。まさに活計に不足なく風景も豊かだ。
そのような中、木馬であった者等、石牛の修行僧が行持し育っていく。本物の道場である。
道元禪師は言われる、
「もし、祖師西來せずは、東地の衆生いかにしてか佛正法を見聞せん。いたづらに名相の沙石にわづらふのみならん。いまわれらがごときの邊地遠方の披毛戴角までも、あくまで正法をきくことをえたり。いまは田夫農父、野老村童までも見聞する、しかしながら祖師航海の行持にすくはるるなり」。(行持 下)
現在の歴史の研究では達磨大師は實在しないという説が有力である。しかしながら道元禪師の時代にはあくまで達磨大師が南インドから中國に坐禪を傳えたということが信じられていた。では達磨大師が實在しなければ坐禪が傳えられた根據が薄くなるのだろうか。決してそのようなことはない。
例えば、初期の佛典金剛般若波羅蜜多經には「應無所住、而生其心」(應に住まる所無くして、其の心を生ずべし)という一句がある。多くの者がこの一句に啓示を受けたという。
六祖は「本來無一物」と言った。道元禪師の師である天童如淨禪師は「瞿曇眼睛を打失する時、雪裏の梅花只だ一枝なり」と言った。禅宗は「不立文字、教外別傳」といい言葉で傳わるものではないわけだが、これらの一句は法を得た者しか口にすることはできない。
そしてそのことを道元禪師は見抜いていたからこそ如淨禪師のもとで心置きなく辨道精進できた。それはインドから達磨大師を介して傳えられた法であった。
そして日本にもその法を傳えるのだ、
「莫作にあらばつくらまじと趣向するは、あゆみをきたにして越にいたらんとまたんがごとし。諸惡莫作は、井の驢をみるのみにあらず、井の井をみるなり。驢の驢をみるなり、人の人をみるなり、山の山をみるなり」(諸惡莫作)
有即ち是れ無、無即ち是れ有、
若し是くの如くならずんば、必ず守ることを須いざれ。
一即一切、一切即一、
但能く是くの如くならば、何ぞ不畢を慮ばからん。
信心不二、不二信心、
言語道斷、去來今に非ず。
三祖大師は言う、「有」は「無」である、「一」は「一切」である、「信」と「心」は分けようがない、と。
「有」と言ったって「無」と言ったって「今」「本來」のことを言おうとしているにすぎないのだ。「一(部分)」と言ったって「一切(全体)」と言ったって「今」「本來」のことを言おうとしているだけだ。「信」という動詞も「心」という主語も「今」「本來」のことを言おうとして言えていない。
言語は「去來」過去と未來しか語ることができない。「今」を語ることはできないのである。坐禪は「今」を語るのである。坐禪しか「今」を語ることができないのである。
恩愛、佛教では父母の恩、國王の恩、衆生の恩、三寶(佛法僧)の恩を四恩といい、それぞれが自分自身の力では如何ともすることもできないことを「恩」というのである。父母、國土大地、人々がなければ私は今ここにいない、そして今ここに佛法とともにある。これを「恩」あるいは「恩愛」というのだ。
だから恩愛とは「今」ということである。恩愛とは「本來」ということである。
そして恩愛をあはれむ、いつくしむということは恩愛をどうする、こうするということではない。どうする、こうするということから離れるのだ。それが「恩愛をなげすつるなり」なのである。
「今」をあはれむといふは、「今」をなげすつるなり。
「本來」をあはれむといふは、「本來」をなげすつるなり。
三祖大師は、「心に異がなければ、すべてのものは一如である」という。
私たちは、人間にはもともと罪があるのだと考えたり、世の中には矛盾があると考えたりする。しかし私たちにはほんとうに罪があるのだろうか、あるいは世の中は矛盾しているのだろうか。心に「異」という対立軸を持ち込むからそこに「罪」や「矛盾」が生じるのではないか。
世の中は「異」という対立軸に依って「二つ」になる。それでは「一つ」なのかといえばそうではない。「一つ」もまた「一つ」かそうでないかという「異」なのだ。
だから三祖大師は「一如」という。「一つ」の如くであるというのだ。「一つ」に似てはいるが「一つ」ではないというのだ。だから「無」にも似ているが「無」ではないというのだ。
二は一に由て有り、一も亦守ること莫れ(信心銘)
「二」ではなく「一」でもなく「無」でもないその先を見よ。
空闊うして天に透る、鳥飛んで鳥の如し
水淸うして地に徹す、魚行いて魚に似たり(眼藏坐禪箴)
南嶽いはく、磨作鏡。(磨いて鏡にするのさ)
馬祖いはく、磨?豈得成鏡耶。(かわらを磨いて鏡になりますか?)
南嶽いはく、坐禪豈得作佛耶。(では坐禪して果たして佛になるのかね?)
坐禪は「その人となる」という言葉があるように、「佛になる」ということではないのだ。馬祖道一禪師は南嶽懷讓禪師のもとで二十年におよぶ修行をされたという。作務には率先して出、老いるまで怠ることがなかった。
あるとき、郷里漢州にかへらんとして半路にいたる。半路よりかへりて燒香禮拜するに、南嶽ちなみに偈をつくりて馬祖にたまふにいはく、「勸君すらく歸郷すること莫れ、歸郷は道行はれず。竝舍の老婆子、汝が舊時の名を説かん」。この法話をたまふに、馬祖、うやまひたまはりて、ちかひていはく、われ生生にも漢州にむかはざらんと誓願して、漢州にむかひて一歩をあゆまず。
「故郷に帰ると修行はできないし、母親が昔の名前で呼ぶぞ」と南嶽はいう。馬大師はご苦労された、しみじみ感じられる逸話である。そんな馬大師が院主に尋ねられて応える。
日面佛も月面佛も三千佛名経にようやく挙げられているような佛である。誰も知らない。調べる必要なんてない。二十年のご苦労の修行のあげくに馬大師は応えたのだ。
「日面佛、月面佛」
これは何だ!
坐禪修行の場にいるとよく「私は坐禪をしに来たので作務などはしない」とか「作務などして何の意味があるのか」などという者がときどき現れます。そういう方々は「行為」ではない坐禪を「行為」として捉え、「意味」を手放すべき坐禪の「意味」を追求してしまうのです。
私たちの多くは「私が何かである」という「名目」と、「私が何かをする」という「行為」とともに「私」という「主語」に捕らわれています。その結果、坐禪を「行為」として捉え、坐禪の「意味」を追求するのです。
坐禪には「主語」は要りません。「私が何かである」という「名目」と、「私が何かをする」という「行為」とを手放すのです。黙々と庭を掃き、黙々と草を取る、それは黙々の坐禪とともに「行為」ではありません。「無償の行為」とも違います。
黙々と庭を掃き、黙々と草を取る、それが「動中の功夫」なのです。
耿耿靑天夜夜星 耿耿たる靑天 夜夜の星
瞿曇一見長無明 瞿曇の一見 無明を長ず
下山路是上山路 下山の路は是れ上山の路
欲度衆生無衆生 衆生を度せんと欲するに衆生無し
釋尊は出家の後、印度各地で様様な苦行をされた。それは六年にも及んだ。その後釋尊は山を下りる。菩提樹の元で静かに休んでいるとき、明けの明星を見て悟りを開かれたという。「瞿曇」は釋尊の名前「ゴータマ」の漢字表記である。大智禪師は瑩山禪師の法を嗣ぐ禪僧である。この偈は釋尊大悟の勝機となった出山(しゅっせん)を頌したものである。
いま明けようとしている靑天に耿耿とした夜夜の星も見える。そのなかに釋尊は明けの明星を一見して無明を解消してしまう。苦行の山から下りる道が、ほんとうは上山の道であったのだ。いままでは衆生を救おうとして出家したのに救うべき衆生なんてどこにもいなかった。
出山相の釈尊は苦行のために痩せさらばえてあばら骨も浮き出すように表現される。一見苦行は修行に不可欠のものと考えられてしまうが、苦行も苦行という価値観のまっただ中にあるということに気付くものは少ない。おそらく釋尊にとって苦行は止むに止まれぬ行であったことだろう。それを釈尊は手放したのだ。菩提樹の元で「何かをする」ということから離れたのだ。釈尊は言う、「大地有情とともに成道す」。大地はまさに大地であった。その人はまさにその人であった。もともと衆生と佛という二見もなかったのだ。だからこそ「下山の路は是れ上山の路」であったのだ。
私たちはともすると上山を目指す。何かを獲得することを目指す。そうではないのだ。ちょっとそれを手放してみなさい、山から下りてみなさい。
「人、はじめて法をもとむるとき、はるかに法の邊際を離却せり。法すでにおのれに正傳するとき、すみやかに本分人なり。」
道元禪師は言う、人が初めて佛法を求めるときには佛法からは遠く離れているものだと。そして佛法がその人に正しく伝わったときには、本分の人になるというのである。これは一見、一般論を言っているように見える。しかしこれは道元禪師がまさに自分自身を振り返り、自分自身のことを言っているのだ。来し方を振り返り、自分自身も初めはそうであったなと言っているのだ。
たとえば、白隱禪師は「衆生、本来佛なり」という。確かにそうだ。しかしながらこのことは本分の人となって初めて言えるのだ。誰もがもがき苦しみ佛法を求める。道元禪師もそうであったに違いない。
修行の時節には挫けそうになることもある、やめようと思うときもある。しかし必ず「衆生、本来佛なり」といえるときが来るのだ。
發心寺堂頭原田雪慧老師は昨年御遷化なされました。謹んで哀悼の意を表します。 禪宗では「爐鞴(ろはい)に入(い)る」という言葉があります。修行においては鐵のように「爐(ろ)」という火中に跳び込んで「鞴(ふいご)」に吹かれて鍛えられるものだというのです。私が老師の「爐鞴」に跳び込んだのは奇蹟に近い偶然でした。そして瞬く間に五年という歳月が過ぎていました。 老師の獨參(どくさん)の嚴しさはあえて言うまでもありませんが、聞き捨てならない聽こえるようにいうつぶやきが樂しいものでした。あるとき私のそばで「物理というのは物の理だが、ほんとうに困ったときはどうするのかね」とにこにこしながらつぶやきました。私は化学を勉強したのですが、老師は物理と勘違いしていたのでしょう。これが最後のつぶやきとなりました。 朝參(ちょうさん)では、毎日のように上等な玉露を丁寧に煎れてくださいました。玉露の深い甘みとともに忘れられない日々となりました。
若狹なる後瀨の山にものの理を問ふこともなき雪の夕暮れ
令和三年立春 立花知彦九拜
烈焔亙天はほとけ法をとくなり、亙天烈焔は法ほとけをとくなり、圜悟はいう。本来底に烈焔も亙天もない、法もほとけもないのだ。
なんでもない本来をあるときは法と呼び、またあるときはほとけと呼んでいるだけである。多くの者は法という言葉にとらわれ、ほとけという言葉にとらわれている。とらわれているから論理に惑わされる。般若心経にも色即是空、空即是色とあるが、もともと色も空もないことに気づくべきである。
説法といえば、釋尊が靈鷲山において弟子たちに説法したというのがその始まりと伝えられている。その説法とは何であろうか。私たちは説法というと「ためになる話」を聴くことだとは思っていないか。
そのとき釋尊は花を拈じた。そして多くの弟子たちの中で迦葉尊者だけが微笑したと伝えられている。拈華微笑の機である。まさにそのとき釋尊は迦葉尊者が「吾に正法眼藏涅槃妙心あり、摩訶迦葉に附囑す」といわれ、迦葉尊者が法を受け継いだと言われた。
このことが説法であり、聞法なのである。それ以上でも以下でもない。法を説くということは法を伝えることなのである。法を聞くというのは法を受け継ぐことなのである。
まさに「佛祖の大會に會して、皮肉骨髓を參究せん」。言葉にとらわれて右往左往するのではない、父母未生以前の本來に參究するのである。
雲巖が道吾に問う。「大悲菩薩(觀音菩薩のこと)、許多(たくさん)の手眼を用ゐて作麼」。觀音菩薩はあんなにたくさんの手と眼を持ってどうするんだろう、という問いである。道吾は答える。「人の夜間に手を背にして枕子を摸するが如し」。夜、後ろ手に枕を探すのにはよいかな、と答える。
雲巖と道吾は薬山門下の兄弟弟子である。問答をしているというより本来の面目をもって觀音菩薩のことを語り合っているという様子である。そして觀音菩薩といえば大乗佛教において千手千眼をもって人々を救う大慈悲の菩薩とされる。
雲巖が提起するのは、觀音菩薩がほんとうに人々を救う菩薩であるとするなら、千手千眼という「手段」による救済でしかないのかということなのである。私たちにはいつも「私」という主語があり、「何かをする」という目的語と動詞のなかで生きている。しかしそれは言葉という意味の中で生きているにすぎない。「私」から発生した意味の中の問題にすぎないのだ。雲巖の問いは意味の中でほんとうの救いはあるのか、「何かをする」という中に解決はあるのか、あるいは「手段」による救いとはいったい何なのか、という問いなのである。
本来のこととは意味以前のことなのである。「である」以前のことなのである。「何かをする」以前のことなのである。「手段」以前のことなのである。坐禅は「手段」ではない。本来のいまここには「私」も「手段」もない。それが「遍身是手眼」であり、「通身是手眼」なのだ。
釈尊は紀元前五-四世紀に在世された方であるが、大乗佛教は紀元前後に興った新しい佛教であった。もともとの釋尊の佛教は「修行して悟りを開く」ことを目指したのに対し、寺院あるいは僧侶を供養することによって救われるという道を説いたのである。大乗というのは大きな乗り物のこと、それに乗っていれば安心というわけである。ここに「修行して悟りを開く」を必ずしも目指さない佛教が誕生したのである。われわれがふだん眼にする大乗経典、佛像はそのころに大乗佛教のよりどころとして始まった。経典の定義は釈尊の言葉を聴いて書き記したということであるので、多くの場合「如是我聞」(かくの如く我聞けり)と始まるのであるが、釈尊の言葉ではないとするのが普通である。
法華経は大乗経典の中の中心の経典で現代の日本にも多大な影響を与えているものである。その法華経の中では釈尊は一代の佛ではなくて永遠の昔からの佛であるとし、さまざまな神力を現す。このような神力を持つ方であるから信じなさいというわけである。
「その時、佛は眉間白毫相より光を放ちて東方万八千の世界を照らしたまふに、周遍せざるということなく、下は阿鼻地獄に至り、上は阿迦尼天に至る」とある。
正法眼藏光明の巻はこの釈尊の光明とは何かということだ。「しかあれば、明明の光明は百草なり」。釈尊の光明が「世界を照らしたまふ」のであるならいまこの百草を照らすというのである。それはまさに本来の百草を本来の百草とする、本来を本来とする光明なのだ。この光明のまっただ中の本来とひとつになるのだ。それが坐禅である。
「優鉢羅華は火裏に開く」という。これは曹洞宗系に属する同安常察禅師の「十玄談」の言葉である。「優鉢羅華」とは「優曇華」ともいう三千年に一度だけ咲くという想像上の花のことだ。その花が火の中で開くというのである。「優鉢羅華」は私たちそのもののことであり、「火裏」というのは火の中であろうが、水の中であろうがというこの「今」のことである。「本来のこと」が今ここにある、というのだ。いや、「いまここにある」と言ってしまってはもう遅い。「本来のこと」そのもののことなのである。
だから道元禅師は言う。
「しかあれば、優鉢羅華はかならず火裏に開敷するなり。火裏をしらんとおもはば、優鉢羅華開敷のところなり。」
ここには主語も動詞もいらない。主語が動詞なのであり、動詞が主語なのである。それらがいまの「本来のこと」の中に溶け込み解消しているのだ。まさに坐禅とは「優鉢羅華は火裏に開く」そのものになるのである。
松門寺の玄關には「至道無難」の書が掲げてある。道に至るに難しいことはない、ということである。しかしながら碧巌録の第二則趙州至道無難には圜悟克勤禪師が「三重の公案」という著語をつけている。坐禪は言ってみれば本來の自己のまっただ中にあって本來の自己に氣づくのだからまさに「無難」であるに違いはない。だから「あるがまま」とか「只ひたすらに坐る」というところにとどまってしまう。「私」が「そのままでよい」としていることに氣がつかないのである。圜悟克勤禪師の言葉で言えば「今を肯定する」という「一重の公案」で素通りしてしまっているのだ。
少し坐っているとそれではどうにもならないことに氣づく。どうしても「そのままでよい」という「今の肯定」から抜けでなくてはならないのだ。船子徳誠禪師に對して夾山禪師は否定に否定を重ねた。「不是目前法」。しかし船子にそんなことではどうにもならないと喝破されてしまうのである。「あるがまま」の否定も「私」の作爲であることに氣づけ、というのだ。これは言ってみれば「二重目の公案」ということだ。
肯定も否定もない。肯定も否定も「私」の見解に過ぎないのだ。だからこそ圜悟克勤禪師は「三重の公案」というのである。その今に氣づくのである。
南嶽いはく、「若し坐佛を學せば、佛は定相に非ず」。
坐禪を志す者は良い状態というものを求めてしまう。坐禪とはかくあるべきものだと思ってしまうのである。澄み切った心境のうちに坐っていることも忘れてしまう、そのようなことを目指してしまうのだ。今、足の痛さに耐えて鐘の音の響きを待ちかねている坐禪、次々に考え事が浮かんできてどうも集中できない坐禪は坐禪になっていないというのである。しかし足が痛かろうが、坐禪に集中できなかろうがそれこそが「本来のこと」に違いないのである。良い状態を求める者は本来の今を忘れている。
坐禪には「かくあるべき」という定相はない。今ここのこと、今ここの自己に坐禪するのである。
「魚、水を行くに行けども水の際無く、鳥、空を飛ぶに飛ぶといえども空らの際無し。」 正法眼藏には魚と鳥の話が多い。坐禪箴にも魚と鳥の話を引く。道元禪師は宏智禪師の公案集である宏智頌古を携帯していたと言うが、その宏智禪師の坐禪箴を引いている。
水清んで底に徹つて、魚の行くこと遲遲
空闊くして涯りなし、鳥の飛ぶこと杳杳なり
「かの坐禪箴をみて、この坐禪箴を撰す」「前後を算數するに、わづかに八十五年なり。いま撰する坐禪箴、これなり」と道元禪師は言いつつ自身の坐禪箴を提出する。
水清んで徹地なり、魚行いて魚に似たり
空闊透天なり、鳥飛んで鳥の如し
私も道元禪師から七百七十六年、平成己丑元朝の一句をしたためておいた。
牛、歩んで牛に非ず
川端康成がノーベル文学賞の受賞を記念して「美しい日本の私」という講演を1968年に行っている。その冒頭でふたつの和歌が紹介されている。
春は花夏ほととぎす秋は月冬雪さえて冷しかりけり(道元禅師)
雲を出でて我にともなふ冬の月風や身にしむ雪や冷めたき(明恵上人)
川端氏は自然とともに生きる日本の心を伝えたかったのだが、道元禅師の歌ははたしてそういうものであったのだろうか。たしかに明恵上人の歌にはそういうおもむきがあるのだが、この2首には天地の隔たりがある。
道元禅師は感性を廃し風物をただ羅列することによって自分自身(本来の自己)の今(正当恁麼時)を伝えているのである。
道元禅師の師匠如淨禅師もいう。「清誇るべからず、香誇るべからず」。ただこの梅花は梅花なのである。
日本の心も感性などもしばらくは捨てておけ。そこに自分自身(本来の自己)の今(正当恁麼時)があるばかりである。
高祖大師は「未曾聞の道をきくといふは、いまの道を聞著するをいふ。未曾有をうるといふは、いまの法を得著するを稱ずるなり」という。
まさに正當恁麼時「たったいま」のことはいまだかつて聞いた者はいないのであり、得た者もいないのである。このいまだかって誰も聞いたことのない、誰も得たことのない正當恁麼時「たったいま」こそが坐禅のしどころなのである。「生死事大、無常迅速」というが人間などいつ死ぬかもしれない・・・というよりも正當恁麼時「たったいま」のことにいま気付けということなのである。
「そのものがそのものである」といい「今は今でしかない」という。しかしそれもまた一法である。永嘉大師は言う、「一法を見ざれば即ち如来」と。如淨禅師の「梅花」とはその「一法を見る」以前の「梅花」なのである。「そのものがそのものである」以前の「梅花」なのであり、「今でしかない」以前の「梅花」なのである。そして坐禅とはその「梅花」となることなのだ。
「春を画図するに、楊梅桃李を画すべからず。まさに春を画すべし。楊梅桃李を画するは楊梅桃李を画するなり、いまだ春を画せるにあらず」と道元禅師は言う。
春を語るのであれば柳の葉や梅の花によって語ってはならないというのである。まさに春そのものによって春を語れというのだ。
また「法身の理は猶太虚のごとし。周遍せずということなし」と説く太原孚上座に対して夾山の典座は「座主の説不是なりと道はず、只だ法身量辺の事を識得して、実に未だ法身を識らざること在り」と言う。
座主が法身を解説するのに夾山の典座は「間違いだとは言わないが法身の周辺の事を知るばかりで本当のことを識らない」と言うのである。法身は法身をもって語るのである。 春は春そのものによって語り、法身は法身そのものによって語るのである。そのものでなければ周辺の様子に過ぎない。本来の自己も本来の自己によって語るのである。葛藤窟裡、みずからが出頭するのである。
「衆生本來佛なり」と白隱禪師は言う。もちろん私たちは「本來の自己」のまっただ中に居るのであるが、そのことにほんとうの意味で気づくことなく「本來の自己」の言語化された影を「本來の自己」と考えてしまっているのである。
だからこそ本來のことに気づくことが必要であり、參禪の者は千年も二千年もの間「大悟」を求め續けてきたのである。そして「河頭に水を賣る」という言葉があるが、まさに河の傍らで水を探し續ける者に水を差し出してきたのが禪家なのだ。
華嚴和尚は「大悟の人が迷うときは如何」との問いに答えている。「割れた鏡はもう照らすことはないし、落花はもう木に登らない」と。本來のことに気づいたのにそのことを忘れたり、失ったりすることなどあり得ないということである。
しかし道元禪師はさらに踏み込んで言う。「却迷を親曽ならしむる大悟ありとしるべきなり」。迷を迷う悟るの迷とするのではなく、悟も迷う悟るの悟とするのではなく却迷とし大悟としてこのたった今の正當の時を迷悟を離れた本來の時節であるというのである。
迷だとか悟だとかを離れ本來のことに気づく、このことを「大悟」というのである。
天童如淨禅師は「宏智古佛と相見す」と言う。宏智正覺禅師は丹霞子淳禅師の法嗣であり、天童如淨禅師から見ると法系で三代以前の祖師である。その宏智正覺禅師と相見したというのである。
「その人がその人になる」という言い方があるが本来の自己に気付くことであり、まさに天童如淨禅師がその人となったのである。天童如淨禅師が天童如淨禅師になったとき、宏智正覺禅師が宏智正覺禅師であったことが深く納得できたのであり、証明されたのであった。その本来の自性に気付かされ気付いたのである。
このとき本当のことに気付く。そして正法眼藏もそのことだけを私たちに伝えようとしていたのだと気付く。そのとき正法眼藏も透き徹るようにわかるのである。
たとえ正法眼藏であっても、その言葉に執着していては本当のことはどうにもならない。まずはその人となるのだ。その人となって道元禅師とも相見するのである。
鏡は自分自身のすがたを映すものである。坐禪も本來の自己を見性するのである。釋尊から傳わった佛道を古い鏡にたとえ坐禪によってたったいまの本來の自分自身のすがたに氣付くことを求めるのがこの古鏡の巻である。
高祖大師は言われる。「いかならんかこれ眼の眼に相似なる。いわゆる道眼、眼の礙を被るなり」と。「どうして眼は眼なのだ。本來の眼が眼によってさえぎられる」と言われるのである。本來の自己とは眼で見るものではない。眼で自分自身を見つめることによって本來の自分自身のすがたを見失っているのである。
それでは心で見るのかと思うのであろうか。しかし心で見ようが眼で見ようが見るということが余計なことなのである。見るということから離れてみればそこが本來の自己なのである。
雪峰は修行僧の前に現れ示す。「胡来胡現、漢来漢現」。胡人がやってきて現れる、漢人がやってきて現れる、というようなことであろう。解釈など拒絶する言葉がここにある。
だが人には欲がある。動物的な欲とか利を求める欲はわかりやすいが、最も自分自身で気付きにくい欲が意味に対する欲なのである。何事にも意味づけをしないと気がすまない。意味の中で解釈し理解しないと納得しないのである。
しかし雪峰は意味から離れよというのだ。意味にしがみつくのをやめよというのだ。意味から離れてみればそこに本当のことがおのづから現れる。
そこに玄沙がぬっと出て来る。「百雑砕」。師匠である雪峰の出鱈目を戒めると思いきやこれまた勝手にどうでもいいことを言っておる。しかしこの問答は悟りを開いた者だからこそできることなのである。師匠雪峰は弟子玄沙を認め、認めるからこそ意味を離れた自由な問答を展開する。師匠も弟子も認めあい他の修行僧の前で本当の問答を展開するのだ。
それを見ている道元禅師もそれに呼応して言う。「胡来胡現は一人の赤ひげのことである」と。すばらしい出鱈目である。雪峰禅師と玄沙禅師と道元禅師が相呼応して言うのである。意味から離れよ。意味にしがみつくな。そこにこそ本当のことがある、と。
道元禅師は言う、「いま玄沙のいふ請和尚問のことば、いたづらに蹉過すべからず」と。師匠たる雪峰に逆に問わせる言葉こそ見過ごしてはならないというのである。ほんものの師匠とほんものの弟子、父と子でなければ成り立たないやりとりだというのである。師匠は弟子に問い、弟子は師匠に問い返す。この問いは霹靂、雷鳴である。廻避するところなどどこにもない。おたがいに身をもってこの雷鳴を受けるのだ。このとき父と子はひとつになり、古鏡と明鏡が互いに映しあいひとつになるのである。
馬祖が百丈と歩いているときに道端で野鴨が飛びたつ。馬祖は「これなんぞ」と問う。百丈は「野鴨」と答えるが、さらに馬祖は「いづこに去るや」と問う。百丈は「飛び過ぎ去った」と答えると百丈の鼻を思いきり捻って百丈が痛がると「飛び去ったことなどない」と言う。
師匠が弟子に問うのは本来の自己である。道端の野鴨なんぞに気を取られている場合ではない。多くのものが問いに気を取られて本来の問いを見失ってしまっているのである。公案はまぎらわしい問いを発することもあるが、それが弟子の真贋を見分ける試金石ともなるのである。
古鏡の巻で雪峰は三聖に言う。「猿がおのおの古鏡を背負っている」と。三聖は百丈のようにその問いには引っかからない。「もともと何ものにも名前などないのに何をもって古鏡とするのか」と逆に問う。この三聖をみて雪峰は謝ってしまうのである。「私が悪かった」と。
公案は両刃の剣である。真贋を切り裂く力を持つのであるが、公案の言葉に溺れてしまうこともある。公案という謎解きに陥ってしまうのである。いつも坐禅によって何が問われているかと言うことに立ち返ることが必要である。
私たちはともすれば道元禅師を「個人の思想」という「新しい鏡」で照らし出そうとしてきた。道元禅師には道元禅師の思想があるというのだ。正法眼蔵はその「新しい鏡」には何も映らない。佛教は思想ではないからである。
ここには「古い鏡」がある。ずっと昔から伝わってきた「古い鏡」である。この鏡はそれぞれ自身の本来の姿をそのままに映す。そしてそのほんとうのことに気づくのである。「それは何か」という以前のことである。考える以前のほんとうのことを映し出してみるのである。
坐禅を「無」だとか「空」だとか世間では言っているが、「無」だとか「空」だとかいうことも余計なことである。この世界のすべてのものが「無」であり「空」であるなどと極端に考える人もいる。そこでは坐禅が「無」の思想、「空」の思想と成り果ててしまっている。坐禅はあくまで思想ではない。むしろあらゆる思想から離れることが坐禅なのである。残念ながら佛教の歴史はその思想化の歴史である。「無」の思想、「空」の思想として誤解されている。
「無」というのは「所有」にかかわることである。私たちは価値を所有し、意味を所有し、自分自身をも所有する。しかしよくよく考えてみれば自分自身という主体をたてるからこそそこに所有の概念が生じるのである。もともと自分自身はなんでもないものなのであるからたったいまのほんとうの様子のなかで所有しているものはなにもないのだ。「身すでに私にあらず」、自分自身でさえ所有しているものではないのである。
「空」というのは「意味」にかかわることである。私という主体が意味を所有しているが、本来のことをみてみればそこに意味はなにもない。
この「所有」にも「意味」にもかかわらない、「無」にも「空」にもかかわらないたった今のことをしばらくは「恁麼(いんも)」といい「如是(かくのごとく)」というのである。もうすでに私たちは「恁麼」の人である。どこに「恁麼」であるかどうか憂うことがあるだろうか。
恁麼ということは言ってみれば「あたりまえ」ということである。しかし「あたりまえ」のことをあたりまえと理解しては元も子もない。もともとの本来の自己であるあたりまえの何でもない自分自身があたりまえという言葉によってとらえられてしまうのである。それではもうあたりまえということに拘束されてしまって身動きがとれないではないか。
「恁麼の事を得んと欲せば、須らく是れ恁麼人となるべし。既に是れ恁麼人、何ぞ恁麼の事を愁えん。」(たったいまの事を得ようとするなら、たったいまの人となるべきである。もうすでにたったいまの人なのであるのに、どうしてたったいまの事を愁うのか。)
もともと恁麼などということはどうでもよいのだ。愁う必要があるのかないのかなどという問題ではないのである。もともと何の関りも無い。だからこそ恁麼なのである。禅ということも同じである。禅などどこにも無い。それが禅なのである。
本来の自分自身のたった今のすがた、この世界のありようを「恁麼」という。それを「本来の自己」ともいうし、この段のように「智」ともいうのである。この本来のありようを忘れて「恁麼」が何を表しているのだろうとか、「智」というものが有るのか無いのかという議論をしてもどうにもなるものではない。だから「智」は有るということでもないし、無いと言うことでもないのである。
私たちが有るといおうが無いといおうが春には松が青々とし、秋には菊が咲く。それを「恁麼」と言おうが言うまいが夏は暑く冬は寒いのである。判ろうが判るまいがこの世はこの世でしかないし自分自身は自分自身でしかない。だからこそ無上菩提もわかる必要のない「疑怪」なのである。そんなものは失うなら失えばよい。
祖師と言われる方々はそれぞれの祖録において「坐禅とは何か」ということを確信をもって書いている。道元禅師も正法眼藏においてそれを語りまた後進に伝えようとしている。私たちは正法眼藏に接してその伝えようとしているものをひしひしと感じる。感じないわけにはいかない。その伝えようとしているものは考え方、思想ではない。あらゆる思想を離れた本来のなんでもない自分自身に気付けというのだ。そのことが解らないと師匠と弟子のあいだに「密語」のような秘密の言葉か特別の何かがあるように考えてしまう。そのことを求めるのが坐禅と思ってしまう。しかしもともと「密語」というものはどこにもないのである。ただ今の自分自身の本来の姿を忘れて、外に答えを探るようでは永遠に坐禅は自分のものにならない。
官人は雲居禅師に問う。霊山での釈迦と迦葉尊者の拈華微笑のやりとりの中に何か密語があったのではないかと、またその密語は何かと。しかし迦葉尊者の気付いたことは迦葉尊者の本来の姿である。これは釈迦から教えられたものでもないし、伝わったものでもない。釈迦は悟りを開いて釈迦になったのであり、迦葉尊者は迦葉尊者になったのである。
坐禅が自分のものにならないと釈迦と迦葉尊者のやりとりの中に何か秘密があるのではないかと思ったり、正法眼藏やいろいろな禅問答を調べてその秘密を探ろうとする。しかしながらその中に答えがあろうはずがない。普勧坐禅儀のなかに「みだりに他国の塵境に去来せん」とあるように他を探っているのである。
答えは自分自身の中にある。密語はない。自分自身の本来の姿に気付けば、釈迦の拈華とひとつになって心の底から笑うことができるのだ。
「いわゆる密は親密の道理なり」と道元禅師は言う。釈尊が本来の自己に密接であることは秘密でもなく、隠しようもないことである。花は花であり、釈尊は釈尊である。密であればこそそこには密という言葉さえも必要ない。まして密語があるはずもない、余計なことなのである。そしてあらわであるからこそ本来の眼を持った迦葉尊者にはわかる。迦葉尊者も花が花であり、迦葉は迦葉である密の道理を隠しようもない。それが「不覆蔵」なのである。
雪竇禅師は言う。「一夜落花雨、満城流水香」。花の香りを含んだ水が満城を流れるように釈尊の密は隠しようもなくいまここに流れている。その釈尊の密語に気付くべきだ。
六祖に「何者がここに来たのか」と問われ、懷讓は「何を説いても当たらない」と答える。この返答に注目する者もあるが、これはとるにたらない通常の語話である。当たり前のことだ。次に修行とか悟りとかはどうなんだと問われる。懷讓は修行とか悟りとかは無いことではないが、本当のことはそういうものに影響されないと答える。六祖はこのことを誉めているが、これもまた通常の語話にすぎない。修行という行為をもって悟りという目的物を得るということによっては本来のことは得られない、ということに気づいたまでだ。これも語話による理解に過ぎない。ここから懷讓のほんとうの修行が始まったのだ。語話に注目するのではなく、語話の尽きたそれからの八年を思うべきである。
「海枯れて底を見ず、人死んで心を留めず」という句は永平廣録にある天童如淨禅師の偈の一節「海枯れて終に底に徹るを見んと要せば、人死んで心を留めずと始めて知る」を引いている。海が枯れはててしまったときそこにあるのは『海の底』ではない。海があったときに『海の底』というのは成立していたが、海がなくなってしまったときにはすでに『海の底』ではなくなってしまっているのだ。それと同じように人があって『心・本来の自己』が成り立っている。死んでしまえばそれが成立しないように、その人がその人となれば『心・本来の自己』などはどうでもよいことなのである。
だから「すでに遍参究尽なるには、脱落遍参なり」、遍参を極め尽くせば遍参も脱落するのである。さらに言えば『心・本来の自己』も脱落し、『禅』も脱落し、『佛』も脱落するのである。それらが脱落しつくしたところにその人がその人である真の境涯があるのだ。
「大道無門、虚空絶路」と道元禅師の師匠である天童如淨禅師は言う。「佛道に入るべき門などはない、この世に進むべき道などはない」と言うのだ。
遍参とはもともと学人が正師を求めて各地を遍歴し師に参ずることを言うのであるが、学人の求めるべきものは師ではなく本来の自己である。その本来の自分自身の今に参ずることが本当の遍参なのである。その本来の自分自身の今はまさしく今ここにある。どこの門から入るというのか。そしてどの道をたどって行くというのか。あるいは何処に行ってなにを求めるというのか。
「艱難辛苦の末に門が開かれ、道が開ける」と思うのはいつも大道をはるか遠くに見て脚下の自己に気づかないのである。今ここに間違いなくある自己の本来を見失っている。坐禅は今ここに間違いなくある自己の本来に遍参するのだ。
香嚴智閑禪師は三十年の修行にも見性できず、大悟をあきらめて山に入って庵をむすび余生を過ごすことにした。しかしあるとき道を掃除しているとほうきで石ころが飛んで竹にあたりその音によって自分自身の本來の姿に氣づいたといわれる。
この有名な話に注目するのは良いが、多くは竹の音にばかり注意がいってしまう。竹の音などのきっかけによって悟りを開くのだからといって竹の音を待ってしまうのだ。待っている者には竹の音は永久に來ないのである。未來を待ってどうするのだ、坐禪はこの自分自身の今に氣づくのである。
釋迦は苦行六年の後、苦行に見切りをつける。苦行によってはどうにもならないことに氣づくのである。苦行をやめて山から降り菩提樹の下で靜かに坐っていた。その時に悟りを開いたと言われる。釋迦は意味、價値の世界から逃れようとして苦行に入るが苦行も「どれだけ苦しい修行をするか」という意味、價値の世界であることに氣づくのだ。菩提樹のもとで坐って意味こそが人間を縛るということに氣づく。
香嚴智閑禪師も修行を一生懸命に續けているうちにはそれが意味を追っていることに氣づかない。意味を追って追って追って、自分自身の本來の姿に氣づかないのである。大悟をあきらめて修行をやめてしまったときに始めてそのことに氣づくのだ。
我々も意味を追っていないか。修行をしてはいないか。坐禪をしてはいないか。そんなことをしているうちは今の本來の自己に氣づくことはない。
坐禅は修行するものに公案(禅問答)を問いかける。これは単に形式的な答を要求しているのではない。私たちは問いかけに対していままでの経験、知識を駆使して答を出そうと努力するのを常としている。しかし坐禅が要求しいるのはそういった意味や価値観で出した答ではない。意味や価値観から離れた「本来の自己」とは何かということなのである。だから私たちの常識の世界からはおよそかけはなれた荒唐無稽の問答を仕掛けるのだ。意味や価値観の中で答を出そうとして何になるのだ、という問いかけである。
この世界には本当の答などないのだという人がいる。あるいは公案など考えるだけ無駄だと思う人もいる。しかしそういう人たちは「本当のこと」がわかっていない。「本当のこと」を教えてくれる師に出会わなかったのだ。
香厳禅師は三十年の修行の大変な苦労の末に道を得たといわれる。その香厳禅師が弟子を指導していくことになって公案を出してきた。高い崖の木の上に口で枝をくわえてぶら下がっている人に祖師西来意を問うというものだ。もちろん黙っていればどうにもならないし、答えようとすれば木から落ちて死んでしまう。香厳禅師は「さあ、どうする」と問う。三十年のご苦労がしのばれる公案である。
私も言おう、答えよと。答はないとか、答えるのは無駄だとか言って公案を避けてはならない。もともと私たちは「本来の自己」そのものなのだから大手を振って行けばよいのである。
香厳禅師の公案は「人が千尺の崖上の木に登って枝をかんでぶらさがっている。下で人がその人に祖師西来意を問う。」と言うものであった。道元禅師は公案の解説などはしない。一言、「なにをか人といふ」と投げかけて来る。
私たちは公案が与えられると「人が木に登って」、「それは千尺の崖上だ」、「しかも枝を口にくわえてぶらさがっている」、「そして人に祖師西来意を問われるのだ」などと頭の中に一生懸命想い、探り、迷い、もがき、苦しむ。しかしそれに対して道元禅師は単純に問いかける。「なにをか人といふ」。これほど鋭い一句はない。
「人とはどこにいるのだ」というのであり、「そんなことを考えているあなた自身とは何なのだ」ということなのである。
公案が提示されるのはほんとうのことに気づいてもらうためである。本当のことは木の上にぶらさがった者の中にあるのではない。他を探っている自分自身に気づいてみよ。
道元禅師は言う。西来意に答えて来たすべての佛祖は樹に登り樹枝を口にくわえて答えて来たのだと。私たちは祖師西来意の公案の前で為すすべがない。口を開いて答えれば落ちて死んでしまう。答えなければどうにもならない。私たちはまさにこのまっただ中にいる。
「本当の自分自身とはなんだ」と聞かれ、「何をしているのか」と問われて意味によって答えても当たるはずがない。もちろん答えなければどうにもならない。私たちはいつもこの蔓がからまった葛藤の中にいるのだ。まさに祖師西来意の公案そのものである。
しかしながら佛祖はこの葛藤のまっただ中で答えて来た。まさにその葛藤そのものが求むべきものだったのである。「葛藤窟裡、自ら出頭し来れ」、葛藤のまっただ中を自分自身で出てこい、というのだ。
香嚴禅師が大笑いしたというが、それは西来意に答えたのか、答えなかったのか試みに言ってみなさい。
坐禅は自己に徹するということ。自己に徹するということは、坐禅をしていても、食事をしていても、作務(清掃、仕事など)をしていても、独参していても、休憩していても、寝ていても、起きていても、ということ。
そうでないと、すべてが過去の経験になってしまう。坐禪をした、食事をした、作務をした、独参した、休憩した、寝た、起きた、と。ああ、よい経験をした、と。
しかし坐禅に経験はいらないのです。余計なことなのです。
坐禅は現在です。自己に徹するということは現在です。だから、決して語られることがないのです。語り始めたところから坐禅は坐禅でなくなってしまっているのです。
それが、たとえどんな自己であれ、黙々と自分自身に徹するということ、それが坐禅です。
Zazen is to penetrate the self. To penetrate the self is doing zazen, eating, working, going to dokusan, resting, sleeping, being awake. If it isn't, everything is only past experience. You did zazen, ate, worked, went to dokusan, rested, slept, were awake. "Ah! It was a nice experience." But experience isn't zazen. It's extra.
Zazen is the present moment. To penetrate the self is the present. Consequently it isn't something that can be spoken of. From the time we begin to speak about zazen, zazen disapears. No matter what condition the self is, zazen is to silently penetrate the self.