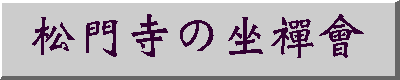
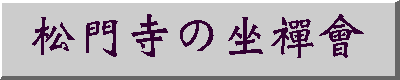
昭和五十四年十二月六日、敦賀に向かう小濱線の夜汽車から遠くの灯を見つめていた。涙が止めどもなくあふれて來た。發心寺の攝心から歸りであった。
その當時、私は一人の意氣揚揚とした坊さんであった。本山での修行を終え、都内の大きなお寺に住み込んでいた。坊さんであることにも何の疑問もなかった。本山では「一所懸命」ということを教えられた。「そんなことは誰でも知っている」という多少の疑問はあったが、それを日々のこととして努めていくことは大變なことでそれこそが修行であると言われれば「それもそうだ」ということになってしまう。またそれ以上のことを教えてくれる坊さんはいなかった。
あるとき發心寺のことをふと聞いた。「本物の坊さんがいる。」
好奇心だけは旺盛だったので、臘八攝心に出かけてみることにした。まるで物見遊山のようでもあった。私の修行の最後の攝心のつもりであった。それが私の本物の修行の入り口になったのである。
小濱は若狹灣の中ほどに位置する古い街である。奈良の東大寺の「お水取り」に水を送る「お水送り」という神秘的な儀式もある。奈良と小濱が地下で水脈がつながっているというのだ。
小濱の冬は季節風で始まる。十二月はちょうどその季節である。氣温以上に寒さが感じられる。そんな中に發心寺はあった。
しんと靜まり返っていたが、四、五十人の修行僧、尼僧、日本人、外國人が一心に修行をしている眞っ只中なのであった。
寒く、そして足は痛かった。私はその當時、ほとんど坐禪などしていなかったのである。
何の疑問もなかったが、私の「修行の最後」なのだから獨參でいろいろ質問してみることにしたのである。發心寺の堂頭老師は本堂のずっと奥に坐っていた。禪僧というイメージからはかけはなれていた。そのことが「論破できる」という氣持ちを私に起こさせた。私は質問をした。しかしながらそこに思いもかけない答えが返ってきたのだった。
その質問はいま考えてみればつまらない質問である。お坊さんと一般の人がいる中でお坊さんとはどうあるべきか、というようなことであった。「そんなお坊さんと一般の人との區別などいらない」というような主旨の答えであったと思う。納得できるものではなかった。
控室は一人の年輩のお坊さんと同室であった。坂本宗謙師である。攝心では會話は嚴禁である。しかしいろいろな話をした。私にはなぜみんながこんなに熱心なのかという基本的な疑問があった。
師には私が「修行もしないお坊さん」に見えたらしくあまり話をしたくなかったようである。しかしふと出た出身大學の話題が二人を引き付けた。師も東工大出身だったのである。師は一轉して發心寺のことを熱く語った。出會いである。
そんな中すぐに三日が過ぎてしまった。堂頭老師の答えは理解を超えていた。歸り際に獨參に行った。
「もう歸りますが、何か私に言いたい事はないでしょうか。」と言った。
「そんなものはありませんが、大事なことはあなたがあなた自身になることです。」と答えてくれた。
このことも私の理解を超えていた。
「自分自身になる。自分自身になる。」とつぶやきながら歸路についた。「でも自分自身は自分自身じゃないか。」
本物の佛教があるとしたら、ここ以外には考えられないという豫感がした。そしてそれを目指して熱心に修行する内外男女僧俗を問わない人たちがいた。
そのことがうれしくてふと涙が出てしまっていたのである。
東京に歸ってから憂鬱な日が續いた。お寺の住込みの生活もいままではなにごともなく過ぎていた。しかし私の中で何かが變わっていたのである。
一方にあれだけ坐禪を求めて修行する人たちがいた。それを目の當たりにしてしまったのである。しかし東京のお寺の日々は毎日葬式と法事に明け暮れる。同じ佛教とは思えないものがあった。同僚たちと茶飮み話をするのも苦痛になってしまっていた。部屋に籠って發心寺のことばかり考えていた。
三日經って決心をした。「發心寺へ行こう。」
「たとえ本物の修行はできなくても、發心寺で修行する人たちの中で最後の修行をしたい。三ヶ月でも半年でもいいから行ってこよう。」
このことは同僚たちあるいは兩親にはまさに「青天の霹靂」であったにちがいない。誰にも相談をしなかった。誰に相談しても分かってくれないと思ったからである。
住込んでいたお寺の住職にも傳えた。ここで私の半生でもっとも悔やまれる言葉が私の口をついて出てしまった。
「このお寺では私は單なる趣味人で終わってしまう。發心寺で本物の修行をしたい。」
怒られて當然の發言であるが、住職は鷹揚に許してくれた。「恩」というのはこういうことを言うのかもしれない。
發心寺の堂頭に電話したら、「來なさい。」と言ってくれた。お坊さんが修行するにはいろいろな手續きが普通は必要である。手續きは面倒である。しかしいまも發心寺の人たちは修行しているのである。一刻も早くとんで行きたかった。翌一月六日から始まる寒行托鉢には是非とも參加したかったのである。發心寺も手續きには寛大であった。
正月は八王子に歸って準備にあたる。兩親にも傳える。この正月を全く覺えていない。心はもう發心寺にあったのである。
一月五日朝出發。
京都から北山を抜けてずっと北に行くと若狹灣に出る。その若狹灣の眞中に位置するのが小濱である。古くは大陸との交易や北前船で榮えた港町であるが、いまは靜かに過去の歴史を傳えている。「海のある奈良」とも呼ばれ奈良の東大寺に春を告げる「お水取り」はこの小濱での神秘的な儀式「お水送り」によって初めて成立するのである。
發心寺はそんな街のはずれに位置する。毎年、發心寺の修行は托鉢で始まる。いわゆる「寒行托鉢」である。一月六日から二月三日の節分までのもっとも氣温の下がる寒中に毎日小濱市内を托鉢するのである。托鉢には一軒一軒に寄っていく「門づけ」の托鉢もあるが、寒行托鉢は二列になって道の兩側を「ホー、ホー」と大きな声を出しながら歩く。街の人々はその声を聞いて家から出てきて寄進をするのだ。「ホー」というのは「鉢盂(はつう)」といって淨戝を受ける鉢のことだというのだが、私には佛道の「法」だということのほうがふさわしいように思える。
冬の日本海側の氣候は嚴しい。太平洋側とはくらべものにならない。季節風が毎日のように雪を運んでくる。晴れることは滅多にない。托鉢も必ず合羽を着けて出かける。足は冷たさで感覺を失う。失ったほうがよいのだ。冷たさもわからないのだから。ところが手はいつまでも感覺を失わない。それでも片手は合掌、もう一方は淨戝を受ける鉢を持たねばならない。雪と風が手に吹きつける。冷たいというより、痛い。吹雪の日には淨戝ごと鉢を落としてしまうこともある。
二時間ほど歩いて休憩となる。發心寺の船大工の檀家さんが工場の休憩所を提供してくれるのだ。なによりもありがたい火である。こんなに火を尊いと思ったことはなかったかもしれない。
「動中の功夫(くふう)、靜中の功夫」という言葉がある。坐禪をしているだけが本當の功夫ではない。作務をしているときも、托鉢をしているときも功夫なのである。「自分を忘れる」という坐禪の目標からすれば、寒さに堪えるだけで「自分について考える」ひまもない寒行托鉢というのは「動中の功夫」の最高のものであるかもしれない。
こんな寒行托鉢の前日に發心寺に跳び込んでいったのだ。發心寺の堂頭(住職、坐禪指導者)は私に聞こえるように「あの人は懲りてすぐ歸るよ」と、冗談めかしていつも言っていた。そんなことを言われて歸れるわけがない。今思えばそれは多分堂頭のいつもの作戰だったのである。
こんな寒行の最中でも坐禪は毎日續けられる。獨參の鐘も毎日のように鳴る。その頃は外國人の修行僧と僧となっていない居士も十人くらいいた。日本人もあわせて全部で二十人くらいであったが、だれもが鐘が鳴ると獨參に思い詰めた眼で向かっていった。
最初に同室になったのは日本語の達者なブラジル人と日本語のできない日系カナダ人の雲水であった。ブラジル人は日本語が驚異的にできた。なにしろ漢和辞典を手に漢文を讀むのである。二人とも堂頭との出會いを私に熱く語ってくれた。
もともと「僧」という言葉はサンガという古代インドの言葉が中國語に音譯され「僧伽」となりさらにつづめられたものであり、「集まった人々」という意味なのである。發心寺にはほんとうにさまざまな人たちが集まっていた。
曹洞宗の本山は福井の永平寺と横濱の総持寺である。これらの本山にも大勢の修行僧がいるが、多くは寺院の子弟である。寺に生まれて曹洞宗の大學に通いそれから本山で修行して寺院の住職となるわけである。彼らの中に自分から進んで修行に來たものは少ない。お寺を繼ぐためには修行もしなければならない、ということである。本山に半ば強制的に修行をさせるという「嚴しさ」の生まれる由縁でもある。
しかしながら本當の「嚴しさ」とは、自分が自分自身に課す「嚴しさ」ではないだろうか。その人がみずからと向き合い一心に修行しているとき、誰もがその人に強制的になる必要はないのである。發心寺では誰もが自分自身と向き合っていた。そしてその空氣を保っていた。
あるアメリカ人の僧はもとバーテンダーだったが、日本に觀光旅行できた時に發心寺に寄って以來發心寺に住みつくことになった。十数年ぶりにアメリカに歸ったとき元の戀人が待っていたというが、構わず日本にまた來てしまっていた。
フランス人の僧は、日本に興味を持って宮大工のところで大工の修業をしていたがふと坐禪をしたのがきっかけで發心寺に來た。大工道具を一式持っていて發心寺の修繕係となっていた。私もよく鉋の刃の研ぎ方などを教えてもらったものである。
南アフリカから來たテレビ局員は現地で何を見てきたのか非常に焦燥した目付きで來た。山を驅け囘ることがとても好きでいつも木の實などを持って來てくれた。そうこうしているうちにだんだんと眼も穏やかになり、發心寺でずっと修行したいといっていた。しかし當時の南アフリカには人種差別の問題が在って各國から非難されていたので、彼に長期のビザはおりなかった。出家すればビザもおりるかもしれないと出家したがかなわず南アフリカに歸っていった。
あるドイツ人は本名をアドルフといった。戰後のドイツでアドルフは重い名前である。彼はのちに出家したが名前ゆえのいろいろな問題があったのかもしれないと思う。
それぞれがそれぞれに坐禪に向かっていた。そんな中にひとりの日本人(私)がお氣樂にまだ坐禪を續けていた。
日本人にもさまざまの修行僧、居士(僧ではないが修行僧と一緒に修行する人たち)がいた。永平寺などではほとんどの修行僧が寺院の子弟で占められているが、當時の發心寺には登校拒否の高校生からアルコール中毒が少しよくなった人、東大を中退してきた人など多彩な人たちが全國から集まっていた。
發心寺の修行僧も寺院の子弟は少なくいろいろなきっかけで普通の人から修行僧となった人たちが多かった。その中に「道林(どうりん)さん」と呼ばれる一人の修行僧がいた。
暮れの發心寺に初めて來たときの攝心については以前に書いたが、そのときに坂本宗謙師が「あの人がこの中で一番優秀な人だ。」と言っていたその人である。「この人が優秀な人?」といぶかしく思ったのを覺えている。いままでに私が出會ったいわゆる優秀な人とはまったく違っていたのである。
發心寺で「優秀な人」と呼ばれるのは、「見性(けんしょう)」しているということである。「見性」するというのは自分の本性を徹見する、つまり悟りを開いているということである。「見性」とか「悟り」について勝手なイメージを持っていたからかもしれないが、およそそうとは見えない人であった。
「トラックの運轉手をしていたんだ。」みなが噂をしていた。本人も否定はしなかった。しかしどうしてここへ來たのだろう、疑問は沸いてくる。部屋を訪ねてみると「白隠禪師息耕録開筵普説講話」などという分厚い本をじっと讀んでいる。當時の私にとっては最初の一行目から何やらちんぷんかんぷんの本である。何か他の修行僧にはないものが感じられた。
發心寺の堂頭老師との出會いは大きい。しかし發心寺の堂頭老師から法を傳えられた人が目の前にいるということも私にとってもっと大きなことであったかもしれない。法が實際に傳わっているのである。
道林師はいつもいろいろな祖録の一説を大きな声でつぶやきながら歩いていた。そのときも道林師はつぶやきながらむこうからやって來た。そしてすれちがった。
「身心脱落、脱落身心」
これは道元禪師が師匠の如淨禪師に述べたといわれる言葉である。この言葉がしばらく耳に殘った。
「身心脱落、脱落身心?」
このとき私の中で何かが轉囘するのである。「要するに自分自身がどうなんだということなのだ。」
それまでは「禪」とか「悟り」とかは探求すべき對象物であった。「でもそうではないのだ。」
發心寺では四月から六月までと十月から十二月までの月初めの七日間攝心修行がつとめられる。攝心は接心とも書き、朝起きてから夜床につくまでずっと坐禪三昧の日を過ごす。普段の發心寺の生活には作務といって屋内の清掃、庭の草取りをしたり、薪を割ったりいろいろな仕事があるが、それも攝心の間は坐禪になる。文字どおり自分自身の心に接する大修行なのである。
北陸の春は四月初めにはまだ來ていない。花もなく、肌寒い中に肅々と攝心は始まる。獨參の鐘は一日に何囘も鳴り響き、大勢の修行僧が張り切って出かけていく。皆攝心になると眼が眞劍になっていく。心に期すものがあるようだ。
獨參では堂頭老師と一對一で向き合う。坐禪の質問をするのもよいが、普通は自分の見解を述べて正邪を問う。それぞれが坐禪とはこういうものだと思いこんでしまっていることにはなかなか自分自身では氣づきにくいものである。それらが指摘されていく中に修行の方向が見極められていくのである。
私の中にも密かに期するものがあった。何かに氣づいていることは確かである。それを獨參でぶつけてみようと。獨參の鐘が鳴る。我先にと出て行く人もいる。私はこう言おうと決めているものがあった。心の中でそれを繰り返してみる。いよいよ私の番である。順番を待っているところからずっと奥に堂頭老師はすわっている。礼拜して目の前にすわりそして言った。
「身心脱落し來る。」
この言葉は道元禪師が師匠の如淨禪師に認められたといわれている言葉である。言葉に間違いはない。
「いいですねぇ。」
意外な言葉が返ってきた。もうこれでよいということか、こんなものでもういいのか、という考えがふと頭を過る。そのとたんにまた言葉が飛んで來た。
「でも、いつ脱落しました?」
いつと言われても、と思う。言葉に詰まる。詰まっているとまた言われた。
「門より入るものは家珍にあらず、縁によりて得るものは始終成壞す。」
無門關の序の言葉である。
「門より入るものは家珍にあらず、縁によりて得るものは始終成壞す。」
「門から入ってきたものはその家の本當の宝物ではない、また因縁によって得たものは必ず失われる。」ということは、學んで得たもの、研鑽して積み重ねてきたものはその人の本當の宝ではない、そういうものは必ず失われてしまうということなのである。さらに進んで言えば「身心脱落」が得たものであったならばそれは眞の「身心脱落」ではないというのである。
やはりそうか、と思う。禪なんてそんなあまいものではないはずだとも思う。まだこの發心寺に來てから四ヶ月もたっていない。昔の祖師がたには二、三十年も修行されたかたが大勢おられる。そんなに簡單に見性できるはずがないのだ。
發心寺の攝心には各食後に空いた時間が一時間ほどある。もちろんその間も坐禪に専念する人たちも多い。攝心中は會話や外出は嚴禁であるが、部屋で過ごしたり、境内の散歩をしたりする人たちもいる。
北陸の四月はまだ春とはいえない日が多いが、その日は珍しく晴れていた。太陽のない長い冬を過ごした者には太陽は本當にありがたく見えるものである。鐘樓のそばに小さな花壇があってそこはひなたぼっこの絶好の場所であった。
堂頭老師の言葉の余韻がある中、冷え切った身体をあたためようとそこに行った。太陽がまぶしくふりそそぎ、花壇にも園芸種の花がいくつか咲いていた。蝶もわずかな花を求めて飛んでいた。空氣はまだ冷たかったがそれは春の日であった。
そのときふと思ったのである。
「家に歸ろう。」
思えば、當初の目的は發心寺の修行僧の中で修行をしたいということだったはずである。坐禪を自分のものにしたいなどとは思ってもみなかった。とりあえず當初の目的は達成したのである。禪ということもまわりの人たちに觸發されて自分なりに一所懸命になってみたが、所詮付け燒き刃のようなものであった。
外にはこんなに明るい春の日がある。坐禪などということは忘れてこの春の日の中を生きていくのだ。「これで家に歸ることができる。」
休みの時間も終り、心も輕くなって攝心に戻っていった。まだまだ攝心は續くのである。しかし後で考えれば、この瞬間が坐禪の本當の入り口だったのである。
もうお氣樂なものである。なにしろふんぎりがついていたのである。この發心寺のように一心に修行を續けておられる尊い方々がおられる。そういう人たちをよりどころとして、私の坊さんとしての存在も保証される、そんな勝手な考えであったように思う。
人はいつも存在理由を求めてしまう。人生の意味を求めてしまう。それがたとえ砂上の樓閣のようなものであっても自分自身がその氣になってしまえばよいのである。自分自身をだましてしまえばよいのである。そしてだましたことにさえ氣づかなくなっていく。確固たる存在理由のためにはだましていることに氣づかないことが重要になる。だからこそなんでもない自分自身「本來の自己」に氣づきようがないのである。
そんなところに堂頭老師の口宣(くせん)が飛んできた。
口宣というのは攝心や坐禪の最中に祖師がたのエピソードとか祖録の話とか諸注意とかを手短に話すことである。當時の發心寺では一日に一、二囘口宣があった。
「このなかにわかりかけてきた人が何人かいる。そのわかったところを捨てて坐りなさい。」というようなことであった。
「わかりかけてきた人?」「何人か?」・・・「わかりかけてきた人」の「何人か」は誰だろう。まさか私ではないだろう・・・でも獨參で「いいですね。」と言われた・・・
發心寺の雲水も外部から攝心に參加した僧も一般の人も獨參で我先にと争うようには出かけていく。しかし堂頭老師に何を言われたのか歸りの足は重い。しょんぼりとしてとぼとぼ歸っていく樣子だ。何を言われたのか知らないがあんなにしょんぼりすることもないじゃないか、とも思っていた。だからその人たちと私は違うとも思っていた。
もしかしたら私はその「何人か」なのかもしれない・・・そういう思いが一瞬頭をかすめたのである。
一度坐禪のことはあきらめた身である。もちろんだめでも失うものはないのである。もう一度獨參にいってみるか・・・もう一度獨參にいってみよう・・・
それからは獨參の始まりの鐘、喚鐘が鳴り始めると必ず獨參に赴いた。しかしながら來る日も來る日も埒があかない。何を言ってもだめであった。出版されている臨濟宗の公案の解答集の解答を持っていったこともあるが、「それはここでは通らない」と簡單に言われてしまったのである。いつしか四月の攝心も終わっていた。
發心寺の日常の生活は一日中、作務という作業に明け暮れる。薪を割ったり、畑仕事をしたり、墓地の草刈りをしたりなかなかの勞働である。そして朝と夜に坐禪を二、三時間する。そのときにも獨參の鐘は鳴る。
月に三囘午前中、市内に托鉢に出る。そんな中でも頭は獨參のことでいっぱいだった。何を獨參に持っていったらよいのか。祖師がたの故事來歴もしらみつぶしに調べた。竹に小石が當たって悟ったという故事や、石につまずいてその痛みで悟ったという故事から何か轉機のようなものが來ないものかと待ちわびたこともある。
しかしそんなものは來るはずがないのである。他人の故事を探ってみてもそれはあくまでも他人のことなのである。坐禪はあくまでも自分自身のことなのだ。そのことをすっかり忘れてしまっていたのである。
そのような時にも堂頭老師は口宣で私を励ましてくれているようであった。少なくとも私にはそう聞こえた。「柿は熟したら必ず落ちる。自分という力を用いなければ必ず落ちる。この中にはもう落ちようとしている人がいる。」
日々の獨參も過ぎてゆき五月の攝心も始まっていた。いつしか坐禪が自分のものとなっていた。「肯心みずから許す」という言葉がある。それは最後には悟ったということを他人が認めるのではなくて、自分自身で確信する、ということである。それは間違いようのないものであった。
獨參に行って三拜して堂頭老師の前に坐った。堂頭老師はしばらくして「しっかり坐ってください。」と言った。私は三拜をして退いた。