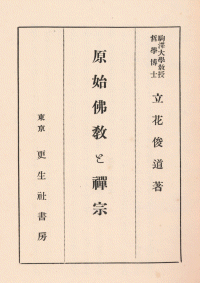
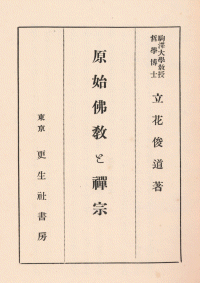
大正15年5月10日發行 發行所 更生社書房
二千五百年前釋尊によりて印度に起された佛教は印度支那日本と順次流傳する間に幾多の宗派に岐れ、今日に至つては根本の佛教は殆ど忘却せられて枝末の宗派のみ重大視せらるるかの觀がある。事實上今日の佛教は皆その一班を教ふる宗派のみであつて、その全貌を説く佛教なる普遍名詞を以て呼ばるべきものではないのである。
釋尊の根本の教とは一體何であるか、佛教の根本經典とは一體何であるかは容易く解答し得られざる難問題であるが、その根本の教理は現存せる各種の聖典中、巴利文の尼柯耶とそれと對應せる漢文阿含部經典の中に最も多く見出さるべきことは何人も異議なき所であらう。
本書の目的とする所は先づこの根本經典の中に原始佛教の意義を探り、更にそれが今日の禪宗と如何なる關係を有するやを分明にせんとするにある。これを企つるの意は禪宗は常に佛法の總府を以て自ら任じて居るが故、一には如何なる程度までこの自信が正當視し得らるるやを觀、且つ現存せる宗派佛法中、禪宗は最も多く原始佛教の面影を保てるものと信ぜられて居る故、今日の禪宗の上に原始佛教の面目を彷彿せしめんとするに外ならない。これ等兩者の關係を明瞭にし、原始佛教は如何なるものなるやが幾分にても分明にさるることを得ば本小篇の世に出づる意は十分足れりとして可。
本書第一篇の初めの一部に對しては友人木村泰賢君の『印度哲學宗教史』に負ふ所が少くない。此處に記して同君に謝意を表する。
大正十五年三月
立花 俊道 誌
原始佛教より禪宗へ・・・原始佛教と禪宗・・・原始佛教とは何ぞや・・・その終り・・・原始佛教研究の資料・・・巴利文學・・・吾人の依らんとする資料・・・原始、根本、初期の佛教・・・南方佛教、巴利佛教・・・一般印度思想と原始佛教・・・ヴェーダ・・・ブラーフマナ・・・ウパニシャッド・・・苦行、種族制度・・・現身涅槃・・・大乘と婆羅門教・・・禪宗
四種のヴェーダ・・・佛典にては三ヴェーダ・・・アタルヴァヴェーダ・・・マヌの法典にても然り・・・ヴェーダとは何ぞや・・・ヴェーダは一種の神話である・・・ヴェーダ神・・・火神アグニ・・・雷雨神、武神因陀羅・・・曙の女神ウシャス・・・夜の女神ラートリー・・・天地神・・・ヴェーダ神の特色・・・佛教の神神・・・佛教神話の道徳性・・・高き地位を奪はれたるヴェーダ神・・・その三の理由・・・『大會經』・・・『阿②那智經』・・・佛教文學に描き出された帝釋天・・・人情美に富める帝釋天・・・帝釋天は何故に佛、佛弟子に劣れりや・・・梵・・・祈祷主から祈祷・・・佛教の梵天・・・ヴェーダの神は何故に地位を下げられたか・・・『堅固經』の例・・・梵天は智徳共に佛に劣る
宗教思想の變化・・・儀式及び犧牲の力・・・儀式の神秘・・・佛教と儀式・・・犧牲・・・佛教より見たる犧牲
種族の觀念と起源・・・上三族・・・首陀族・・・巨人歌・・・佛教と種族
解脱の道・・・苦樂の兩端・・・佛も苦行を行はれたり・・・苦行の種類・・・苦行・・・佛教も今日の吾人の眼には苦行主義
ウパニシャッドとは何ぞや・・・ウパニシャッドは如何にして生れたるか・・・智慧の位置・・・ウパニシャッドの主觀主義・・・一、智慧は道徳に優る・・・二、智徳竝行・・・三、智者道徳的差別想に累せられず・・・佛教の智・・・無差別の境・・・佛教は倫理的宗教なり
眞言密教・・・淨土教の阿彌陀・・・兩大學者の考證・・・彌陀はアフラ、マヅダなり・・・禪の外來の分子・・・眞如と梵・・・梵とは何ぞや・・・世界の第一原因としての梵・・・梵の定義・・・梵は造化者・・・梵の兩面と眞如の兩面・・・諸法實相と事事無礙
原始佛教の無我説・・・小我か大我か・・・無用の戲論・・・婆蹉普行沙門・・・我とは如何なるものか・・・禪者の『我』・・・禪者の悟と梵我一體
三學竝進か、戒先慧後か・・・禪那と三昧・・・神秀と慧能・・・禪門より小乘戒を見るに二法あり(一)・・・『禪戒鈔』と『聖薄伽梵歌』・・・唯心、實相と『我』・・・禪戒と教戒・・・禪門より小乘戒を見るに二法あり(二)・・・清規と小乘戒
佛の語義・・・辟支佛とは何ぞや・・・縁覺は誤譯・・・諸種の佛身・・・法身佛報身佛・・・現身佛・・・誕生・・・四門出遊・・・出家・・・苦行・・・成道・・・成佛の宣言・・・佛は如何に自身を見られしや・・・禪門の佛・・・禪の現身佛
三寶とは何ぞや・・・歸依三寶・・・自燈明法燈明、自歸依法歸依・・・一個の比丘は一個の佛・・・佛教は行の教なり・・・僧とは何ぞや・・・福田・・・僧寶讚仰・・・四種の門
殿堂・・・造像の初に關する傳説・・・形色音聲を以て佛を見る能はず・・・造像の始・・・佛の四大遺跡・・・祗管打坐・・・那伽大定・・・僧院主殿堂從
寒岩枯木の境・・・牛角沙羅林中の挿話・・・陀尼耶と佛との問答・・・雨の情趣・・・雷雨中の修養・・・自然との親み・・・禪僧の自然・・・原始僧の見たる自然
羅漢果は佛道修行の目標・・・出家・・・階級を經ずして得る悟・・・得法淨眼とは何ぞや・・・在家者には阿羅漢果は得られず・・・在家人の涅槃・・・菩薩とは何ぞや・・・菩薩の意義・・・原始佛教の菩薩・・・菩薩の地位・・・菩薩思想の一轉化・・・羅漢の利他心・・・禪宗は羅漢道(一)・・・禪宗は羅漢道(二)
自己燈明自己歸依所・・・自力主義・・・聲聞・・・和尚・・・阿闍梨・・・優婆塞・・・ウパニシャッド・・・入門式・・・出家受戒・・・聞經、傳經・・・聲聞はこの意味に於ては自利者なり・・・自律道徳・・・佛教の倫理的自律・・・倫理的自力・・・宗教的自力・・・禪宗の自力主義
禪と念佛・・・禪と未來往生・・・禪は一世一道・・・原始佛教の現世主義・・・二種の涅槃・・・無餘涅槃・・・涅槃の同義語・・・佛の主として説かれたるは有餘涅槃・・・禪生活の妙境
實踐躬行主義・・・禪の實行主義・・・簡素なる生活・・・食物・・・住所・・・比丘尼の止住所・・・禪僧の簡素主義
『原始佛教と禪宗』といふ、これを一箇の研究問題として見れば、これには大體二の方面あることが見出されるであらう。その一は歴史的で、釋尊によりて初めて起されたる佛教、即ち初期の佛教、根本佛教、原始佛教が如何に發達して今日の禪宗になつたかと云ふ、その發達の過程を尋ねるもので、これは禪宗の教理史であり思想史である。この場合吾吾はこの問題を單に『原始佛教と禪宗』と呼ばずして『原始佛教より禪宗へ』と呼ぶの一層適切なることを感ずるものである。佛教各宗は何れもその源流を原始佛教に發したものであるとすればこの歴史的の研究は啻に禪宗ばかりでなく、各宗ともに必ずあるべきものである。『原始佛教より眞言密教へ』『原始佛教より淨土教へ』といふことも勿論なくてはならぬ。而してこれ等の場合にありては原始佛教が如何なる發達をなして今日の眞言密教なり淨土教なりとなつたか、此處でその發達の過程が探求されるのである。或は眞言密教や淨土教は歴史を超越して居る、隨つて原始佛教とこれ等とを結びつけるべき必要もなく、又結びつくべき何物もない。或は又これ等は原始佛教時代からして、若しくは自然法爾に眞言密教であり淨土教であつたといふものがあるかも知れぬが、斯ういふ一切藏經皆佛説論や超歴史論之今日に於て一顧の價だに有せざることは吾が禪宗門に傳はれる靈山會上の拈華微笑の談の何等歴史的價値を有しないのと變る所はない。佛教各宗はその起源又少くもその關係を原始佛教に求めなければならない。而して原始佛教との關係が濃厚であればあるほどその宗派は佛教的であるといはれねばなるまいし、之に反して原始佛教との關係が希薄であり、外來の分子を含んで居ることが多ければ多いほどその宗派は非佛教的であると云はれねばならぬであろう。
二種の方面の第二は此の中間の歴史的過程を考察することを止めて現存のままの原始佛教と禪宗とを比較せんとするもので、前なる方面を歴史的と呼びたるに對し、これは單に比較研究と稱せらるべきものであろう。この場合ではこの問題を單に『原始佛教と禪宗』として取扱つて差支がない。前者では原始佛教より禪宗までの教理又は思想の成長發達の經路を探るのがその目的とする所であり、後者では未だ何等の成長發達をもなさざる原始佛教と既に成長發達を遂げたる禪宗とを比較せんとするものである。原始佛教と禪宗との兩者が如何なる程度まで共通の點を有するか、如何なる點に於て相背馳するか、禪宗は佛教の正脈であるといひ、總府であるといふ、若しさうだとすれば禪宗は佛教各宗中原始佛教と最も濃厚なる最も密接なる關係を有つて居るべき筈である。この禪宗は佛教の正脈であり總府であるといふ語が如何なる程度まで正當と認め得らるべきや、それを考察するのが二種の方面の第二で、これはまた同時に本編の目的とする所である。
原始佛教、根本佛教、又は初期の佛教などといふ語がよく用ひられて居るが、一體何が原始佛教であり、根本佛教、初期の佛教であるか。これ等の語の確かなる定義を與ふることは困難であらうかと思ふ。先づ歴史の上からいへば、佛教の初とは佛が初めて法を説かれた時であらうか、若しくは更に溯つて佛の成道とか、成佛の宣言とか出家とか誕生とかの何れに初まるとすべきものであらうか。即ちこれ等佛傳の上の事實は何れも原始佛教の範圍内に含まれるべきものであらうか、判然とは判らないのである。誕生と出家とはともに佛の事ではあるが、佛がまだ佛となられない前の事で、正當に佛教歴史の初であるかといふことになると、問題はよほど難解なものになりはしまいか。佛が佛となられたのはその成道の時であるが、この時は單に佛となられたに止まつて‐所謂自受用法樂の時で、佛に自分は佛になつたといふ自覺は勿論あつたらうが佛となられたことを他に向つて宣言されたわけでもない。佛がこれを宣言されたのは稍々後の事である。佛が成道後ブダガヤを引上げて鹿野苑に赴かれる途中阿耆毘迦‐活命外道のウバカ(中阿含、『羅摩經』では優陀、『五分律』では優波耆婆)といふものに逢ひ、彼の問に答へ、彼の疑を解くために自分は三藐三佛陀即ち正等覺者であることを宣言された。『羅摩經』に『自覺無上覺』とあるがこれにあたる。これが佛が自分は佛になつたといふことを他に向つて宣言された第一の場合である。しかし又佛が『轉法輪經』を説いて、その教を具體的に纏つたものとして發表されたのは鹿野苑初説法の時である。それで佛教歴史の初はこの初轉法輪即ち故リス・デビヅ教授の所謂『正法王國の建設』でなければならないやうだが、しかし一面から見れば佛が悟を開かれた時即ち佛たるの自覺を獲られた時が佛教史の正當なる初であるやうにも思へるし、或は又佛が自分は佛となつたと他に向つて宣言された時が佛教の初であるやうにも思はれる。
原始佛教の初を定むることは斯の如く困難であるが、その終を定めることは更に困難なことである。判り易くいへば釋尊一代の間だけを原始佛教といつたものであらうか、更に又第一結集とか第二結集とか第三結集とかいふものもこれに含めたものであらうか。第一結集は佛滅後間もなく行はれ、これには大して異議を唱へるものもなかつたが、夫から百年を隔てて行はれた第二結集には異議者が大分現はれた。所謂『十事の非法』なるものが毘舍離城なる伐地子の比丘等によりて正當として主張されたのであつた。夫から佛滅後四百年の間に小乘は二十部の多數に分裂した。原始佛教とはこれ等の總てを一所にして名けたものであらうか。吾吾は原始佛教とは原始時代の佛教、古い佛教、初期の佛教と解し、場合によつては阿含佛教、小乘佛教、南方佛教又は巴利佛教などと同一視して居るけれども、歴史の上に的確に時期を定めることになると殆ど不可能の事になりはしないかと思ふ。
以上は時間の上から的確な定義を下すことの困難なることを述べたものであるが、更に今日に殘つて居る材料に就ていうと、吾吾は何れと何れとを原始佛教の研究材料として取るべきやといふ難問題に遭遇することを覺悟しなければならない。巴利佛教聖典全部を原始佛教研究の資料と見るも如何であらうか。巴利佛教聖典とても後世の作、佛滅後數世紀或は十數世紀の間に出來たと思はれるものもないではない。隨つてその全部を原始佛教の研究資料と見るかは穩かではあるまい。嚴密に云へば原始佛教の研究資料たる巴利聖典は唯その幾分である。しかし何れと何れとが果してその所謂幾分であるかは亦容易く解答することが出來ない。
斯うして時間の上からいつても、その研究資料の上からいつても原始佛教と非原始佛教との間の境界を定めることは非常なる難事である。最も古き時代に説かれ、又は集められて今日に殘された聖典によつて傳へられたものが原始佛教である、と斯ういふより外に更に的確なる定義を下すことは到底不可能の事であるかと思はれる。唯吾人は當面の便宜上竝に必要上、釋尊及びその直弟子によつて説かれ、滅後直に行はれた第一結集の際に集められたと言ひ傳へられて居る聖典によれる佛教を指して原始佛教と呼ぶのである。即ち時間の上からは釋尊の成道若しくは初轉法輪の時から入滅後間もなき間、數十年の事であり、研究資料の上からは巴利聖典中の經律二藏の中、後世の作と思はれるものを除ける部分と、漢譯中これに適應する部分とに依らうと思ふのである。
上に原始、根本、初期の佛教、南方、巴利、阿含、小乘佛教など種種の文字を用ひて來たが、これ等の異つた語は皆同じものを指して居るであろうか。余の考によればその間に多少の相違があるやうである。原始、根本、初期の佛教といふは多少意見を異にする人もあらうが、大體同一物を指して居るであらう。これ等は阿含佛教又は小乘佛教と呼ぶ時と同じく巴利漢譯兩者からその研究の資料を提供されて居る。但し阿含佛教又は小乘佛教の名が一はその研究資料の限定されて居ることを示し、一はその内容の限定されて居ることを示せるに反して、原始、根本、初期の佛教といふ名はその内容も研究資料も、更に又最も重要なる問題たる歴史上の範圍も判然限定し得られないといふ相違あるのみである。南方佛教、巴利佛教といふ名は言ふまでもなく現時南方佛教諸國に行はれて居る佛教を指せるもので、學者によつてはこれを原始佛教と同一視するものもあるが、これは勿論穩當ではあるまいと思ふ。南方佛教といふは北方及び東方に行はれて居る佛教、大乘佛教と區別するために南方地方‐錫蘭(セイロン)、緬甸(ビルマ)、暹羅(シヤム)、柬蒲塞(カンボヂヤ)、老①(ラヲス)の地方に行はれて居る佛教に與へた便宜的の名稱で、これも決して的確な科學的な名稱とは云ひ難い。これはサー・チヤールス・エリオツトの云へる通り巴利佛教と呼ぶのが寧ろ適當である。
原始佛教はいふまでもなく釋尊の創始に係るものである。佛の初めて開創された教である。他の方面からいへば佛教の興起は全く佛の力、佛の獨創力によれるものである。しかし獨創の力に富み偉大なる痕跡を今日に殘された佛だとて時代の風潮と全然沒交渉であり一般の潮流より超然として言つたり行ふたりするわけには行かなかつた。佛はこの潮流に乘じてこれに順應して進まれたか、若しくはこれに背いてその逆轉を計られたかでなくてはならぬ。而してその態度の順逆何れにあるにせよ、その活動の極めて目覺ましいものであつたらうとは佛の傳記に就て何等の智識も有しないものでも容易く想像し得るところであらうし、事實またさうでもあつた。吾人は本論の劈頭に於て有史以來の印度思想の特色を擧げてこれを原始佛教の思想と比較し、兩者の如何なる點に於て相一致せざるやを明にしたいと思ふ。語を換へて言へば印度最古の文學たるヴェーダ(Veda)以下の印度の正系及び傍系思想を辿つて原始佛教の思想と比較しその相違せる點を明にしようといふのである。斯うすると佛教外の思想をその背景として描き出すのであるから原始佛教獨特の思想は自ら明瞭に現はれて來るであらう。これは原始佛教の思想を明にすることであり、同時に又禪宗の思想を明にすることである。
ヴェーダの讚歌には多くの神が現はれて出た。これ等の神神の中或ものは原始佛教の中に取り入れられてその神話と世界説との中に仕組まれて居る。しかし原始佛教内に於ける彼等の位置は低下して人間と同等若しくはそれ以下となつて了つた。ヴェーダの次に出たブラーフマナ(Brahmana)の時代では印度人は極度に祈祷の效力を信じた。彼等はヴェーダ時代の印度人がなしたやうに外に向つて神を讚仰し神に祈祷し神に犧牲を供してその威力に賴ることを止めて、主觀的態度を取り、祈祷の力を信じ、その力を以てしては如何なることをも成し遂げ得られると信ずるやうになつた。それからウパニシヤツド(Upanisad)の時代が來た。これは歴史上佛教の興起の少し前から初まり佛教の興起當時も勿論繼續して居た。この時代は印度人の思辯空想の盛なりし時代で、その反響の一端は佛教文學の中でもこれを窺ひ知ることが出來る。この思想を佛の實際的眼、實行を重んずる見地より見れば世にこれほど無用の閑事はなかつたのである。隨つて佛は極力これを排斥された。この外古來印度人の最も重要視したる苦行の如き、佛は解脱を得るに要なしとしてこれを排斥され、全世界中印度特有の制度として今日尚ほその存在を續けて居る彼の種族制度の如き、佛は四海四民平等主義の理想に戻るものとしてまたこれを排斥された。斯の如くして佛は佛出世以前及び佛在世當時の印度人が最も重要視したるものをば悉く排斥して自身は戒定慧の三學、無常無我苦の三特相、苦集滅道の四諦、正見正思惟正語正業正命正精進正念正定の八正道によりて現身に解脱涅槃を得るの可能なることを説き教へられた。即ち佛教は婆羅門教の神秘的迷信的哲學的宗教的なるに對して極めて倫理的合理的人間的常識的である。
然るに後世の大乘教となるに及び、佛教は原始時代に一旦背いた婆羅門教に還り、世界觀の上では汎神論を取り、實我説を取り、證悟契當はその實我を徹見することであると説明するやうになつた。即ち佛教は或意味に於ては婆羅門教と變らないものとなつて了つたのである。しかし斯うして非常な變化に逢つた佛教の中でも禪宗は原始佛教の面影を保有することの特に多き宗派である。吾人が本編に於て兩者の近い關係を明にせんと試みる所以の理は亦此處にある。そこで本編は
第一篇 古代印度思想と原始佛教
第二篇 禪宗と婆羅門教
第三篇 原始佛教と禪宗
との三篇より成る。これによりて兩者間の關係を出來るだけ明瞭に説き明したき考である。
ヴェーダ(Veda)は現存せる印度歐羅巴文學中最も古き文學であつて、その成立年代は或は西紀前六千年より三千年の間とされ、或は西紀前千三百年より千年の間とされて居る。通常リグ(Rig)ヤジユル(Yajur)サーマ(Sama)アタルヴァ(Atharva)の四を合わせて四ヴェーダと稱するけれども、アタルヴァヴェーダのヴェーダの正經として認められるやうになつたのはよほど後世の事に屬するらしく、佛典の中では通常三ヴェーダの語を記し、アタルヴァの一を除くを例としてある。『諸經要集(スッタニパータ)』九二七偈の中に
『アータッバナ(Athabbana)の法は行はず、夢や相の占をも星術をもこれを行はざれ、吾が屬徒たるものは鳥獸の聲を判じ、病を醫し、妊娠の法を行ふことなかれ』
といふ文句があるが、佛の時代ではこれは單に病を癒したり、災難を避けたり、或は戰爭の起つた時敵中に惡疫を流行させたり災禍を下したりする法を説いた魔術の書と見做されて居て、他の三ヴェーダと同一に見られるべき權威ある經典とは認められては居なかつたのである。しかしこれは單に原始時代の佛典の中ばかりでなく、ずつと後に出來たとされて居るマヌ(Manu)の法典の中でさへ常に『三種の永久のヴェーダ』(trayam brahma sanatanam)の語を用ひてアタルヴァの一を除外するのが常である。同法典中唯一箇所(一一の三三)
『彼(婆羅門)をして躊躇する所なくアタルヴァン(Atharvan)及びアンギラス(Angiras)によりて啓示されたる聖典を用ひしめよ、語は實に婆羅門の武器にして彼はそを用ひて己の敵を屠ることを得』
といひ、アタルヴァン及びアンギラスの與ふる天啓の事を記してある。しかし尚ほアタルヴァヴェーダの語は用ひてない。先に擧げた『諸經要集』にアータッバナとあるはこのアタルヴァンの子孫の意である。
ヴェーダは一體如何なる性質の書であるかといふと、こは古代印度人が神を祭る時に唱へた讚美歌及び祈祷歌を集めたもので、彼等が祭を行ふ場合には祭火の中に醍醐(ギー、Ghrita)を溶かしたものを投じ、祭草の上に蘇摩(ソーマ、Soma)の液汁を注ぎ同時にこれ等の讚美歌及び祈祷歌を唱へて神を宥め讚め又は祈つたものであつた。これ等は何れも古來の敬虔なる詩僧(リシ、Risi)が作つて記憶によつてその家族に傳へたものであつたが、異れる時代に作られ異れる家族によりて傳へられたものが次第に寄せ集められてリグヴェーダ以下のヴェーダの形をなすやうになつたのである。
ヴェーダは斯うして讚美歌又は祈祷歌を集めたものであるが、これは同時に又一種の神話であつてこの中には自然界の現象又は力に神格を與へこれを神として崇めてある。古代印度の神といふは多くこれであつた。これ等の神は多くの點に於て人間に類似しその身體の形状、社會の階級、相互の家族的職業的關係は人類のそれ等と大體似て居るやうに描き出してある。彼等は本來死すべきものであつたが、蘇摩の酒を飮み、又はアグニ(Agni)及びサヴィトリ(Savitri)から贈物としてこれを受けたので、不死の身を得たといつてある。唯しかしこれ等の神神は一方から見れば多少異れる時代に現はれた多くの詩僧が各各獨特の詩想に任せて自由に描寫したものであるから、各神相互の關係は至つて混雜して居てその間には殆ど統一といふものがない。多くの神は力光輝恩惠智慧の如き屬性を他の神と共通に所有して居る。隨つて一の神を判然と他の神より區別することの出來ない場合が多い。而してこれ等の神神の人間に對する關係はといへばそはそれ等が代表する自然界の現象又は力の人間に對する關係と略ぼ同一なることを思はしめる。例へば火、特に祭の火に神格を與へて神となしたるアグニ(Agni)はグリハスパチ(Grihaspati)即ち家の主人と呼ばれ、人間の家のアチチ(Atithi)即ち客と呼ばれる。或は僧(Ritvij; Vipra; Purohita; Hotri; Adhvaryu; Brahman)即ち人と神の間の仲介をなすものと呼ばれる。これは祭の時火中に投ずる醍醐(ギー)その他のものは火によりて天上の神に運ばれ、斯くして祭の火は神人兩者間の仲介をなすこと僧の如くなりと信ぜられたからである。
因陀羅(インドラ、Indra)は初めは雷雨の神として旱魃と暗黑との惡魔を除くものとされたが、後には戰の神としてアリヤン人(Aryans)が非アリヤン人即ちダーサ又はダシュ(Dasa, Dasyu)と呼ぶ黑色の蠻人と戰ふに力を添へる。この神は力強き武士として武士族のもののために崇拜される。ヴェーダ時代の數多き神神の中で最も重要なる神に非れば確かにその中の一で、リグヴェーダの讚美歌の中約四分の一はこの神を讚め又はこの神に祈るためのものであるといふ。人類に最高の利益を下すものであるが、同時に又肉慾的で粗暴で不道徳的である。
ウシャス(Usas)は曙の女神であつて水浴から出て來たもののやうに美はしく生生として東天に現はれ夜の黑き幕を取拂つて暗黑を除く。この女神は齡古くはあるが再再生れることによつて若返る。その目覺める時は空の一端から一端を照し、天の門を開く。惡夢を拂ひ惡鬼を追ひ、嫌はれたる夜の黑き幕を去る。暗黑のために隱されたる寶を現はしこれを豐かに惜気なく人に施す。總ての生物を睡眠より目覺めしめて活動に就かしめる。ウシャスは赤色の馬又は牝牛によつて挽かれたる輝く車に乘せられる。輝く車と云ひ赤色の馬又は牝牛と云ふは曉の赤き光線を指して居るであらう。
ラートリー(Ratri)は夜の女神でウシャスの姉であるとされて居る。ウシャスと同じく天の娘である。夜といつても眞暗闇の夜ではなくして燦然たる星光りの夜である。この夜の女神はあらゆる光彩を以て飾られたる暗黑を除くといつてあるが、これは星の光りのために天地の自ら明かなることを形容したものであらう。この神が近よると人も獸も鳥も共に休息をする。この神を崇拜するものは狼盗賊の害を免れ、安全の地に導かれる。この神はその妹なる神と雙神としてウシャサーナクタ(Usasanakta、曙と夜)又はナクトーシャーサー(Naktosasa、夜と曙)と呼ばれることがある。
ジャーヴァープリチヴィー(Dyavaprithivi)は天と地とを現はせる一對の神である。天地間に澄めるらゆる生物の父母として總てを造り總てを扶助する。一は多産的の牡牛で、一は雜色の牝牛である。共に無限の種子を有して決して老ゆることがない。彼等は廣くして大なる生物の住所である。彼等は食物と富とを供し、大なる名譽と主權とを與へる。彼等は生物の父母として彼等を護り彼等の不名譽と災禍とに陷るを防ぐ。
以上は唯數種の例を擧げたに過ぎないのであるが、これ等の例によりても推量し得られる通り、ヴェーダの神話の中の神とは、勿論その總てではないけれども、その中の大部分は自然界の現象殊に特異の現象に神格を付したもので、此處に神神として崇められて居る曙夜天地水火暴風降雨山河等の如きものが自然現象として有する特色は決して見逃されることはなかつた。これ等は常にこれ等の神を造つた詩僧の念頭を去ることはなかつたのであらう。隨つて吾人はこれ等の詩中に描き出されて居る神の屬性を聞いただけでもそれが何れの神の事なるやを容易く想像することが出來る。要するにこれ等詩僧の描き出したる神神の屬性は彼等が生活して居た社會の個人個人の屬性を客觀化したものに外ならない。
佛教はそれ自身の神話を有つて居るといふことが出來る。佛教の教ふる世界組織の中には多くの神の世界があり、その神の名目は吾人を以て婆羅門教の神、ヴェーダの神話中に現はれる神を思はしめるものが多い。實際佛教の神は多くの點に於て婆羅門教ヴェーダの神に似て居る。佛教文學中に見出されるヴェーダの神の主なるものは因陀羅(インドラ、Inda, Indra)梵天(ブラフマー、Brahma, Mahabrahma)生主(プラジャーパティ、Pajapati, Prajapati)婆樓那(バルナ、Varuna)伊舍那(イーシャーナ、Isana)パルジャンナ(Pajjunna, Parjanya)蘇摩(ソーマ、Soma)毘紐奴(ビシュヌ、Venhu, Visnu)及び下級神、阿修羅(アシュラ、Asura)夜叉(ヤクシャ、Yakkha, Yaksa)羅刹(ラークシャサ、Rakkhasa, Raksasa)毘舍闍(ビサーチャ、Pisaca)乾闥婆(ガンダルバ、Gandhabba, Gandharva)天女(アプサラス、Acchara, Apsaras)などである。
此處に一つ注意すべきことは原始佛教文學の中ではこれ等の神神は唯單に純然たる神話的の性質を有つて現はれることなく、一一多少道徳的の性質を有つて現はれるといふことである。即ち彼等は原始佛教の文學の中に現はれる限り道徳又は不道徳の行爲者である。語を換へて言へばヴェーダ文學の中でとは違つて、原始佛教文學の中では彼等は常に多少道徳上の目的から描き出されて居る。彼等の總ての起源がヴェーダに溯り得られるや否やは別として、彼等の神話は常に多少道徳的雰圍気に包まれて居る。彼等の佛教文學に現はれるのは常に或道徳上の必要に迫られてである。彼等は大體道徳上の立場から見られ、稀にその性質は中性又は無性である。即ち道徳的でも不道徳でもない。
第二は佛教文學の中では彼等は彼等がヴェーダ神話の中で有つて居た傳統的の高い地位を奪はれて了つた。彼等は最早崇拜讚仰の目的物ではない。彼等に讚美の辞や祈祷犧牲を奉ぐるものはいない。こは一は佛教は婆羅門教の神秘的宗教的儀式的なるに對して遙に人間的道徳的常識的であるからであり(緒論參照)、二は佛教は吾吾の開悟その他の上に於て吾吾の自力を用ふべきことを教へるからである。佛教の教によれば、吾人の開悟、解脱即ち吾人自身の救濟に對して外部のものは何らの力をも吾吾に借すことは出來ない。神の力も人の力も何らの用をもなさない。吾吾は自己の救濟には徹頭徹尾自己の力を用ひねばならないからである。而して第三には斯うして自己の力によつて佛果羅漢果の如き高き地位を占め得たものは普通謂ふ所の神以上に尊まるべきものであるからである。佛の考によれば佛阿羅漢は勿論のこと、向果の上にある人と雖も神以上に尊まるべきものである。
巴利文『大會經』(マハーサマヤスッタ、Mahasamaya-sutta,漢譯にては長阿含一二卷『大會經』及び『佛説三摩惹經』)には七十以上の神神の名を連ねてある。これ等の神神は佛及び佛弟子たちに敬意を表せんがために來たのである。漢譯の同經には
『復十方の諸神妙天あり、皆來つて集會す、如來及び比丘僧を禮敬せんがために』
といひ、
『今日大衆會し、諸天神普く集まる、皆法のための故に來り、無上衆を禮せんと欲す』
といつてある。同『阿②那智經』(アーターナーティヤ、Atanatiya-sutta)漢譯にては『佛説毘沙門天王經』には亦四十一の神の名を列ね擧げてあるが、此處に集つた四方の神神の中北方倶吠羅神(クベーラ、Kuvera, 毘沙門)は一同を代表して美しい偈を唱へ、佛及び過去に於ける佛の先輩『過去七佛』を讚歎し奉り、出家及び在家の佛弟子たちが森林の中に入つて冥想する場合、佛に對して信仰心を有せざる神が彼等に危害を加へるの虞あれば彼等はこの『阿②那智經』を誦すべきことを勸めた。この二の著しい經文の中にあつてさへ吾人は讚歎の辞や祈祷又は犧牲のこれ等の神神に對して奉げられたのを見ることがない。『阿②那智經』は一種の讚歌であつてこの中には諸佛讚歎の偈が載せてあるが、この中には希求、哀願、要請何れの意味に於ても祈祷といふものはない。唯これを反覆することは惡意を以て佛及び佛弟子に近づき來る神に對する自衛の道と信ぜられて居るだけである。
原始佛教文學中に於ける婆羅門神の地位を説明するには帝釋天(因陀羅)梵天(大梵天)の二大神を取つてこれを佛教の光によつて觀察するのが最良の方法であると信ずる。帝釋天は上にも言つた通り、ヴェーダでは初は雷雨の神であり次には軍の神であつたが、原始佛教の文學の中でも或程度まではこの性質を保留して居る。彼は提婆(デーヴァ、Deva)即ち天の長としてその敵なる阿修羅(アシュラ、Asura)との不斷の戰を指揮する。佛教文學中に於ける彼は一方極めて勇武であるが、一方には道徳的で善良で、ヴェーダ時代に於ける不道徳は勿論、粗暴な気まぐれな性質を有たなくなつた。阿修羅の軍は厚顔無恥にして惡意を有てる神であるが、帝釋天及びその眷屬即ち四天王及び三十三天は概して善良なる神である。帝釋天は前世に於ては七種の美徳(兩親に孝養であつた、家族中の長者を尊敬した、愛語を用ひ、惡口をせず、人へ物を施し、誠實で、慈愛であつた。『雜阿含』四〇の一)の所有者であつた。彼が帝釋天として生れ出たのはこの善業の結果である。彼は佛の説かれた法に對する信仰、善行、學問、施與、智識を讚美する。彼は佛、阿羅漢、有學の聖者に對して敬意を表する。帝釋天に關して最も感激すべき人情的の物語はこれである。
彼一日阿修羅軍と戰はんがため車に乘りて行く途中、綿樹の上に鳥の巣を構へたるを見た。彼は車の轅がその巣を壞たんことを恐れ、その御者馬多里(マータリ、Matali)に命じてこれを避けしめた。彼はこの時その巣を壞たんよりは寧ろ戰に敗れんといつたといふことである。(『長阿含』二一卷世記經、戰鬪品、『雜阿含』四六の一參照)。
帝釋天は斯の如く有徳の神ではあるが、佛及び阿羅漢果を成じた佛弟子には劣るものとしてある。何故なれば彼はまだ貪慾を離れて居らぬからである。帝釋天、生主、婆樓那、伊舍那はまだ貪慾を離れて居らない。それ故に天子等が阿修羅軍と戰うて怖畏を感ずる場合これ等の神神の旗印を見上ぐるともその怖畏より脱れることは出來まい。之に反して比丘等が森林樹下空屋の中にあつて怖畏を感ずる場合三寶を念ずれば彼等はこの怖畏より脱れ得るであらう。これ三寶は貪瞋癡その他の邪惡より逃れて居るからである。帝釋天は生老病死憂悲苦惱失望を免れる事が出來ない(『增阿含』一四の一參照)。これを免れることは佛教的修養の第一義諦で帝釋天はまだこの境地に達することが出來ないで居るのである。これが彼が佛及び佛弟子に劣れりとされた所以である。
ブラフマン即ちブラフマー(Brahma)は本來ヴェーダでは祈祷、聖典、聖語、聖智、僧又は聖典以下のものに内在する力の意であり、後に至つて阿中の第一原理、自存的最上精神の意を有つやうになつた。古代印度人の考によれば祈祷は深き信心の表現としては一種の力である。それによりて人間の意志と神の意志とが結合され、斯くして人は神を動かすことが出來、或は神を強ひて人の希求するものを與へしむることが出來ると信ぜられた。その結果としてヴェーダでは祈祷主(Brahmansapati, Brihaspati)が宇宙の第一原理と信ぜられて居たが、後になつては祈祷そのものが第一原理と信ぜられるやうになつた。斯くの如く本來單なる祈祷であつたブラフマン(Bra'hman)は宇宙の主なるブラフマン(Brahma'n)となつた。語典の上では中性名詞であつたものが男性名詞となつた。佛教がこの神に關する考を取入れたのはこの語が既に男性名詞となれる頃のことであつた。
佛教の宇宙觀では梵天即ち大梵天(Brahma, Mahabrahma)は色界初禪の最高の世界に住めるものである。初禪天の最下位に住めるものを梵衆天といひ、中位に住めるものを梵輔天といふ。これ等は大梵天の從者であり眷屬である。宇宙の第一原理、最高の自存者、絶對精神、これと結合することは婆羅門の最高の成功と思はれたる梵天(第六章、第七章參照)も佛教の中ではこの廣大なる宇宙の一部を支配する一の神と思はれたに過ぎない。ヴェーダ文學の中では祈祷、聖典、聖語、聖智、或は祈祷を奉げ、聖典聖語を知り、聖智を有する僧侶の意とせられ、聖典以下のものに内在する力の意とせられ、後世の婆羅門教にては最上の實在者、宇宙の創造者を指すものとされたが、佛教の宇宙説では色界最下の世界の主たるに過ぎないとされた。帝釋天は四天王及び三十三天の主で欲界の地居天の主であるが大梵天は色界初禪の主である。
大梵天、帝釋天を初め印度古代の神神が原始佛教の中では何故に斯うしてその地位を下げられ、その威力を剥ぎ取られたかというと、そは第一原始佛教は極めて人間的であり、人間本意であるがためと、第二はそが智と行とを本位とせる教であるが爲めである。唯一神にせよ、多神にせよ、神を宗教の主體とし神人合體を理想とせる宗教にあつては神は宗教の本位でなければならぬが、原始佛教の如く解脱の理想は古人の智的行的努力によりて、四諦の理を悟り、八正道を踏み行ふことによりて達せられるべきものと説く教にありては、神は重要視せさるべき謂れなく唯その古來の傳説によりてその存在を繼續するだけである。第二は原始佛教は特に行を重しとする教であるから人も神も共にこの同じ標準によりてその價値を判斷されねばならない。佛は自身刹帝利族に屬せられたから、武族の神帝釋天を重んぜらるべきであると思ふが、ヴェーダの中に於けるこの神の性格は道徳的には稍々劣つて居るから佛はこの神を大梵天以上に重要視するには躊躇されたであらう。大梵天は初禪の首位を占むるに對して帝釋天が唯欲界地居天の首位を占むるに止まるはこの意に基けるものではなからうか。
長阿含一六卷『堅固經』(Kevaddha-sutta)の中に、或神通力ある比丘に關する物語があるが、これは佛教中に於ける梵天の地位を明にするものとして此處に略説すべき必要がある。この比丘一日定中にあつて地水火風の四大の盡きる所を究めたいと思ひ、天上界に昇つて四天王にこれを問ふたが彼等はこれに答へることが出來ず、帝釋天に問へといつた。帝釋天もこれに答へ得なかつたので、比丘は上へ上へと昇つて終に梵天の世界に來た。梵衆梵輔の二天衆も同樣返答が出來ず、愈々大梵天自身に問ふこととなつた。しかし大梵天も四大は果して何處にありて盡きるやを知らずして當惑したが、自分の眷屬たる梵衆梵輔二天の面前で自分の無智を告白するは自分の威嚴を傷くるものであると思ひ、彼は話頭を他の方面へ導き大言壯語することによつてこの窮地より脱れ出でんと企て、比丘に向て
『余は梵天である、大梵天である、無能勝者、統千世界、最得自在、能造萬物、能爲變化、富貴、尊豪、衆生父母である』
といつた。比丘がこれは自分の知らうと思ふことでないといつても大梵天は三たびこれを繰返し、而して後座を下つて比丘の手を取り人なき所に伴れ行き何故に比丘の問に答へずして徒らに大言壯語せしやを語り、その無智を告白し、且つ人間の世界に還つてこれを佛に問ふべきことを忠告した。比丘はもちろん還つてこれを佛に問うた(長阿含『梵動經』參照)。
これは勿論一種の作話に過ぎない、『堅固經』大體の旨意はリス・デビヅによれば、神通の無用なることと世界は人人の心中に存して遠く他界に求むべきものでないといふ意味を含めたものであるといふが、一面には梵天が佛教で如何なる待遇を受けて居るか、語を換へて言へば梵天はその徳に於てもその智に於ても遙に佛に及ばざるものとされて居ることを示すものと見ることが出來よう。涅槃を體得した佛は無限性を得て居るが、梵天は原始佛教ではまだ有限である。一切智者たる佛の智慧は無限であるが、梵天の智慧は有限である。斯うして婆羅門教にては最高の尊貴、婆羅門生活の理想境に居るものとされたる梵天も佛教文學の中ではその世界説中の一隅を占むる一生物、唯他の生物より優れたる性質を有てる一生物に過ぎないものとされて居るのである。
アリヤン人がその印度に於ける第一の定住地たるパンヂャーブ(Panjab)を去つて東南の方に進み、恒河(ガンガー、Ganga)耶尤那河(ヤムナー、Yamna)の豐饒なる流域即ち古代印度の歴史の上にて中部地方と稱する地方に移り、同所に定住するに至るや、彼らの宗教心理はよほど著しい變化を蒙つた。先づ第一に彼等は彼等がパンヂャーブに住んで居た頃のやうに讚美及び祈祷の上に自然の恩寵を感ずることがなくなつた。それかと云つてこの時代のアリヤン人は後世の彼等の子孫のやうに深遠なる哲學を組織して彼等の新らしい郷土に於ける気候の變化、社會の紛糾せる状態より生ずる艱難に對して慰藉を求めるといふほどにも進んでは居らなかつた。その結果としてこの時代の僧侶は煩瑣なる儀式を案出するに熱中したものである。祈祷又は犧牲は神を動かして人間の欲求する如何なる惠をも與へしむることを得といふ考は極端まで持つて行かれたのである。彼等は儀式が微細であればあるほど神を動かす力も強いと信じた。一方からいへばこは又婆羅門族が刹帝利族に對して優勝の地位を要求した結果でもあつた。即ち婆羅門族は微細にして神秘なる儀式を作出しこれを秘密に傳へた。ブラーフマナ(Brahmana)と稱する文學はこれ等の事柄を記せるものである。彼等は公言してこれ等の儀式を知れるもののみ獨り力強く、刹帝利、吠舍その他のものは國王自身と雖も、これ等の儀式の助を借りて初めて強きことを得といつた。而して極端に宗教的なる印度人は彼等の言ふことを容易く信じた。
リグヴェーダ時代に於ける印度人にも儀式の宗教の重要なる一部と看做されて居たことは事實である。しかしそれも決してこのブラーフマナ時代ほどではなかつた。この時代では儀式を微細にし神秘的にして儀式を行ふ人の一言一行はいふに及ばず、この儀式に用ひられる一箇の器物と雖も或種の神秘的なる意味を含んで居ると信ぜられた。之に加へてこの時代の印度人の考によればあらゆる自然現象、あらゆる人生の出來事も宗教上の儀式と或種の關係を有つて居た。物は有生と無生とに拘らず總て儀式と或種の關係を有つて居た。物の存在その事が既に儀式のためであつた。儀式は萬事であつた、一切であつた。斯の如くして出來上つたブラーフマナ文學は、アタルヴァヴェーダと共に西紀前一千年より八百年の間の作物であると信ぜられて居る。アタルヴァヴェーダはヴェーダの一部であるが、實際をいへばブラーフマナの序文と見られるべきものである。
ブラーフマナ中に見らるる婆羅門教の儀式主義と著しき對照を形造れるものは原始佛教の排儀式主義である。吾人が既に述べた通り、儀式尊重はブラーフマナ時代の一大異彩であつて儀式は自然現象より動物竝に人間生活の總てを支配した。神も人も有生物も無生物も祈祷又は犧牲の力によつて自由自在に動かされた。これがブラーフマナが構成された時代の印度人の有つて居た信仰であつた。翻つて佛教は如何と見れば、佛教には讚美歌又は犧牲を以て阿諛すべき神もなく、祈祷によりて希求又は祈願すべき神もない。佛教には神學(Theology)もなければ接神術(Theosophy)もない。神話(Miths, mythology)は或意味に於てはあるともいへようが、その神話及び世界説の中に現はれる神神は恩惠を下したり、害惡を除いたりすることを直接に祈願されることは決してなく、これ等の神は唯佛、佛弟子又は他の神聖にして有徳なる人人の何よりて人に保護を加へ人の危害を除くものと信ぜられて居た。佛教の神は一部は婆羅門教の神を取入れたものであることは確かであるが、これ等の神神はその神話及び世界説の上にその低き地位を保留して居るに過ぎない。神の力は削がれ、儀式の效力は全然認められなくなつて了つた。斯うして佛教は實行道徳主義を高調して現はれ出たのである。
これに關連して吾人はブラーフマナに載せてある犧牲に就いて一言するの必要あることを感ずる。犧牲は古代の印度人間では普通に行はれる儀式の一であつた。人間犧牲のことさへブラーフマナの中には載せてある。アイタレーヤ・ブラーフマナ(Aitareya-Brahmana)(七の一三)にはシュナフシェーパ(S'unahs'epa)といふ一少年の事が説いてある。
彼は國王の一子に代つて犧牲として神に奉げらるべきであつたが、神神が現はれて彼を救つたといはれて居る。
同ブラーフマナ(一の八)には又次のやうなことがいつてある。
神神はその儀性として人間を殺した。しかし人間の中で犧牲に適當なる部分は遁れて馬の中に入つた。それで馬は犧牲に適する動物となつた。神神は馬を殺した。しかし犧牲に適當なる部分は馬を遁れて牛に入つた。神神は牛を殺した。しかし犧牲に適する部分は遁れて羊に入つた。それから山羊に入つた。犧牲に適する部分は一番長く山羊に留まつた。隨つて山羊は犧牲として最も適當なる獸となつた。
シャタパタブラーフマナ(S'atapatha-Brahmana)(一、二、三の六‐七)にも次の如き物語がある。
神神は犧牲として先づ人間を奉げた。しかし人間の犧牲的の部分は人間を遁れて馬の中に入つた。夫故に馬を奉げた。しかし犧牲の精は又遁れて牛に入つた。精は更に遁れて羊に入り山羊に入り、又地に入つた。神神は地を掘つてその精を得んと試みると、それが米と麥の形をなして存することを見出した。夫故に『これを知るもの』(Ya evam veda)に取つては米と麥との奉げものは人間及び動物の奉げものと同じ效力がある。
斯ういふ記事からして馬牛羊山羊の如き動物の犧牲はブラーフマナの時代には極めて普通に行はれて居た事柄であるといふことが判らう。而して勿論普通ではなかつたかも知れぬが、人間の犧牲も全くないことはなかつた。馬と牛との犧牲は中止されたが、羊と山羊との犧牲は今日でも尚ほ行はれて居る所である。神神の心を和ぐるため斯の如き殘忍なる犧牲を行ふことが必要であると考へられて居たのであつた。
佛教に就ていへば佛教はこの種の殘忍事は一も有つて居らない。吾人が繰返していへる通り、佛教は犧牲の手段を用ひて機嫌を取り又は制裁を加ふべき神を有たない。而して人間は勿論の事、他の如何なる動物と雖もその生命を奪ふことは佛教では最も惡むべき罪惡の一と考へられて居る。Yanna(Yajna),Yttha(istha),Yaga,Yaja,Homa,Hutta,Havya,Huta,Bali,Puralasa(Purodasa)などの如き語は佛教聖典中に用ひられて居るが、併し常に特別の意味を與へてある。これ等は何れも單に奉げもの、供へものなどの意に過ぎない。佛教聖典中でこれ等の語のその本來の意義即ち犧牲の意に用ひられるのはそが婆羅門教徒の實行せる犧牲又は神供の意に用ひられる時である。生物の生命を奪ふことはそが如何に微細なる生物たるにせよ、佛教では非佛教的行爲として難ぜられ、一方には又慈愛同情人道主義は稱歎すべき美徳として常に擧げられて居る。斯る殘忍なる犧牲と佛教との兩立しないことは勿論いふまでもない。
印度人は他に比類なき社會制度を有する國民として世界に知られて居るが、そは彼等がその特殊の種族制度を有し、而もそれが太古以來今日に至るまで固く守られて來て居るからである。種族の觀念はリグヴェーダ初期には全然ないものであつた。この時代のアリヤン人は無數の小部族に分れ、各部族はそれぞれ自己の長者を有つて居た。この程度の文明にありては各人共に同時に僧侶であり、武士であり、平民であつて、生れ又は職業に基く社會上の區別は一もなかつたのであるが、時の進むに隨つて社會は益益複雜となり、職業は益益專門的となつて或一部の人民又は家族は或特殊の事業に從事するといふ習慣の時代が到著したのである。宗教上の儀式は上にもいつた通り前よりも複雜となり、何人と雖も幼年時代より特にこれに教育されるでなければ儀式を行ふことが出來なくなつた。夫故に神と人との仲介をなす特權は或家の父より子に世襲的に傳へられた。婆羅門族(ブラーフマナ)は斯の如くして建設されたのである。小なる部族の長は常に他の部族を併呑することに熱中して居た。これには勿論成功したものも成功しないものもあつたが、その成功したもの、即ち都合よく四邊の小部族を併呑したものは統一王(Samraj)と稱せられ、その國土及び人民を保護するの必要よりして彼等は常に軍人を養ひ、調練を加ふるの必要があつた。武士族(クシャトリヤ)は斯うして起つた者である。その他の人民は廣い意味の實業に從事した。即ちマヌの法典(一の九〇)に所謂
『家畜の番をなし、施を行ひ、犧牲を奉げ、ヴェーダを學び、商業を營み、金を貸し、地を耕す』
などの事をやつた。よりて吠舍即ち庶民の一階級が形造られた。これ等の三種族は職業及び階級によりて區別されては居たが、共に同じアリヤン族に屬し、これ等の階級に屬するものは適當の儀式によりて入門式(Upanayana)を行つた後再生者(Dvija)と稱せられた。こは一たび母の胎内より生れて生命を獲、入門式によりて再び新なる生命を獲るからである。こは上に擧げた三階級の人人の生れながらにして有する特權であつたが、これ等の外にこの特權を全然有しない一の種族があつた。それは首陀(スードラ)といふものである。これを一生者(Ekaja)と呼ぶは母の胎内から生れ出るだけで、入門式によりて生ずる再生の特權を全然有つて居らぬからである。首陀は外來のアリヤン人に非る本來印度土著の人民を殘らず含めるもので、彼等はアリヤン人のために征服され奴隷として虐使された、宗教的にも社會的にも永久に呪はれたる人民である。マヌの法典(一の九一)には彼等は唯一の業を有するのみ、そは柔順に上の三族に仕へることであるといつてある。
斯の如き社會的區別が何時初めて出來たかは明瞭でない。唯吾吾はリグヴェーダ(一〇の九〇)に巨人の歌(Purusa-sukta)なるものを見出すが、その中に
『彼(即ち巨人)の口は婆羅門であつた。彼の兩腕は武士、彼の兩股は吠舍であつた、而して彼の兩足から首陀が生れた』(『摩登伽經卷上』)
と斯ういつてあるから、印度に於ける種族の觀念はずつと早い時代に溯ることが出來る、即ち少くもリグヴェーダの遅い時代まで溯つて行くことが出來よう。しかしこの組織の十分なる發達は勿論後日アリヤン人がパンジャーブを去りて中部地方に定住した後即ち印度宗教文學史の上でいへばブラーフマナ時代の事であつた。而して佛教の起つた頃は種族制度はその發達の頂點に達して居て、人の社會的地位及び職業はその生れによつて定められるを常として居た。人はその生れによつて生涯貴族たり平民たり富貴であり貧賤であり賢明であり愚癡であるべき運命を有つて居つた。人はその生れのために束縛され、ただその生れが許す範圍内に於て自由なることを得た。而してこの自由の範圍は極めて狹いものであつて上の三階級に屬するものと、下の一階級に屬するものとの交通は嚴密に又は絶對的に禁ぜられ、この禁制を犯すものは極めて重い社會的制裁を受けねばならなかった。上三族の中でも異れる種族に屬するものの間の婚姻は勿論の事、一所に飮食することさへ堅く禁ぜられ、人若しこれを犯せば彼はその族種を失い、子子孫孫浪人とならねばならなかつた。種族制度は社會的發達及び個人的自由に對しては實に永久的障害であつたのである。
種族制度に對する佛の態度は第一にはあらゆる種族の平等主義四海同胞主義を教へ、第二にはあらゆる人間の關係を道徳の根底の上に置くことであつた。佛は先づ次のやうなことをいはれた、
『比丘等よ、恒河(ガンガー、Ganga)、耶尤那河(ヤムナー、Yamna)、阿夷羅婆提(アチラヴァチー、Aciravati)、薩羅浮(サラブー、Sarabhu)及び摩企(マヒー、Mahi)等の如き大河の水が大海に入る時はその本名を失ひ唯大海のナニりて知らるるが如く、刹帝利(カッチャ)、婆羅門(ブラーフマナ)、吠舍(ヴェッサ)、首陀(スッダ)の四姓に屬する人人もその家を捨て如來の教へたまへる法と律とに於て出家生活に入る時はその本來の姓名を失ひ、唯釋子沙門の隨徒として知らるるに至る』(巴利文『增一阿含』四卷二〇三頁、漢文『增一』三七卷)。
この考は啻に僧伽即ち出家の弟子の間のみならず、在家の弟子の間にも推し及ぼされねばならない。即ち何人たりとも單にその生れによりて特權を得ることは出來ない。佛の教へられた法と律との上では何人も平等でなれけばならない。人類の間に區別を生ずるは生れでなくして行であるといふのが、佛の基本思想であつた。人は行によりて貴人ともなり賤人ともなり婆羅門ともなり旋陀羅(チャンダーラ)ともなる。佛が道徳教の教主、四海同胞主義平等主義の教師として斯の如き教を説かれるのは自然の事である。種族制度は本來アリヤンと非アリヤン人とを區別するため、次には婆羅門族の至高の地位を與へるために設けられたものであるが、佛は全然これを無視して
『生れによりて賤人たるにあらず、生れによりて婆羅門たるにあらず、業によりて賤人となり、業によりて婆羅門となる。』(『諸經要集』三六偈、漢文『雜阿含』四卷、『別譯雜阿含』一三卷)
といはれた。佛のこの態度はその自己の種族たる刹帝利を揚げて從來常に優勝の地位を占め來つた婆羅門族を抑ふるためと見られぬでもない。佛には斯うした意志が全然ないと否定はされぬかも知れぬが、勿論そればかりではない。佛は驕慢不逞の婆羅門を抑壓するがためにこの筆法を用ひられたかも知れぬが、しかし眞の婆羅門は常に讚美の辞を用ひてこれを稱揚された。
佛教の教ふる所と印度の他の宗教の教ふる所と異なれりと思はれる點で今一つ顯著なるものはそれが苦行を排斥する點である。婆羅門教は解脱の道として苦行、供犧、開悟及び信仰の四を教へ、耆那教も亦解脱の道として開悟と苦行とを示した。婆羅門教の教ふる四種の解脱道の中、佛は唯開悟の一のみを取りて他の三を全然無視し、又は極力排斥された。佛はその成道後第一の説法なる『轉法輪經』の中で、その最初の弟子等五人のために苦樂の二邊即ち兩極端を避けて中道に就くべきことを教へられた。即ち一面には俗惡なる享樂主義を排し、一面には苦痛多き苦行主義を排せられたのである。その時佛の用ひられた語は
『比丘等よ、出家者たるものは、これ等二の極端に賴つてはならない。二の極端とは何であるか、それは(一)この諸欲の上に於て享樂に熱中することで、卑しく鄙び、凡夫的非聖者的で、人を不利に導くものと(二)この自身を苦しむることに熱中することで、苦痛多く非聖者的で人を不利に導くものとである』
であつた。斯うして佛は極めて明白に宣言して、苦行主義をば欲樂主義肉慾主義と同じやうに排斥すべきことを教へられ、この苦樂の二邊即ち兩極端を避けて中道に賴るべきことを説かれた。苦樂の二邊を離れた中道とは八正道のことである。
佛がその最初の説法の劈頭に於て斯ういふ宣言をされたに就ては多少の理由がある。佛は出家後間もなく阿羅羅(アーラーラ、Alara)、迦藍(カーラーマ、Kalama)と羅摩(ラーマ)の子鬱頭藍(ウッダカ、Uddaka Ramaputta)とを訪ひ解脱の道を問はれたが、前者は無所有處を以て後者は非想非非想處を以て各各自ら達し得る極度の點と信じて居たので、佛は彼等の教ふる所に滿足し得られず、彼等を捨てて苦行林中に入つて苦行に身を委ねられた。この時この所にあつて世尊と同じく劇しき苦行を行ひ世尊を信じ且つ尊敬して世尊の遠からず悟を開きたまふべきを期待して居たものはこの五人の弟子であつた。世尊はその當時の印度の宗教的風俗に倣うて極度の苦行を行ひ
『日に一麻米を進む、示現して此を服す、入息出でず、還報の息なきことを示す』(『普曜經』卷五)
とか、
『太子正眞道を求めんがための故に、淨心に戒を守り、日に一麻一米を食む、設乞ふ者あれば亦以て之を施す』(『過去現在因果經』卷三)
といつてあるやうなことを行はれた。佛が巴利文『本生物語』九四の中にも
『苦行家としての余は極度の苦行家であつた』
といつて居られる言に徴しても判る通り佛自身も斯ういふ苦行を行はれたのである。
當時印度に行はれて居た苦行の種類は如何いふものであつたか、此處にそれを一瞥するは興味あることであり又重要なることである。今長阿含十六卷『③形梵志經』、『方廣大荘嚴經』七卷、『過去現在因果經』三卷、『普曜經』五卷などによつて當時行はれて居た苦行の重なる種類を列擧して見よう。弊衣粗食樹下石上の如き衣食住の簡素主義は古昔の印度の苦行者に取つては何でもないことであつた。或は水ばかりを飮んだ、或は上にも記した通り、一日一麻一米を取り若し乞ふものがあればそれをも施した。斷食の結果餓死するをも意としなかつた。意としない所ではない、耆那教徒の如きはそれを幸福なりと見た。乞食に出て若し主人喜んで施せば受けるが、少しでも悋むやうな顔をすれば受けない。隨つて一粒の米をも喉に通さずして一日を過すこともあつた。杵臼の音及び狗の吠ゆる聲を聞けば乞食を止める、喚び戻されても受けない。寒を履んで煖に就かず、熱に處して涼を求めず、風雨を避けず蚊虻を逐はず、或は五熱を以て身を炙り、煙を以て鼻を熏じた。灰や塵土を以て身に塗り髪や鬚を引き抜いだ。常に兩手を擧げ、常に立ち常に噂まり常に一足を擧げ、仰いで日月を觀て居た。或は板棘刺灰糞瓦石の上に臥た。或は高い巖から身を投げた。或は自ら身を打擲した。その結果としては(これは佛の苦行に就いていつたのであるが)
『顔貌愁悴、身形萎熟、猶ほその所親を喪ひ、葬送既に畢り、忍を抑へて歸るが如し』(『過去現在因果經』卷三)
又は
『血肉盡く乾枯し、形體極めて贏痩せり』(『方廣大荘嚴經』卷七)
といつてあるやうに、苦行の結果は實に悲慘の極であつた。つまり、斯うして肉身を苦しむれば苦しめるほど人間は靈的となり神聖となり神秘的となると信ぜられた。印度人の如く精神的であり、宗教的であり、神秘を悦ぶ人民に取つて斯ういふ信仰の出で來るのは一向不思議ではない。或は又この肉體に苦痛を與へそれによりて身心を鍛錬することは人間が修行をするに絶好の手段であると信ぜられた。更に又苦行は印度人に取りては一面には解脱の道であり、一面には魔力、超人間的の不可思議力を得るの道と信ぜられた。インド人の考によれば苦行生活をする人はあらゆる人間中最高最尊の人であつた。彼等の眼にはヴァーナブラスタ即ち林棲者又はサンニャーシン即ち遁世者の生活は實に人間の最も理想的な生活の道として映じたであらう。
梵語では苦行の事をタパス(Tapas)といふが、これはtap(熱す)といふ語根から來た名詞で、もとは單に『熱』の意味であつたが、それが『熱誠』、『熱烈』の意となり、更に難行苦行の意を有するやうになつたのである。このタパスは印度人に取つては極めて重要なる異議を有する事柄で、リグヴェーダでは
『タパスによりて原人は創造を初め、タパスによりてリタ(Rita)即ち自然界及び人事界の秩序は保たれ、タパスによりて帝釋天は天界に勝利を制した。タパスによりて人は生天の果報を得る』
などといつてある。リグヴェーダに用ひてあるタパスの意義は難行苦行までは及ばなかつたかも知れぬ、恐くは熱誠熱烈の意であつたらう。ブラーフマナによれば神神は苦行の效によつて神聖なる身となつた。リブ(Ribhu)(半神的生物)は蘇摩の飮料の配分に預つた。神神は犧牲、苦行、懺悔によりて天界を征服した。生主は世界を創造せんがために先づ苦行を行うた。苦行によつて仙人は生れた。この時代になつてはタパスは全く苦行の意と解せられて居たのである。この古い考え及び實行は今日と雖も尚ほ續いて印度人の考へ且つ實行して居る所と云つて宜しい。タパスに對する印度人の信仰は今も昔も變る所はない。
佛はその最初の説法に宣言された通り、苦行主義に對しては全く反對の態度を取られた。さうかといつて享樂主義をも勿論是認されない。自らは非苦非樂の中道主義を取るといはれた。しかしその實行上の教の極めて嚴肅に克己自制的なる點を見れば佛教も今日の吾人の眼には何れかといへば苦行的である。今日の吾人の眼には原始時代の佛教はやはり苦行主義を肯定するものと見えるが、當時の印度人の眼にはよほど放縱なる生活振を教へるものと見えたであらう。これは五人群の比丘が鹿野苑で世尊の遠くから近づいて來られるのを見た時、世尊は先に苦行林で眞摯なる苦行を廃せられ、普通人の生活に還られたから吾吾は敬意を以て迎へることをしまいと約束したといふことによつてもこれを察することが出來る。佛の實行教の今日の吾人の眼に苦行主義を説くものと映ずるだけ、佛も根底から苦行を排斥することはされなかつた。長阿含十六卷『③形梵志經』に③形梵志迦葉が佛は一切諸祭祀法を呵責し、苦行人を罵つて弊穢とされると聞くが、この噂に僞りはありませんかといふ意味の事を問うと、佛はこれに答へて自分は苦行者の中死後或は天の善處に生れ或は地獄に墜つるものあることを知つて居る。それで如何して苦行者を罵ることをしようぞと答へられた。即ち佛は一概に苦行者を排斥された譯ではない。唯婆羅門教の教ふるやうな苦行のための苦行といふ極端なる苦行を排斥されたのである。佛の斯うして苦行を排斥されたのは犧牲や儀式を排斥されたのと同じく第一にその效力を信ぜられなかつたからであり、第二には恐く當時印度の苦行が動もすれば職業的となり、苦行によりて衣食の資を得るものもあつたからであらう。要するに佛は根底から苦行を排斥されたのではなく唯それを極端に持運ぶことを排斥されたのである。
ウパニシャッド(Upanisad)とは古代印度婆羅門教の四種の天啓(Sruti)の第三のものに名けた名稱である。こは獨立せる一種の文學のやうに普通考へられて居るが、その實はブラーフマナの最後の一部を形造れるものに過ぎない。その成立した年代は、古ウパニシャッドに就いていうと、大凡西紀前七百年より五百年の間と考へられて居る。即ち佛教の興起以前百餘年よりその興起の篤時代にまで及ぶのである。ウパニシャッドで取扱つてある問題は主として字宙及び個人の本體に關するもので、前者はこれを最上我(Paramatman)又は大我と呼び後者はこれを命我(Jivatman)又は個人我と呼ぶ。涅槃即ち彼等の所謂梵涅槃(Brahma-nirvana)とは智慧の力によりてこの個人我が最上我と冥合することをいふのである。姉崎博士の『現身佛と法身佛』(七頁)に
『婆羅門教の解脱とは吾と梵とが一致なることを悟得する事、即ち吾が絶對に梵に歸入し合一したるに外ならない。この解脱は智見悟徹によりて得らるべく、斯うして得られた境地を梵涅槃と呼ぶ』
といつてあるはやはりこの事柄を言ひ表はせるものに過ぎない。
吾人が上に既に述べた通り、ブラーフマナは神の機嫌を取り又は神を制裁するの目的を以て行はれた儀式の規則及びそれを行ふに就ての心得を取扱へる文學である。この時代では儀式は恩寵を與へ害惡を除かんことを神に求むるには最も效力ある方法と信ぜられたが時の經過とともに彼等の考へにも一轉化を來した。而してその轉化の理由は大體下の通りである。久しくアリヤン部族間に行はれ來つた戰爭が止んで、彼等は精神上の問題に費やすべき時間を得た。この時代の特徴として見るべきものは刹帝利族出身のものがこの新らしき運動の指導者たるべき地位に立つたといふことである。これと關連してウパニシャッドの末期に起れる佛教及び耆那致の開祖はともに刹帝利族に屬するものであつたといふ事實をも併せ考ふべきである。この時代以前即ち、ヴェーダ及びブラーフマナの時代は婆羅門族ばアリヤン社會全體に對して絶對の權威を有つて居たが、ウパニシャッドの時代になると彼等の權威は制限せられ、國民の生活は世俗的となり、僧侶は温和になり普通人民は以前よりも重大視せられるに至つた。一言にしていへば婆羅門族の勢力衰え他の種族のものが勢を得るやうになつた。戰爭の止んだ結果として刹帝利族のものは精神的の事柄、特に哲學上の問題の研究に從事するやうになつた。而してウパニシャッドはこの時期に於けるアリヤン人の精神的發達の産物である。
印度の歴史を通じて智慧は常に重要なる地位を占めたものである。印度思想のこの特色は早くヴェーダ文學中に認められた。世界の起原、質料(Substance)、その構成の過程、その他これ等と類似の問題は同文學中所所に言及されて居る所である。ブラーフマナは主として儀式を取扱へるものであるが、これ等及び他の哲學上の問題もこの中には多少討議されて居る。ブラフマンば宇宙の第一原因であり、アートマンは個人的精神であること、兩者の間の冥合、輪廻、解脱の教など總て或程度まではブラーフマナの中にも論じてある。しかしこれ等の問題の詳しき説明、及びその哲學的討議はウパニシャッドに至つて初めてこれを見ることが出來る。ウパニシャッドに入つて初めて印度人はこれ等の問題の眞面目なる研究に著手した。吾人は、此處にウパニシャッドが如何にこれ等の特殊の問題を取扱ふやを詳しく論じようとするのではない、唯この時代の印度人に取つては智慧は最も重要なるものであつたといふことを記すれば足りるのである。
ヴェーダ及びブラーフマナ時代では自然を神として崇拜し、儀式を行うてこれ等の神の媚を求めたものであつたが、ウパニシャッドになると人間そのものが自然界のあらゆる勢力よりも更に重要なるものとなり、人間そのものは自然の説明者であり、同時に説明であるとされるに至つた。即ち吾人が宇宙に内在する神をば直接に看取し得るは吾人の心中であるとされた。即ち從來神や儀式や唯外界にのみ向つて居た印度人の宗數的思想は人間の心中にその方向を轉じて來たのである。この時代の印度人は只外形的の儀式によりて彼等が宗教によりて得んと期待して居た心の滿足を得ることが出來なかつた。それ故に彼等は人間を中心とせる哲學上の思辯の上に心の滿足を見出さんと試みた。彼等は智慧をこの目的を達する上の最上の方便と考へ、人間生存の最高理想たる梵との合一も、智慧の力によりのみ果し得らるべきものとした。斯の如く知る人(Ya evam veda)には何事も果し又は達し得られないものはない。何物も彼を害することは出來ず、何人も彼と競ふことは出來ない。智慧は婆羅門に取りてはて最高の所有物であり、この智慧を所有する人は最高の價値ある人である。
道徳的見地から見て吾吾はこの思想の中に三箇の著しき意義あることを發見するのである。先づ第一に智慧は絶對的の價値を有し、あらゆるものに對して效力を有つて居る。斯の如く知る人はその罪惡から免除される。火の木を燒くが如く斯の如く知る人總てその罪惡を燒き盡して清淨潔白となり腐朽と死滅とを免かれる(ブリハド、五の一四の八)。黄金を盗むこと、酒を飮むこと、師の妻を犯すこと、而して婆羅門を殺すことと、この四は婆羅門の四大罪惡であるが、五神火の秘法を知れるものはこれ羅罪惡のために汚されることなく、清淨潔白となり、清淨なる世界の所有者となる(チャーンドーギャ、五の一〇の九‐一○、『摩登伽經』卷上)。伊師迦(イシーカー)と名くる葦の柔かなる纖維の火中に投ぜらるれば燒き盡されるが如くアグニホートラの意義を知りてこの供犧を行ふものはその罪惡總て燒き盡さる(同、五の二四の三)といつてある。斯くしてウパニシャッド時代の婆羅門に取つては先づ第一に智慧は道徳に優つて居た。斯の如く知る人に取つては罪惡といふものはなかつた。智慧は彼等が犯す所の罪惡を總て消盡した。智慧の前には道徳は全くその權威を失つて了つた。しかし時の經過とともにこの考へは少し變じて善行は智慧と同樣に價値あるものと認められるに至つた。カタウパニシャッド(三の六‐八)に
『理解力を有し、その心常に堅く持せられ、その感官は御者のよき馬の如く制せられたるもの……理解力を有し注意深くして常に清きものは實に到りて再び生るることなき所に至る』
といひ、同ウパニシャッド(二の二四)に
『先づその邪惡より脱れざるもの。禪定なく攝制なきもの、心安息せざるものは智慧を以てしても我を得る(アートマン)こと能はず』
といつてある。斯の如くして以前にあつた、『斯の如く知る人』はあらゆる罪過より除外されるといふ思想は少しく修正を加へられ、善行は智慧と同樣に必要なるものと認められるやうになつた。この二種の殆ど相反對せる思想と相對して第三の變化が起つた。それは智慧ある人は善業又は惡業の差別的思想に累せられないといふことである。斯の如き人は「何故に余は善をなさざりしや、何故に余は惡をなししや』等の思に累せられしことなし。斯の如く知る人はこれ等の思想より己を救ふ(タイチリーヤ、二の九)といつてある。智慧の人即ち斯の如く知る人は高く善又は惡の道徳的差別なき天地に飛翔し、差別的觀念に全然打ち克つて了つて居るのである。
佛教の智を重んずることは素より論を俟たない。佛教はウパニシャッドと同じく智慧を重んずる。姉崎博士が『現身佛と法身佛』(七頁)の中に
『佛教では梵なる實體の觀念、吾なる個人の本體の觀念をも排斥したけれどもその知力主義、觀念主義なる點に於ては婆羅門教の教ふる所と變ることはなかつた』
といはれるのは至言である。煩惱の斷絶、悟又は涅槃を成ずること、輪廻よりの解脱、四諦の了解、八正道の實踐など總て根本的に智慧の力によるものである。夫故に智慧は佛教には缺くべからざるものであり、之に反して、無智は最も卑むべき害惡の一である。佛はいはれた
『比丘等よ。汝と我と斯の如く久しく馳走し輪廻の疲れ多き道を轉轉流浪ぜざるを得ざりしは四諦の理を了解し會得し得ざりしためなり』(巴利『增一』二卷一頁、漢譯『增一』一七卷、法顯譯『大般温涅槃經』卷上)。『智なければ定なく、定なければ智なし、智と定とを有するもの彼は涅槃に近づけるなり』(『法句』三七二)。『邪惡の何處より起るやを知るものはよくこれを除く。斯くて彼等はこの渡り難くして渡られしことなき暴流を渡る。再び生を受けざらんがために』(『諸經要集』二七三)。
智は三學の一であり、智の反對なる無明は三毒即ち三種の根本害惡の一である。智は四力(Bala)五根(Indriya)四法(Dhamma)四分(Anga)の一である。念(Sati)覺(Sampajanna)擇法(Dhamma-Vicaya)七菩提分法(Bojjhanga)正見(Samma-ditthi)正念(Samma-sati)正憶念(Yoniso manasi-Kara)は智の中に含められる事が出來よう。佛の名號を一瞥しても如何に智慧の佛教に重んぜられるやを知ることが出來る。
佛陀、三佛陀、三藐三佛陀
十力(Dasabala)
師(Sattha)
一切智者(Sabbannu)
有眼者(Cakkhuma)
普眼者(Samanta-cakkhu)
善逝(Sugata)
大智者(Bhuripanna)
如來(Tathagata)
世間解(Lokavidu)
これ等は佛教文學中最も普通に現はれる佛の稱號の少數に過ぎぬが、此處にこれ等の稱號の中に、佛教の智慧を重んずる意味が十分に現はれて居るを見ることが出來ると思ふ。即ち佛教は智慧を重んずることウパニシャッドに劣ることはないのである。これで又一はこれ等兩者が同一時代に屬することを悟ることが出來よう。實際智慧を重んずることは當時一般の習であつた。
ウパニシャッドと原始佛教とはこの點までは竝進するが、此處に至つて兩者は各各異なれる方向を取るやうになる。それはウパニシャッドは智を重んずること道徳以上なるに反し、佛教は決してさう遠く進むことはなかつたからである。原始佛教では智は常に道徳のために制裁され、若しくは智と徳とは常に竝行する。これが原始佛教がウパニシャッドや大乘佛教のやうに哲學的方面に於て大なる成功を擧げることが出來なかつた理由の一である。要するに智と徳とは竝行するか、又は徳は光、智は後であるかである。佛教では智と徳とを同一視して智者は必ず徳者なりといふが如きことは決してない。唯兩者の間に密接の關係ありと見たることは確かである。例へば
『淨戒と正見とを具し、自ら己の業をなすもの、世は斯の如き人を愛す』(『法句』二一七)、『老後に至るまで戒を持つは樂、正信を樹つるは樂、智慧を得るは樂しく、惡を作さざるは樂し』(同三三三)
といつてある。戒ある人、賢き人、即ち徳者と智者とは全く同一視されないまでも兩者は極めて密接の關係ありと見られて居ることはこれで明白である。一方に於ては戒は三學の首位に居ることより察して佛教の修養は道徳に初まるといふことを知ることが出來る。佛教の高き修養に志あるものは第一に道徳の人でなければならない。
『徳の上に立ちて智者は心の集中と智慧とを養ふ。熱烈にして勤勉なる比丘はその纏結を解かん』(巴利『雜阿』一卷の一三頁及一六五頁、漢譯『雜阿』二三卷、『別譯雜阿』九卷)。『常に徳と智を所有し、よく平静に達して熱烈に專心なるものは渡ること難き暴流を渡る』(巴利『雜阿』一卷五三頁)。
斯の如く佛の智を重んぜられたことは事實であるが、而もこれを徳以上に置かれたことはなく、尚又た徳と智とを同一視されたこともなかつた。
しかしこの智の上に於て原始佛教はウパニシャッドと一致する一の點を有つて居る。それは吾人が上の三箇の著しい點といつた中の最後の點である。但しこの點に於ても吾吾は佛教とウパニシャッドとの間に尚ほ多少の距離あることを認めざるを得ないのである。こは既に上にいつた通りウパニシャッドは常に智慧に最上の地位を與へ佛教は常に徳を以てこれを牽制せんとして居るにも因るであらう。『斯の如く知れる人』は智慧の力によりて道徳上の差別的觀念を遁れ得とされて居る。彼は余は何故に善をなさざりしや、余は何故に惡をなししやといふが如き考へを以て己を惱ますことなし、善惡の二を知るものは自由なり(タイチリーヤ、二の九)。或理由のために惡をなしたといひ、或理由のために善をなしたといふ。斯の如き二種の思は彼に克つことがない。彼は兩者に打ち克つて居る。而して彼が作したことも作さなかつたこともともに彼を惱ますことがない(ブリハド、四の四の二二)。斯くて全能的のウパニシャッドの智慧は智者を倫理的差別の範圍外に超脱せしめる。一方に於て原始佛教は倫理道徳的の宗教として道徳的差別を全然超脱するが如きことは決して期待されることが出來ない。而も吾吾はウパニシャッドのと殆ど同じ思想の聖典中所所に述べられて居るのを見出すのである。これは或は當時一般的思想の影響と見るべきものであるかも知れない。眞の意味の比丘、婆羅門、又は佛は善惡、罪福、喜不喜、淨不淨その他の差別的觀念を離れて居る。例へば
『罪業福業共に捨てて清淨行の人たり、智慧を以つて世界を渡るもの、彼ぞ比丘と稱せらる』(『法句』二六七)、『此處に福業も罪業も共に脱れて著を伏し憂なく染なく清淨なるもの、この人を吾は婆羅門と呼ぶ』(同四一二)、『智者は一切處に依賴することなく、喜も不喜もなすことなし、憂悲慳貪の彼を汚すことなき、葉上の水の汚すことなきが如し』(『諸經要集』八一一、『義足經』卷上)。
斯の如く佛教にては比丘、婆羅門、佛陀はウパニシャッドの『斯の如く知れる人』の代りとなる。彼等は善惡、罪福、喜不喜、淨不淨の差別的觀念の上に超然たるものと考へられて居る。而して斯の如き境界は完全なる道徳意識の活動によりて達し得られたる精神的修養の結果であることは論を待たない。吾吾がこの程度の修養を得る時は差別的觀念の絶對的に絶滅し得られること、ウパニシャッドの『斯の如く知れる人』の場合と異る所はない。
ホプキンス博士はいつた
『婆羅門教に取つて智慧は幸福の道であり、耆那教徒に取つては苦行は幸福の道であり、佛教徒に取つて清淨と愛とは幸福の道である。』
佛教は智慧を重んじ、苦行も或程度までは、これを是認しないことはない。しかし佛教は智慧は重んずることはウパニシャッドには及ばず、苦行を是認するといつてもそれは耆那教や婆羅門教には及ばない。佛教は何物よりも清淨及び愛即ち廣き意味の道徳を貴ぶ。要するに佛教は倫理的異彩を有てる宗教である。
日本現在の佛教各宗の中で、佛教本來の教の外、所謂外來の分子を何程か含まないものは全くないといつてよからうと思ふ。例へば眞言密教の如き、その行ふ所の儀式即ち秘法の類を見ても、その崇拜する神神即ち同教で明王部又は天部と稱するものを見ても、そは婆羅門教に近い關係のあることは否定し得べからざる事實である。即ち眞言密教は婆羅門教の極度に儀式特に供犧を重んじ儀式の效力を信じた時代、婆羅門聖典文學史の上でいへばブラーフマナ時代、又は少し溯つたアタルヴァヴェーダ時代の婆羅門教より大なる影響を蒙つたものであらう。眞言密教の印度に起つたのは勿論ずつと後の事である。西紀後二世紀か三世紀か、それとも六七世紀か、兎に角大分後の事であるが、それが含んで居る佛教以外の分子は斯うして一千年も昔既に印度に存在して居たのである。それを取り入れて作つた佛教が眞言密教である。佛は婆羅門教に背いて佛教を起されたのであつたが、後世の佛教は却つてこれに化せられて了つた。而してその最も著しい例の一はこの眞言密教である。
淨土教にしてもこれと同樣で、阿彌陀佛に關する教の全部の起源を單に佛教のみに求めるといふことは到底不可能である。或は印度にある總ての教を探索しても阿彌陀佛の如き佛(又は神)は發見されなからうと思ふ。それで自然に阿彌陀佛の起源はこれを印度以外の何處かに求めねばならぬことになる。佛國の東洋學界の泰斗たるシルヴァンレヴィー氏は
『阿彌陀佛の觀念、信仰、名稱は古代の婆羅門教にも、又古代の佛教にも全然無關係なもので、印度自身が説明し得ざるものである。而してこれ等の觀念乃至名稱はゾロアスター教のイランには極めてありふれたものである』(『龍谷大學論叢』二五〇號九頁)
といつて居る。この事に就いてはサー・チャールス・エリオッド氏も殆どこれと同じやうなことを云つて居る。氏はその大著述なる『印度教及び佛教』の中に、佛教とゾロアスター教との接觸竝に阿彌陀佛の創造に就いて可なり詳しく考證して居る(同書三卷、二〇二頁、二〇九頁、二一六‐二二〇頁)が、中に
『西部支那及び中央アジアでは佛教、道教、摩尼教、景教及びゾロアスター教が互に教理を借り取つたことは今尚ほ支那でやつて居ると同じであつたらう。而して佛教はこの接觸によつて變化した』(同卷二一七頁)
と云ひ、
『阿彌陀佛の根本の特點は光明の極樂世界であつて、そは慈悲の世界のものであること、而しその名號を唱ふる善人はその所に導かれることである。この二種の特點はゾロアスター教の文獻中にも出て居る、最高の天(善思善語善業の極樂の後に來る所の)は無量光又は無邊光と名けられる。この處もその主なるアフラ・マヅダも共に常に光明及び光榮を含める語を以て述べてある。こは又ちやうど阿彌陀の極樂世界が音樂と樂しい音に鳴り響いて居るやうに、歌の世界である。祈祷によつて此處に生れることが出來るし、アフラ・マヅダと大天使とが迎へに來て信仰篤い人へその道を示してやる』(同卷二二〇頁)
と云つて居る。氏の説は前に引いたシルヴァン・レヴィー氏の説と同じく阿彌陀佛はゾロアスター教から來た佛、ゾロアスター教の善神光明神アフラ・マヅダが正しくその正體で、同教のこの神には阿彌陀佛に關する傳説と殆んど同じ傳説が附隨して居るといふのである。『增一』や『雜』の如き阿含經には佛法僧の三念、佛法僧天戒施の六念、これに休息、安般、身、死の四を加へた十念といふものがあるが、念佛はこの三者の何れにも加つて居るし、而もこの三念六念十念の功徳によつて未來天上界に生れることも説いてあるから一見すると阿彌陀佛を念じ未來極樂に往生するといふ信仰もここに萌して居るかとも思へるが、しかし同じ念佛は念佛でもそれとこれとは大に違ふし、第一阿彌陀佛の名や極樂世界(スカーヴァチー)の名稱の天の如きも佛教の世界説中には見えない。更に又極樂淨土を西方十萬憶土にありと説く所を見、阿彌陀佛が印度の古い藝術に現れて居ない所を見、而して又淨土教の經典を初めて譯した人は總て西域即ち今日の中央アジアの人であつた點などを見てもシルヴァン・レヴィーやサー・チャールスの阿彌陀佛の起源を印度と見ずして波斯と見るの必ずしも根據なき談でないことが察せられよう。
以上は單に眞言密教と淨土教についていつたのであるが、これ等以外の宗派についても同じことがいはれようかと思ふ。要するに何れの宗派にせよ、多かれ少かれ、佛教としては皆不純な分子を含まないものはないといふことになるのである。
然らば我が禪宗は如何であらうか。禪宗が印度、中央アジア、支那、日本の各國に傳はり流布して居る間に、その教の中に、佛教外の原素を取り入れた事實はなからうかといふと、私は大にあらうと思ふ。禪宗が支那で老荘の學派と接觸してその所謂虚静恬淡無爲無欲の教味を多分に攝取したことは何人も否定せざる所である。しかしこればかりではなく、既に印度に於て禪宗は佛教外の教理、所謂外道の説を取り入れた事實がありはしまいかといふに私はこれも大にあつたことと信ずる。こは勿論獨り禪宗ばかりではない、大乘教は皆さうであつたらう。例へば大乘佛教の教とウパニシャッド及びヴェーダーンタの教とを比較して見ると、前者の眞如法性と後者の梵との間には極めて著しい類點がある。而してこの類點たるや決して偶然に出來た類點ではない。眞如法性の教は原始佛教が發達して大乘佛教となる間にその教義の發達の自然の結果として出て來たものではなく、ブラーフマナ、ウパニシャッド、ヴェーダーンタと印度思想の本系中にあつた梵の教義が何時とはなしに佛教の中に取り入れられたのである。兩者の間に著しい類點のあるのは決して偶然ではない。
ブラーフマン即ち梵といふ語はリグヴェーダでは聖歌、祈祷、聖典、聖智等の意義を有つて居たが、それと同時にこの聖歌乃至聖智に内在する力の意義をも有つて居た。梵が後に至つて自存者(Svayambhu)即ち世界の第一原因となつたのはこの後の意義あるによるのである。ウパニシャッドの中では世界の起源の説明は初めには極めて物質的であつた。即ち世界の起源は或は水、或は空、或は非有、或は有、或は不滅と種種のものに歸せられたが、それがやがて梵といふものに統一されて了つた。勿論梵なる世界の第一原因が出てからも他の名も用ひられたが、これ等は多くの場合に於て梵の屬性の一部を見たり、梵の一方面のみを見たり、或は凡を有形又は無形のものに即して見たりするより生ずる概念の相違に過ぎなかつた。梵は雰圍の空であり、生気であり、樂であり、虚空であり(チャーンドーギャ四の一〇の五)、日月電空風火水その他のものであり(ブリハド二の一)、食気意識又は歡喜である(タイチリーヤ三)とされたこともあるが、梵の一概念は總てこれを統括し包含し盡した。即ち梵は一方に於ては世界を創造し世界の事物を産み出し又は自己を分解してこれ等のものを作り出したものであるが、又一方に於ては一切に貫通し一切に即して遍在する實在體である。語を換へて言へば梵と宇宙間の事物とは一即一切、一切即一であり、有形無形悉く梵に歸入し皆梵と同一體といふことになるのである(タイチリーヤ二の六)。僧肇法師の語として知らるる『天地同根、萬物一體』の語も要するにこの意義を表はせるものに外ならない。天地萬物悉皆即梵であり、皆梵に歸入するが故に同根であり一體であるのである。然らばその梵とは如何なるものであるか、梵の定義は如何といふことになると、そは到底與へ得らるべきものではない。梵の本體は不可知、不可説、不可得、不可解である。梵は言詮不及意路不到の當體で、肯定的の語を用ひては到底これを形容することは出來ない、唯『あらず、あらず(ネーチ、ネーチ)』といつて示すより外にこれを示すべき道がない(ブリハド三の九の二六以下諸所)。
これを『起信論』に
『是の故に一切法、從本已來言説の相を離れ、名字の相を離れ、心縁の相を離れ、畢竟平等にして變異あるなし、破壞すべからず、唯是一心、故に眞如と名く』
といへる文、及び『傳心法要』に
『此の心無始以來、曾て生ぜず、曾て滅せず、青ならず、黄ならず、形なく相なく、有無に屬せず、新舊を計らず、長に非ず短に非ず、大に非ず小に非ず、一切の限量、名言、蹤跡、對待を超過し、當體全是』
といつてある文と併せ見ると、實大乘の眞如なるものは畢竟婆羅門教の梵と異なるものてないことが理解されようかと思ふ。唯その異なる所は梵は造化者であるが、眞如はこの性能を有つて居らぬといふだけである。梵に有形無形、死不死、往行、此有彼有(ブリハド二の三の六)と斯うした二種の方面あるは眞如に不變眞如と隨縁眞如とあると同じであらう。即ち眞如は一方には『凝然不作諸法』であるが、一方から見れば『眞如不守自性、隨縁成就一切法』である。斯うして一見全然矛盾した屬性及び作用が一の梵又は眞如にこれありとされて居る。これは普通眞如縁起又は諸法實相と稱せられるもので、實大乘に通じて教へらるる教である。我が禪宗でもこの意味を説明する語は勿論澤山ある。『禪戒鈔』に
『山モ法性ナリ、河モ眞如ナリ、一草モ佛身ナリ、牆壁瓦礫モ佛心ナリ』
と云ひ、『辯道話』に
『是時十方法界の土地草木牆壁瓦礫皆佛事を作す』
前者は眞如の本體を現象に即して示し、後者は現象に即して眞如の作用を示せるものであらう。
華嚴教の法界觀では單に眞如と諸法との相即ばかりではない、諸法相互間の相入、即ち諸法と諸法と相關相入することをも説く。語を換へて言へば單に理事無礙を説くばかりでなくしてなく事事無礙をも説く、正法眼藏の『諸法實相』の卷に
『ここを以て實相の諸法に相見すといふは春は華に入り、人は春にあふ、月は月をてらし、人はおのれにあふ、あるひは人の水をみる、おなじくこれ相見底の道理なり』
といつてあるはこの事事無礙の意を述べたものではなからうか。佛教の眞如と諸法即ち實在と現象との關係を説く教は此處に至つてウパニシャッドの梵と萬有との思想よりも一歩先じて居ることになるかと思ふ。斯うして大乘佛教の實相と諸法とに關する教は既に婆羅門教の梵と萬有とに關する教の中に存在した。而してそは遠くリグヴェーダやブラーフマナにも溯ることが出來るが、それが熟したのはウパニシャッドであり、更に大成したのはヴェーダーンタである。この思想の佛教に取り入れられたのはそれがまだ萬有を幻(マーヤー)即ち非實在とし、梵の本體のみを眞個の實在なりとするヴェーダーンタにならない前の事であつたかと考へる。大乘佛教‐禪も勿論その一部として‐も既に印度に於て原始佛教外の説を取り入れた事實が斯うして歴然と認められるのである。
吾人は上に大乘佛教の眞如法性と婆羅門教の梵との間には非常なる類點のあることを説いた。而して又この類點たるや決して偶然に出來た暗合ではないことをも述べた。大乘で説くこの眞如法性といふやうなものは原始佛教には説かれて居ない。誰でも知つて居る通り原始佛教はその根本教條の一として『諸法は無我である』と教へた。諸行無常及び一切苦の教とともに、諸法無我の教を説いた。この三は普通『三特相(チラツカナ)』として知られ、原始佛教の根本教條となれるもので、佛教の一大特色を形造るものであり、佛教の他の印度の諸宗教との相違は此處から出發して來るといふも過言ではない。諸法無我は斯うして原始佛教の教理の根底を形造るものである。
この所謂我‐原始佛教で『無我』といつて常に否定の語を以て言ひ表してある‐なるものは一體何であるか。婆羅門教の教ふる個人我即ち命我(デーヴァートマン)であるか、宇宙我即ち最上我(パラマートマン)であるか、小我か大我か、これは判然とは判らないのである。併大體から察すると、これは宇宙我ではなくして個人我であらうかと思はれる。それで宇宙我は原始佛教には全く説かれて居ない。唯個人我だけはそれに言及してあるが、それも常に唯否定的の語を用ひて『無我』と言つてあるだけだから、その我が一體如何いふものであるか、判然と推量し得べき道がないのである。佛の意によれば我は本來ないものである、そのないものの説明はしようとしても出來よう筈がないといふのであらう、幽靈は居らぬと信じて居る人に幽靈の説明を求めてもそれは出來ないと同樣である。釋尊の我に對する態度はこの幽靈を信じない人の幽靈に對する態度に同じであつたらう。要するにないと信じて居るものを説明することは不可能であり又無用である。
一體佛はこの我に關する話や死後の生活に關する話をすることを自らも努めて避け、弟子たちをもこの種の話に導き入れることを避けられたことは勿論、假令さういふ話を前方で持ち出してもこれを遮り、これに耽つたり深入りしたりすることを無用の閑事として警告された。
『世界の永劫不永劫、邊無邊、衆生死後の存在有無如何等の如き問題は永久結果を見ることのない、而して又人間の生活には要のない戲論として顧みられなかつた』
と赤沼氏がいつたが、この數言は釋尊の気持ちを十分言ひ盡くして居るかと思ふ。
これに就ては無數に例が擧げられるが、その中で面白いのは『雜阿含』三三卷二二經(『別譯雜阿』一〇卷六經、巴利『雜阿含』四卷四〇〇頁)に出て居る佛と普行沙門婆蹉(ヴァッチャ)との間の問答である。この普行沙門一日佛の所へ參つて佛に向ひ『我といふものはありますか』と問うた。これに對して佛は沈默したまま何とも答られなかつた。次に彼が『我といふものはありませんか』と問うと佛は同じやうに默つて居られた。普行沙門は再び同じことを繰返して問うたが、佛はやはり何とも答られなかつたので、彼は座を起つて去つて了つた。後で阿難陀は何故にあの普行沙門の二回の問に答へずして默して居られしやを佛に問うたすると、佛は『若し私が我といふものがありますかと問はれて、あると言つて答へたならば、それがため私は常住を談ずる沙門婆羅門に同じいことにならうし、一切法は無我と説く智慧の向上に副はぬであらう。若し又私が我といふものはありませんかと問はれて、ないと答へたならばこれは斷滅を談ずる沙門婆羅門と同じいと云ふことにならうし、且又我があると信じて居るこの愚なる普行沙門をば無我と説くためにますます愚に陷れることにならう』といはれた。つまりこの場合の佛の『我はあり』と答へられない理由は勿論明白であるが、『我はなし』とも答へられない理由は、これがため問者をますます迷妄に陷れる虞があるからだといふのである。實行を重んずる佛の眼から見れば我の有無、世界の常無常、有限無限、死後生命の有無の議論など、全く無益の遊戲であり、無用の戲論である。佛は斯ういふ哲學的議論の如き、議論のための議論の如きは極力これを排斥されたが、その中にはこの有我無我の論を含まれて居て、佛は遂ひに我の正體を明かにされなかつたのである。
我とは一體如何いふものであらうか。これに就て故リス・デビヅ教授はウパニシャッドの我を解して
『我は小い生物で、形は人間に似て居り、平常は心臟中に住んで居る。睡眠又は入定中は身體を脱け出るが、眼を覺まし又は定を出ると、還つて來て生命と活動を續ける。死後は身體を脱け出て獨り永久の生命を續ける』(『佛教印度』二五一‐二五五)
といつて居る。勿論斯ういふ物質的な、生気的なものではないが、禪宗の教にもこの我に似たものがありはしないであろうか。
臨濟禪師は
『赤肉團上有一無位眞人、常從汝等諸人面門出入』
といつた。或僧が大隨に問うて
『劫火洞然大千倶壞、未審這箇壞不壞』
といつた時、大隨はこれに答へて
『壞』
といつた。この無位眞人とか這箇とかいふのは一體何を指して居るであらうか。必ずや或一物を指して居るであらう。
『人人屋裏主人公』とか、『自己本來面目』とか、『呼應底是何物』とか、『秘在形山那一寶』とか、人人具足の那一物とか、心性、佛心、佛性、法身、法體といふものもこの同じ或一物を指し、若くは又この同じ或一物とは何ぞやといへば無我を教へる佛教だけでは如何してもこれを説明することはできない。
『癡人喚作本來人』と長沙の景岑禪師はいつた。この或一物を喚んで本來人となすは癡人の沙汰であるかも知れない。無我の我を計すると同じく、實際ないものをあるやうに思うて居るのであらう、斯ういふことを申したらば高祖大師には
『瓦礫をにぎりて金寶とおもはんよりもなほ愚かなり』
といつてお叱りをうけることであらう。それも十分承知して居る。『辯道話』の中にいつてあるやうに
『わが身うちに一の靈知あり、かの知すなはち縁にあふところに、よく好惡をわきまへ、是非をわきまふ、痛痒を知り苦樂を知る、みなかの靈知のちからなり、しかあるにかの靈性はこの身の滅するとき、もぬけてかしこにうまるる、ゆゑにここに滅すと見ゆれどもかしこの生あれば、ながく滅せずして常住なりといふなり』
とまで信じないことは勿論であるが、吾吾は禪家の人が常に無位の眞人とか屋裏の主人公とか、那一寶とか、その他種種樣樣の語を用ひ表はさうと努めていることを注意せざるを得ない。前にもいつた通りそれはウパニシャッドなどに説いてある生気的の我では勿論ない。又靈知と呼ばれるものでも勿論あるまい。然らば何であるか、無いものを便宜のためにあるやうにいつたまでで、語では何物か物を指したやうにいつてあるが、實際はないものである。と斯ういへるかも知れぬが、此處に無我といつた場合の我や、諸法空といつた場合の諸法とは違つて、吾吾の中にある所の或何物かが認められて居ると私は信ずる。一方には無我と教へる、隨つて大我は勿論のこと、小我をも談ずるわけには行かない。しかし無我と一蹴りに蹴飛ばしただけではやはり飽き足らぬ所がある。それでこの何物を表はせりとも判らぬやうな語‐語の上では判然と物を表はして居るが、これを解釋するには判然と物を指すことを避ける‐を用ひたのかと思はれる。私はこれを吾吾の小我‐生気的な我若しくは靈知的な心ではないであらう‐と見る時、初めて吾吾は無位の眞人や屋裏の主人公や形山に秘在する那一寶に就ての苦しい解釋より免れることが出來ると信ずる。
つまに他の大乘教も同樣であるが、禪宗はこの點に於てウパニシャッドの教を取り入れ更にその正統を受けたヴェーダーンタと共鳴する點が多いのである。『寶鏡三昧』の『渠正に是れ汝』の語は一面からは主觀と客觀と、兩者の相回互せる事實を述べたものとも見られようが、他の一面からはこの所謂『渠』及び『汝』なるものはチャーンドーギャ、ウパニシャッド(六の八の七)の中に
『それは汝である、汝はそれである』
といへる有名な語と同じく、兩者の回互し、兩者の同一體たることを示す前に、兩者にはその本體たり中心たるもの、即ち我とも名くべきものの存在することを穩穩裏に示せるものではなからうか。更に又同ウパニシャッド(一四の三)に
『これ即ち心臟の内部に存す。わが我なり。實に穀粒よりも麥粒よりも芥子粒より黍粒よりも、或は黍粒の核子よりも一層微なるもの、これ即ち心臟の内部に存するわが我なり。更に地よりも大に、空よりも大に、天よりも大に、これ等の世界よりも大にして』
といへるは『少室六門』に
『心心心尋ぬべきこと難し、寬なる時は法界に遍く、窄きや鍼をも容れず』
と云ひ『寶鏡三昧』に
『細には無間に入り、大には方所を絶す』
と云ひ、榮西禪師の『興禪護國論』に
『大なる哉心や、天の高きは極むべからず、而も心は天の上に出づ、地の厚きは測るべからず、而も心は大地の下に出づ』
と云へる語とを思はしめる。宇宙の本體である梵は無限小であり同時に又無限大である。一切處に偏通し一切時に偏滿して居る。この宇宙の本體たる梵と個人の本體たる我とは畢竟同一體である。小宇宙(マクロコスモス)と小宇宙(ミクロコスモス)とは同一體である。『それは汝である』、『吾は梵である』ことを悟る。この大小兩我の畢竟同一體なること即ち梵我一如の理を十分理解するのが婆羅門教の悟で、婆羅門教で梵涅槃と云へるものは即ちこれのことである。
大慧は
『不渉他塗徑與本地相契』
といひ、
『久久純熟默默契自本心』
といつた。無門關には
『者箇胡子直須親見一回始得』
といひ、
『識得自性方脱生死』
といつてある。これに類する語句は禪書の中から無數に拾ひ出すことが出來ると思ふが、要するにこの上の勞作の必要はない。禪宗でいふ所の證悟即ち契當即通、見性悟道、心性を徹見すといひ、或物に契當すといひ、或は自己本來の面目に相見するといふ時の気分は婆羅門教の梵我の一致、契當などといふ時の気分と異る所はないものと私は信ずる。
つまり吾が禪宗はウパニシャッド系の印度思想と大體三の點に於て一致する所がある、第一は汎神論的世界觀の上に於て、第二は我を談ずる上に於て、而して第三にはこの證悟契當の上に於てと斯いふのである。
これから進んで原始佛教と、禪宗を比較し、兩者が如何なる點に於て一致し又如何なる點に於て背駆するやを考察して見たいと思ふ。吾吾は第一篇で婆羅門教と原始佛教とを比較した時、これ等の問題にも多少觸れないことはなかつた。今少しく詳しく言うと、原始佛教の婆羅門教と異なれる點として擧げたものはまた禪宗の婆羅門教に異なれる點であり、同時に禪宗の原始佛教と共有する點である。
以下吾人が數章を設けて兩者の比較を試みんとするは兩者の共通點をば更に明にせんとする意に出づるに外ならない。
戒定慧の三學は共に竝べ進むべきものともいへようし、又は修行の順序によつて斯う竝べたものといへよう。即ち戒によつて先づ身の行を正しうし、定によつて心を練り、心を落付け、その定の力によつて獲る所の如實の知見、即ち悟が慧である。それでこの三を戒定慧と斯ういふ順序に竝べたのは決して無意味ではなく、大體修養の順序に隨つてならべたものである。今少し詳しく言うと、原始佛教の教によれば佛教者は先づ第一に品行方正でなければならない。在家の人ならば五戒、八齋戒、又は十善戒を持ち、出家の中で沙彌は十戒、比丘は二百五十戒‐通常二百五十戒といつて居るが、その實は二百二十七戒しかない‐兎に角これだけの戒を持つて先づ身の行を正しうせねばならない。これが即ち戒である。佛は曾て鬱低迦(ウッチカ)に告げて
『汝當に先づその戒を淨うし、その見を直うし、三業を具足すべし』(『雜阿含』二四卷二〇經)といはれた。
定慧は定力によつて慧が得られるともいへようか、この二は又平行するともいへよう。通常吾吾は禪定といつて二者を同一物のやうに思うて居るが、實際は禪は禪那(ヂャーナ)で思慮する方だし、定は三昧(サマーヂ)又は三摩地(サマーヂ)で落付く方である。即ち禪は觀(Vipassana)に當り、定は止(Samatha)に當る。定と禪とが竝べ進められると、最後に悟に達する。それが即ち慧である、完全なる慧である。
戒定慧の三は平行すべきものたるにせよ、次第順序のものたるにせよ、これが原始佛教に取つて極めて大切のものであることは勿論いふまでもない。佛教修養の要領はこの三大項目の中に収め盡されて居るといつて差支へがない。この點は我が禪宗も全く同一であるといつて宜しからうと思ふ。神秀禪師は七佛通誡の偈の第一句諸惡莫作を戒、第二句衆善奉行を定、第三句自淨其意を慧に配當して教へた。慧能禪師之を聞いて、これは大乘の人を説得する禪である、しかしまだ本當のものではない。自分の教へる戒定慧は最上乘の人を説得する教であるといつたといふ。慧能禪師の批評が中つて居るか否かは知らぬが、兎に角この三は佛教修養の大眼目で、佛教の修養は戒なる道徳的修養から初まり、定慧なる宗教的修養に終る。私の考では諸惡莫作、衆善奉行は道徳的修養で、自淨其意は宗教的修養である。斯う申すと先の神秀禪師の配當されたものと合わない樣であるが、これは勿論きちんと合ふべき性質のものではない。兎に角佛教の修養は戒に初まり、定慧、或は單に慧に終る。道徳的に出發して宗教的に終るといふことでなくてはならぬと思つて居ればよい。以下我が禪門が如何に小乘戒を見るかに就て少しく話を進めて見たいと思ふ。
禪宗より小乘戒を見る見方には大體二通りあるやうである。その一は禪宗の第一義諦門からこれを見下さんとするもので、この見方からすれば小乘戒などはまるで眼中にはない。『禪戒鈔』の中にいつてあるやうに
『コノユヘニ聲聞ノ持戒ハ菩薩ノ破戒トイフナリ』
といつた調子で、これを戒と名くるさへ既に烏滸の沙汰である。同書の中に
『五戒十善ハ人天ノ果ニシテ是世間也、不可謂出世、又二百五十戒マデハ不離世間天上以欣上厭下假令至非想非非想而壽盡墮無間獄也、シカルヲオロカナル族ハ五戒十善二百五十戒等ヲ受授スル小乘ノ行人アレバ此名相ノ砂石ヲ以テ一句ノ聞法ヨリ功徳多シト思へり』
といつてある。これが禪宗の第一義諦門から、小乘の五戒十善戒二百五十戒の如き有漏戒を見た見方であらうかと思ふが、この見方からして言へばこれもなるほど、至當の言であらう。尚ほ同書の不殺生を説明せる條に
『殺不殺ノ詞ハアリトイヘドモ不似世間其上三界唯心ゾ、諸法實相ゾト談ズルトキ殺トモ不殺トモ不可談』
といひ更に
『流轉生死ノ生ニ對シテ殺不殺ヲ判ズルコトハ眞生ノ理ニソムク上ハ殺モ不殺モ爭デカ破戒ノ義ナカランヤ、從來ノ殺不殺ハ二ツナガラ破戒ナルベキナリ』
といつてある。即ち三界は唯心の所現であり、諸法はそのまま實相の當體であるからはその上に殺すものと殺されるものと差別されてあるべき筈はない。殺不殺を論ずるは眞生の理に背き破戒の過に陷るものである。唯心の上、實相の上には殺すものとか殺されるものとかいふ對待はない。これをありと見るは凡夫の妄見である。大乘一心戒、心地無相の戒の上では能殺所殺の別ありと見るはそれが既に破戒である、と斯ういふのである。これは不殺生戒に就ていつたのであるが、その次なる不偸盗戒、不妄語戒、その他に關してもこれと殆んど同じやうなことがいつてある。
此處で吾吾は『聖薄伽梵歌(スリーバガヴァドギーター)』の一節を引いて試にこれをこの『禪戒鈔』の文と比較對照するの甚だ興味あることを感ずるものである。梵歌の本文を引用するに先ち、そのいはれを簡單に記して見ると、クル族のパーンヅ王の五子とヅリタラーシュトラ王の百子との間の長い葛藤の果、兩方は戰場に於て雌雄を決せんとして居る。パーンヅ王の第三子アルジュナはヴィシュヌ天の權化で、王子のために車を御して居るクリシュナに對して同族相鬪ふ(彼等は從兄弟である)の非理を説き、斯の如き戰に加はるに就ての悲痛の情を述べる。クリシュナは王子を慰諭してその非理にあらざることを説くが、その語の中に
『彼現身者(我)を見て能殺者とするもの、またそを所殺者とするもの、この兩者は倶に知らざるものなり、彼は殺さず、又殺されず、彼は生まれず、彼は死せず、曾て出現せず復更に出現せざるべし、不生にして常住、永遠にして盤古なり、身は殺さるるも彼は殺されず。
人若しそを不壞なり、常住なり、不生なり不滅なりと知らば誰をか殺さしむべき。……刀もこれを截らず、火もこれを燒かず、水もこれを濕さず、風もこれを乾かさず。
こは截る能はず、燒く能はざるものなり、濕ほすも得ず、乾かすも得ざるものなり、常住にして普遍、堅固にして不動なり、永久なり。
彼は非顯現なり、不可思議なり、不變化なりと稱せらる。故にかかるものと知らばこれを憂ふべきにあらず。』
といふ一節がある。即ち兩者の間に驚くべき一致點のあることが判るであらうと思ふ。吾吾が殺した殺されたと思うて居るのは、いふまでもなくこの目に見得べき肉身に就ての話で、この肉身の奥に潛める‐といふは語弊があらうが‐絶對の本體、即ち『禪戒鈔』の中に唯心又は實相と呼べるものの上には殺不殺の談は出來ないことである。それで『殺不殺ノ詞ハアリト雖モ不似世間』といつてある。此處でさういふ話をするのは根本的に間違つて居るといふので『從來ノ殺不殺ハ二ツナガラ破戒ナルベキナリ』といつた。絶對界に入つては殺生の事實も殺生の話も共に出來ないことであるからして『佛戒ニハ總テ殺生ト云フ事ノイハレヌナリ』といつてある。『聲聞ノ持戒ハ菩薩ノ破戒ナリ』といへるも勿論この意味から言つたもの、即ち第一義諦門から見下して言つたものである。
今この唯心、實相又は法性、眞如、佛身、佛心などの語を用ひて指せるものを『聖薄伽梵歌(スリーバガヴァドギーター)』に『我』と呼べるものに代へて見よ。吾吾はそれを吾が大乘禪の眼から見て、婆羅門教の眼から見ると同じくその中に少しも矛盾を見出すことがないであらう。『彼(我)は殺さずまた殺されず……身は殺さるるも彼は殺されず』とある。此處に『身は殺さる』とあるは即ち上の世間の殺生、聲聞の殺生、從來の殺生をいふので、『彼殺さず、また殺されず』といへるは『眞生ノ理』の上の殺不殺、菩薩の殺不殺、禪門獨特の殺不殺に就ていふのである。
心地無相の戒、禪戒一如の戒、達磨の一心戒といふやうな高い見地からしたならば小乘の戒法は斯うして一言の下に貶さるべき運命のものであらう。しかし斯う貶されるのは啻に小乘戒ばかりではない、教相家の戒と雖もやはり同樣の運命のものである。『禪戒鈔』の序には『教家之所謂戒定、名同趣異、源一流別』といつてある。小乘の戒律にせよ、教相家の戒律にせよ、禪門の戒にせよ、その本源に溯れば同一であるべきであるが、その支流になると斯の如き相違を生じたのである。しかしこれは教家の戒であるか否かは知らぬが、同じ不殺生戒を談じ、不殺生戒のあり得べからざることをいふにしても慈雲尊者の語はまだ曖昧がある。尊者は『十善法語』の中に
『一切衆生は我が子なるに由りて、一切有命のものに對すれば不殺生戒と名くる。此に我が子といふは世間親子の間は睦まじきものなるによりて、之に比べて説いた言ぢゃ。實は一切衆生の心念思慮を以て自己の心とすることぢゃ。自身と一切衆生と平等にして元來隔てなきぢゃ』
といつて居られる。これを『禪戒鈔』の『眞生ノ理ニ背ク』からして殺不殺の話は出來ぬといふのに比すると、大分趣が異なつて居る。同じく『殺生の出來ない』といふにしても『禪戒鈔』や『聖薄伽梵歌(スリーバガヴァドギーター)』では殺生不殺生といへる理屈がない、殺しても殺すことにはならぬではないかといふ調子である。前者ではまさかそれまではいつてないが、後者には明かにさういつてある。これに比すると、慈雲尊者は『一切衆生皆是吾子』ではありませんが、『山鳥のほろほろと鳴く聲聞けば』と歌つた人もあるではありませんか、『一切衆生の心念思慮を自己の心』として御覽なさい、殺生なぞといふ無慈悲な事が如何して出來ます。それですから有情を殺すことは出來ません、と斯ういふのであるが、同じく殺すことが出來ませんと云ふにしても『禪戒鈔』や『聖薄伽梵歌(スリーバガヴァドギーター)』の「出來ません」と慈雲尊者の「出來ません」とは大へん意味が違ふし、心持が違ふ。前者は法身佛で、後者は現身佛である。後者の方がよほど人間味豐富である。
禪門の第一義諦の上から見れば殺不殺持戒破戒は成り立たないことは上に述べた通りである。第一義門からいへば殺不殺持戒破戒の談は不可能であるが、第二義門の上ではこは必ずしも不可能ではない。不可能でない所ではない、殺不殺持戒破戒は此處では大なる意義を有つこととなつて來る。先には『聲聞ノ持戒ハ菩薩ノ破戒ナリ』といふ文句を引用したが、第二義門の行を尊しと見る上からいへば小乘の戒とてさう貶しつけらるべきものではない。高祖大師は勿論のこと、支那で清規を作られた人たちは大體この態度を取られたやうである。高祖は眼藏の『受戒卷』には『禪苑清規』を引いて
『既受聲聞戒應受菩薩戒』
といはれ、『衆寮清規』の劈頭には
『寮中の儀まさに佛祖の戒律に敬遵し、兼て大小乘の威儀に依隨し、百丈の清規に一如すべし』
といはれ、さらに『辯道話』の中には
『この坐禪をもはらせん人、かならず戒律を嚴淨すべしや、しめしていはく持戒梵行は、すなはち禪門の規矩なり、佛祖の家風なり』
と云はれ、『出家卷』『受戒卷』には『禪苑清規』を引いて
『三世諸佛皆出家成道を曰ひ、歴代祖師佛心印を傳ふ。盡く是れ沙門、蓋し毘尼を嚴淨するを以て方に能く三界に洪範たり、然れば則ち參禪問道は戒律を先となす』
と云はれて居る(「毘尼を嚴淨する」以下の文は榮西禪師の『興禪護國論』にも引いてある)。高祖とても先きの『禪戒鈔』についてあるやうな高邁な見識を有たれないではない。但高祖は智と行、知目と行足とを峻別し、智は高遠なるべくとも行は卑近なるべきことを尊しとせられた。これに就ては眼藏や大清規の中から無數の證據を引いて來ることが、更に煩はしく引くの必要はない。
そこでこの戒定慧三學の中で定慧のみならず戒をも同じく重しと見る點に於て原始佛教と禪宗とは全くその揆を一にするといつて宜しからう。但禪門の戒は心地無相の戒とか禪戒一致の戒とか菩薩清淨の大戒とかいつて極めて抽象的のものであり、禪院の規矩として禪僧行履の標準として用ひられて居るものは支那では百丈清規とか、禪苑清規とか、勅修清規とか、吾が日本の曹洞宗では重に大清規、稀に小清規、瑩山清規といふもので、印度で造られた毘尼即ち律とはその内容が非常に違つて居る。隨つて例へば得度、受戒、安居、自恣、布薩などいふ語は原始佛教と禪宗と兩者に共通に存するが、その事柄は非常に異なつて居る。しかし佛祖の戒律にせよ大小乘の威儀にせよやはり戒である。僧伽全部又は個個の比丘の行に關する規則を説いたものであるから、これを戒と見るも一向妨ぐる所はない。高祖の『戒律を嚴淨すべし』とか、『持戒梵行はすなはち禪門の規矩なり、佛祖の家風なり』とか、いはれた心持を察すれば高祖は大乘戒と同じく小乘の戒律をも重んぜられたことが判る。要する所禪宗は定慧と同じく戒をも重んずる宗旨である。
佛といふ語は佛陀、即ち梵語及び巴利語のBuddhaの上の一字をもちひたものである。Buddahaといふ語は語根(ルート)budhに接尾音(サフィックス)taが加はつて出來たもので、この語根には『煩惱連續の眠から覺め、或は四聖諦を悟り、或は涅槃を證する』と註されて居るから、Buddhaには「覺めたる、知りたる、悟を開きたる、涅槃を證したる」などの意義があるわけである。これを通常『覺者、智者』と譯してあるのはよく當つて居ると思ふ。特に『覺者』なる譯語の目ざめたるの意と悟りたるの意とを兼ねて居るのは興味あることである。音譯では佛陀、浮陀、佛駄、歩他、浮圖、浮頭、勃陀などの文字をあててある。このBuddhaにsam更に又samyakの接頭音(プレフィクス)を加へてSambuddha、samyaksambuddha即ち三佛陀及び三藐三佛陀といふ文字を作り出した。前者は『等覺者、遍智者』の意味、後者は『正等覺者、正遍智者』の意味である。場合によるとサンミャクサンブッダは佛を表はし、サンブッダは辟支佛、而して單にブッダといふは聲聞を表はすと解することもあるが、通常この三語は共に佛を表はすものと解する。
辟支佛もやはり佛である。通常の佛と同樣、自分獨りで師なくして悟を開くものであるが、通常の佛とは違つて、自分が悟を開いた後それによりて他を教へ導くことがない。自分が得た悟を自分獨りで味はひ十分享樂した上、時機が來れば涅槃に入る人たちである。梵語にはPratyeka-buddhaといふ、『獨り獨りで覺りたる』ものの意である。隨つてこれを『獨覺』と譯するのは當つて居るが、『縁覺』と譯するのは當つて居らない。これは通常『辟支佛は十二因縁を觀じて獨りで悟を開くから縁覺と呼ぶ』と解せられて居るが、これはさうではなくして、pratyeka(辟支、獨り獨りの意)といふ形容詞がpratyaya(男性名詞、縁の意)又はpratitya(中性名詞、縁の意)と甚だしく似て居るところから生じた混同であると私は思ふ。『六度集經』三卷にこれを譯して『縁一覺』といつてあるのをも併せ考ふべきである。これは上のpratyaka又はpratityaとpratyekaのekaとに特に眼をつけて譯した語で、かのAvalokitesvara(觀自在)を『觀世音』或は『光世音』と譯するのと同樣、大へん複雜せる誤譯である。辟支佛は佛は佛でも他のために法を説くことをしない、隨つて眞の意味の佛ではない。眞の意味の佛はサンブッダ、サンミャクサンブッダである。此處に吾吾が意味する佛とは言ふまでもなく、この佛のことである。
佛といふ語は專門的に或は通俗的に種種樣樣の意味に用ひられて居る。その通俗的の用例は今此處では措いて論じないとして、吾吾はそれが三身四身乃至十身いろいろ違つた佛身を表はすやうに用ひられて居ることが解るのである。しかしこの中で最も普通に知られて居るのは法報應の三身説であらう。この三身説は勿論後世の發達せる大乘佛教のものであるけれども、その思想だけは原始佛教にもいくらかあると云へようかと思ふ。法身なる語の『佛遺教經』の中に出て居ることは誰も知れる通りで、此處に佛は
『自今已後我が諸の弟子展轉してこれを行ぜば即ちこれ如來の法身常に在して而も滅せざるなり』
と仰せられたとしてある。此處に法身常住といへるは法身佛、即ち法を身とせる佛、その所説の法の上に身を留むる佛は、弟子たちが教の通りに修行して廃せざる限り、又所説の法を護持して失はざる限り、その法と共に常に世に存在するであらうとの意である。隨つてこの法身は法華經や眞言密教で教ふる所の法身とは全然別物である。法身といふ語は同じくても久遠の釋迦牟尼佛や常住普遍在の大日如來を指して法身と呼ぶのとは全くその意義を異にして居る。
『法身』の語は巴利文學の中にも諸所に用ひてある。此處に用ひられた法身の意義によると、佛は單に法の王、法の主であるばかりでなく、法そのものである。法の體現である。佛は
『法を見るものは吾を見、吾を見るものは法を見る』(巴利『雜阿含』三卷一二〇頁)
といはれた。この期の中には佛即法、佛身即法身といふ思想も含まれて居ると思ふ。佛弟子阿難陀は曾てその同行の衆に對して説法して
『佛は眼であり、智であり、法であり、梵であり、説教者、導利者、施甘露者、法王、如來である』
といつた。佛自身も曾て
『佛は法を身とし、梵を身とし、法そのものであり、梵そのものである』
といはれた。此處に法と梵とを對立させたのは頗る興味あることで、當時本系の印度思想によれば梵即ち絶對自存者は宇宙の第一原理であり、本體であつて、梵そのものと合一することは婆羅門の悟、即ちその終極の目的であつたから、佛が佛は梵を身とし梵そのものであるといはれるのは、或意味に於ては佛はこの説を肯定されることになり、佛身、法身、梵身の三身一致の法身の思想は大乘佛教の法身の思想と大へん近いもののやうになつて來る。但巴利語の註釋家は佛を『梵を身として梵そのものたり』といふ時の梵は『優れたるもの(ゼッタブータ)』の意であると解して居る。この『佛は法を身とし梵を身とし云云』といへる經文はAgganna-suttaで長阿含の『小縁經』の原典であるが、譯文なる漢文『小縁經』に法身梵身の語を見出し得ざるは遺憾である。なほ『法を見るものは吾を見る』の句も漢譯『雜阿含』四七卷二五經には見出されない。
報身佛の根底をなせる思想は何であらうか。『大乘本生心地觀經報恩品』には
『是故に諸佛身は眞善無漏、無數大劫、因を修し、證する所』
とあるが、この『無數大劫因を修して證する所』とある酬因感果こそはその根底をなせる思想であらう。さうすれば原始佛教にもこの報身佛の思想はやはりあるといふことが言へようと思ふ。勿論後世の發達佛教に於けるやうな色身無邊、壽命無量などの特徴があり屬性があるのではないが、しかしこの報身佛の思想の萌芽とも見らるべき朴素な思想は原始佛教にも勿論あつた。それは佛の大悟徹底される前、菩薩としての修行時代が即ちそれである。成道以前の釋尊の修行事は巴利文の『出家經』(諸經要集四〇五‐四二四)、『羅摩經』(中阿五六卷)、『精勤經』(諸經要集四二五‐四四九)などに出て居る。巴利文『本生經(ジャータカ)』には總て五百四十七の物語が載せてあるが、これは釋尊が前世に於て人間では國王大臣婆羅門居士苦行者旋陀羅など、動物では獅象鹿猿馬兎など、鳥類では白鳥鳩鸚鵡鶉その他種種樣樣のものに生れ出て、常に自分の身を苦しめて他のものの利益を計り、惡を避け善に就いて人に道徳上の規範を示された事蹟を集めたものである。この經の理想とせる所によれば前世に於ける佛‐それを菩薩と呼ぶ‐は斯うして五百餘生の間(これも勿論只その一部分であらう)生れ代り死に代りして慈悲喜捨の四無量心と布施持戒忍辱精進智慧眞實決定出離慈悲捨の十種の波羅蜜の完全に徹定する所まで行ひ果された時初めて菩薩は佛となるべき期待を以てこの世に生れて出て來られたといふのである。釋尊は斯うして四阿僧祇十萬劫の間生生世世道徳行を行ひ、最後に成佛の誓願を果たされたのであるが、この時は佛は肉身の上では三十二相八十隨好紫磨金色を完全に具へ智力の上では十力、十八不共法、四無所畏の如き佛特有の特色を持つて居られたとしてある。巴利文『大般涅槃經』や英譯の『遊行經』には世尊は若し望まるれば一劫の間世に住まれることが出來たといつてある。しかしこれだけでは色身無邊とか、壽命無量とかいふわけには行かぬ、即ち報身佛の理想にはまだまだ遠い所がある。ただ上に引いた『出家經』や『羅摩經』の只今生だけの釋尊成道前の修行を引き延ばして過去の生生に生れ代り死に代りして成佛の素因を漸次に作り上げられたとした所を見ると、斯うして次第に報身の理想に近づいて行かれるものであることだけは察することができよう。阿彌陀佛の如き理想の報身には到底及ぶ所ではないが、酬因感果が報身の思想の根底を形造れるものである以上その朴素な理想は原始佛教中にもこれを見ることが出來るといつて宜しからと思ふ。
しかし眞實の意味の佛は釋尊から出發しなければならない。釋尊の在世年代は確かには判らぬが今最も多く信ぜられ居る所は西紀五六三年から四八三年までの間といふことである。刹帝利種の出で迦毘羅衛國(カピラヴァッツ)の淨飯王(スッドーダナ)を父とし、その妃摩耶(マーヤー)夫人を母として生れ出られた。その誕生の際に劇的の事實ありしことは遍く人口に膾炙せる所で、幼兒から冥想を好める質の王子であつたらしく、これに就ては一の興味ある傳説が傳へられて居る。しかし佛教の教理と結びつけられて最も興味ある且つ最も意味深き釋尊傳の一部はその四門出遊に關することである、傳ふる所によれば釋尊は馬車に乘つて遊園に游ばんがため四回に東南西北の四門を出で、老者病者死者及び出家者を見られたといふ。この四門出遊によりて釋尊は世に老病死の苦痛あること、出家によりてこの苦痛より脱し得べきことを悟られた。佛教教理の要諦は離苦得樂、出離得脱又は轉迷開悟である。而してこの教理の要諦はこの四門出遊の事實の上に明かに示されて居るといつてよい。
四門出遊の際に見られた老病死者及び出家は釋尊に對して極めて深刻なる感動を與へた。この時釋尊はお年既に二十九歳であつたといふから、早熟なる印度人としては、特に王者の家に生れ出られた一人としては、世間の快樂を味はるべき時間の十分にあつたことは勿論いふまでもなく、又如何なる類の快樂と雖も求めて得られないものはなかつた筈である。一方からは又印度人の二十九歳といふ年齡は家庭的の安定を求むる頃である。釋尊にも耶輸陀羅(ヤソーダラー)といふ妃があり、羅④羅(ラーフラ)といふ兒があつた。而して身は一國の太子であるから普通の人であれば家庭的の安定を得べき條件は悉く備はつて居たと思はれるが、釋尊には普通の人の經驗せざる又は經驗し得ざる惱みがあつた。愛も位も富も如何ともすることの出來ない惱みがあつた。それで釋尊は妻子の恩愛を棄て、やがて來るべき國王の高き位置をも一國の富をも弊履の如く棄てて出家し、赤裸裸の一乞丐となつて苦行林の中に入り、出離解脱の道を求むるためには如何なる苦患をも辞せられなかつた。これが釋尊の苦行時代といふものである。
梵語のタパス(Tapas)は苦行の意味である。釋尊出世當時の印度人はこのタパスによつて、解脱及び神通が得られるものと一般に信じて居た。上の第四章にも述べた通り婆羅門經では苦行、智慧、供犧、及び信仰の四によつて解脱が得られると説き、佛教と殆ど同時代に起つた耆那教では供犧だけは反對したけれどもやはり苦行を行ふことを勸めた。それて釋尊も當時一般の人人の信ずる所に隨うて苦行を行はれた。上にも引いた中阿含『羅摩經』の原典Ariyapariyesana-suttaには佛が修業中如何に烈しき苦行を行はれたかが精しく説いてある。或は一粒の米、或は一粒の麻を喫して一日を過された。六年の久しきに亘つて斯うした極度の苦行を行はれたけれども解脱の道に於ては更に得られる所がなかつた。此處に至つて釋尊は苦行は徒らに自己の身心を苦しむるに過ぎぬこと、それよりも普通の飮食を取つて體力を回復し禪定によつて解脱を求むるのが正しい道であることを悟られた。それでその苦行林の傍を流れて居る尼連禪河(ネーランヂャナー)に浴して身體の垢を去り村長の息善生(スヂャーター)の獻ずる乳粥を受け、それを喫して體力を回復し、菩提樹の下に坐つて『堅固の誓を建立し、解脱の道を成ぜんと要す』といふ意気込を以て大禪定に入られた。此處に世界歴史上の一大事實ともいふべき佛成道が續いて起るのである。
佛傳の吾吾に教ふる所によれば釋尊は成道後その自得の法門を一切衆生の前に開示すべきや否やに就て躊躇された。自分が悟り得た法は甚深微妙である。それを説いても衆人は解せぬであらう。それだから説くことは止めにしようといふ年が佛に起つた。『普曜經』の文を引いて見ると、佛は
『我今これを説くとも、衆人は解せじ、我が今日の如き默然たるに如かじ』
と、しばし躊躇の念を懷かれた。そこへ梵天が現はれて佛に説法を勸請する。それから佛は説法の決心をしてその相手を求め、佛陀伽耶より鹿野苑に向はれる。この途中佛が活命外道の優波迦(ウパカ、羅摩經では優陀、五分律では優波耆婆(ウバヂーヴァ)に作る)に會はれると、彼は佛の相好を見て驚異の念を懷き、佛は誰人なりや、誰を師として悟を得られしやと問うたので、佛は彼に答へて
『吾には師あるなし、吾には等しきものなし、人間及び天人の世界に於て吾に及ぶものなし、吾は世の阿羅漢なり、吾は無上の師なり、吾は唯一の等正覺者なり、吾は清涼歸寂(の人)なり』
といはれた。これが佛の自分の成佛を宣言された第一の例である。つまり佛は斯くして成佛の自信と一切衆生救度の慈念とを懷いてこの世界に出て來られたのである。
佛は如何に自身を見られしや、如何に自分自身を見られたであらうか。單に一個の人間に過ぎぬものと見られたであらうか、或は又人間以上のものと見られたであらうか。一方には佛を呼んで兩足尊(デイパヅッタマ)といふ。これは人間中の最上者といふ意味であらう。佛傳中には佛が魔王の脅迫に會はれ、魔女の誘惑に會はれたことを語つて居る。勿論共にこれを退けて無事なることを得られたが、これは一面には佛の人なることを語れるものと見ることも出來る。或は又その日常生活の状態から見ても、原始佛教の佛には人間味豐かな點が非常に多いやうに思ふ。日日の乞食、教誡、入定、食事、入浴、或は朝早く濟度すべき人を見てそれを濟度せんがために自ら赴かれる。日中午後は樹林の中に入り樹下に晏坐して半日を過される。午後夕方近くなると在家出家の弟子たちのために教を説かれる。夜分月明に乘じて遅くまで出家の弟子たちのため教誡を埀れられたことも際際あつた。斯うして佛は單に人間の師として仰ぐべき點が非常に多いのである。しかし又曾て香姓(ドローナ)婆羅門といふもの(『雜阿含』四卷一四經には『豆摩』、『別譯雜阿含』一三卷一八經には『煙氏』に作る)が佛に對して、汝は天人(デーヴァ)なりやと問へるに應じて非ずと答へ、乾沓和(ガンタルヴァ)なりや、龍(ナーガ)なりや、閲叉(ヤクシャ)なりや、乃至人なりやと問へるに應じて同じく非ずと答へ、最後に『佛と、婆羅門よ、吾を斯の如く知れ』と答へられた。或は『佛は人天界の最第一者と稱せらる』といふ文もあるし、佛を『天中の天』『天上天』又は『天人師』とも呼ぶし、神通奇瑞に連關して佛の周圍には神秘味がまた至つて豐かである。これ等は總て佛自身の信ぜられたことであるか否かは容易に斷言出來ぬが佛が人間であつて而も通常の人間以上の力あるもの、或意味では通常の人間でないといふ自身を有つて居られたと言つて宜からうと思ふ。
禪門の佛とは如何なるものであらうか。語を換へて言へば禪門で『佛』といふ時第一に思ひ及ぶものは何れの佛であらうか。法身報身應身の何れかであらうか。或はこれ等以外の何かの佛であらうか。禪宗が實大乘である以上それに法身佛の思想のあることは論を俟たない。現身の釋尊は然燈佛の所に於て記別を受けてより過去三大阿僧祇劫の修行を經て來て佛となられた。即ち酬因感果の佛である、と斯ういふから此處には報身佛の思想もあるであらう。或は又禪門では吾吾自身が佛であり少くも佛になり得る可能性を有つて居る。吾吾は迷つて居るから凡夫であるが悟ればこのまま佛であるといふ。これを己身佛と呼んで置かう。臨濟禪師が
『此の三種の身はこれ汝が即今目前聽法底の人なり。祗外部に向つて馳求せざるが故に此の功用あるなり』
といつたのは吾吾の一身に三身佛具はつて居ること、佛を見るためには吾吾は外に向つて馳求するの要なき意味を述べたものであらう。但この身このまま佛であるといふ意味では決してない。正法眼藏の『即心是佛』の卷には
『癡人おもはくは、衆生の慮知念覺の未發菩提心なるをすなはち佛とすとおもへり。これかつて正師にあはざるによりてなり』といひ、又
『しかあればすなはち即心是佛とは發心修行菩提涅槃の諸佛なり、いまだ發心修行菩提涅槃せざるは即心是佛にあらず』
といつてある。
併し禪門で佛を本師釋迦牟尼佛大和尚として拜み、その佛が四月八日に降誕され、十二月八日に成道され、二月十五日に涅槃に入られたといふ時、その佛に就て思出すのは如何なる佛であらうか。釋迦牟尼佛の名によつて法身佛又は報身佛が意味される場合もないではない。眞言密教では發心の大日如來は釋迦牟尼佛と身を現じて大日經を説かれたと云ひ、淨土教では報身佛たる阿彌陀佛と佛教の教主釋迦如來とは同一體であるといふが、三身即一の教は密教や淨土教を借らないでも、吾が禪門にもあり得る。しかし禪門の本尊とする佛は必ずや現身佛たる釋尊、即ち黄面の一比丘として行化四十五年の後世壽八十歳にして世を去られた歴史上の釋尊を指して居ることは疑ふの餘地がない。『傳光録』に「設ひ三十二相八十種好を具足すると雖も必ず老比丘の形にして人人にかはることなし」といつてあるは實に至言であると思ふ。
佛法僧の三寶は佛教徒の信仰崇敬の對象體である。三寶の中で佛は教を説いた人、佛教を起した人で佛教信者に信仰崇敬さるべきことはいふまでもない。報は佛の證られた理、説かれた教である。昔ジュデヤの宗教で聖書が神の啓示として神聖視せられ、印度の婆羅門教でもヴェーダ、ブラーフマナ、ウパニシャッド、スートラの四が聞經(スルチ)即ち天啓經として同じく神聖視された事實に思ひ合せると法が佛教徒の信仰崇敬の對象となる所以は自ら了解されるであらう。僧は佛の説かれた教に依りて修行をする人、又は修行し終つた人で、佛の後繼者嗣續者であり、佛に代つて教を説き傳へる人たちである。佛教徒が斯うしてこの三寶に歸敬するのは正法眼藏『歸依三寶』の卷の文句を借りていへば一は大師なるが故であり、二は良藥なるが故、而して三は勝友即ち善知識なるが故である。
原始佛教時代の佛教徒は『南無佛』といつて單に佛歸命の意を表することもあつたが、多くの場合に於ては『我歸依佛、我歸依法、我歸依僧』といつて三寶歸依の意を表示したものであつた。人が初めて佛教に歸依すると、三歸五戒を受けるといふ。つまり三寶に歸依し、五戒を受ける。五戒を持つべきことを誓ふといふは佛教入門の形式で、これを誓つた上はこれを持たねばならぬことは勿論である。この語界を受け、五戒を持つべきことを誓ふに先ち三寶に歸依し、三寶を一代の師主と仰ぐべきことを誓つた。長阿含『遊行經』には福貴(プックサ)の語として
「我今佛に歸依し法に歸依し僧に歸依す。唯願くば如來、我正法中に於て優婆塞となるを聽したまへ。自今已後壽を盡すまで殺さじ、盗まじ、婬せじ、欺かじ、飮酒せじ。唯願くば世尊、我正法中に於て優婆塞となるを聽したまへ」
とあるが、これは初入佛教者の唱ふるに文句としては典型的のものである。それでこの三寶歸依は佛教入門の形式の一部であつたのである。しかし歸依三寶は單に佛教入門の形式たるに止まらず、歸依後平生と雖も亦これを唱へた。これは南方佛教國では今日も尚ほ行はれて居る習慣である。即ち一にはこれを唱ふることによりて初めて三寶に歸依するの意を表し、次にはこれを唱ふることによりて三寶を恭敬し三寶に歸依するの意を表するものと見たらよからう。
巴利文『大般涅槃經』によれば佛はその入涅槃の少し前に阿難陀のために種種の法を説かれたが、その中に佛入滅の後比丘等は各各自己と法とを燈明とし歸依所として、他を燈明とし歸依所としてはならぬと教へられた。これは通常佛教は自力教であるから、佛は比丘等の各各自己を燈明とし自己を歸依所として他の力を恃むことはならぬといふ意味、即ち佛はこの中に極度の自力主義を高調されたものであると解せられてゐるが、しかし此處に法と自己と二つのものを擧げてある所を見ると、これを單に自力主義の高調と見るは如何であらうか。これは佛は入滅して無餘涅槃に入らるれば少くも形體即ち肉身の佛は世になきものであるが、その遺教即ち一代の説法は比丘及び他の信者の記憶の中に留まるべきものであるから、佛亡き後の佛教徒は遺教を佛の口から聞く教と同樣に心得て、これを燈明としこれに歸依して行かなければならない。それで法燈明法歸依といはれたのである。同じ『大般涅槃經』の中に佛は阿難陀に告げて
「阿難陀よ、汝等の中或は師の言教は過去せり、吾等の師は世にあらずと思ふものあらん。阿難陀よ、こは斯の如く見るべきにあらず、余が汝等のために説きたる法、設けたる律、これ余が滅後汝等の師なり」
といはれたが、この語もこれと併せ考ふべきである。
次に比丘は三寶の中の一で、佛に倣うて修行するもの、佛のよられた道によつて進み、佛の獲られたのと同じ悟を獲んと努力して居るものである。即ち總て佛であるべきであり一個の比丘は各各一個の佛であるべきである。それで佛は自分が涅槃に入つた後比丘等は各各自己を燈明とし自己を歸依所として修行すべきことを告げられたのである。それでは佛在世中は「歸依三寶」であつたものが、佛滅後は「歸依二寶」でよいかというと、これは容易く斷言することは出來ないが、しかし佛は自分が滅した後も三寶に歸依せよと教へられたこともないやうである。
比丘は佛と變らない、佛のやうに修行し佛のやうに悟を開き、佛に代つて道を傳へ、教化を宣揚するもの、つまり、佛自身が佛の教の體現であつた。佛の教を形にしたものが佛自身であつたが如く、比丘も佛に倣うて修行し、佛同樣の悟を開き、佛同樣に教を説く以上やはり佛である。佛の教の體現である。佛自身が信者の歸依の對象體であるが如く、比丘僧伽も亦歸依の對象體となるのは一向不思議はない。それで僧歸依は佛歸依法歸依と同じく佛教教團成立の當初からあつた。佛が鹿野苑で五群の比丘即ち⑤陳如(コンダンニャ)以下五人の同行者を濟度された時は世にまだ僧と呼ぶべきものがなかつたので、彼等は佛法の二寶に歸依したのみであつたが、その次に度せられた耶舍は三寶に歸依して居る。即ち僧歸依は佛教成立の當初からあつて僧は佛及び法と同じく尊敬(ヤサ)され信仰されたといふことになる。
佛教は元來行の教である。教の教であるよりもむしろ行の教である。原始佛教の教ふる教は「教の法」(pariyatti-dhamma)よりも寧ろ「行の法」(patipatti-dhamma)であつた。佛もさうであつたが、比丘は自ら行うて一方には悟を求め、一方には信者の歸依の客體となり、信仰の對象となる。原始佛教ではこの通りであつたが、この點に就て今日の佛教各宗中最も多くこれに近いものを求むればそれは禪宗であらうと思ふ。禪宗は特に三寶特に僧寶崇敬の宗旨である。勿論何れの宗派も三寶を崇敬せぬものはない。この點は何れの宗派も同樣であらうが、三寶共に尊びながら、その中何れを最も多く尊ぶやといふことになると、他の宗派で或は佛寶を或は法寶を特に崇敬するに對して禪宗は特に僧寶を崇敬するものであるといへよう。即ち他の或宗派では佛法二寶の中何れかを崇敬して僧寶をあまり崇敬しない。少くも僧寶にはあまり重きを置かないのに對して、禪宗は三寶併せ崇敬する。又は特に或は少くも他の宗派以上に僧寶を崇敬するといふことになるかと思ふ。
僧とは一體何であるか、「律」の教ふる所によれば、それは僧伽(サンガ)即ち比丘の集團である。五名以上の比丘の集まつた團體である。しかし同じ團體といつてもそれにはまだ向果に入らない比丘の集團と、既に向果に入り又は阿羅漢果を得たものの集團の別が有る。眞實の意味の比丘衆即ち僧伽とはこの最後の意味のもので『法華經』の初めにある
「皆是阿羅漢、諸漏已盡、無復煩惱、逮得己利、盡諸有結、心得自在」
の文句、『別譯雜阿含』九卷の
「所作已辯、得阿羅漢、諸漏已盡、捨於重擔、獲於正智、心得解脱」
の文句は唯これに當る。『衆許摩訶帝經』十一卷に
「刹帝利族、或は婆羅門族、及び毘舍、首陀の族の善男子輩、佛に投じて出家し、鬚髪を剃除し、袈裟の衣を被、正信にて修し、聞法開悟し、悉く阿羅漢道を證得せるもの」
といつてあるのはこれである。しかし初向以上阿羅漢果までの比丘衆を一括して「應供(ダッキネーヤ)の僧伽(サンガ)」といひ、未だ向果に入らざる凡夫位の比丘の集を「假(サンムチ)の僧伽」といふ。準僧伽の意である。前者は特に四雙八輩と呼ばれ、彼等自身からいへば信者の供養に應ずるだけの徳があり、信者からいへば是等の人人に施した施物は特に大なる功徳を齎すものと信ぜられて居る。そこで彼等のことを「福田」又は「功徳田」と呼び、或は「世間の福田」と呼ぶ。世間の人の「福即ち功徳を植うる田地」の意である。これを「八福田」と呼ぶは四向四果り八つの階級があるからである。即ち信者が彼等に歸依し彼等を尊崇し衣服臥具飮食醫藥の四種の供養物を以つて彼等に施す時はその功徳は無限に增長するものと信ぜられた。彼等は極度の克己的生活を營み道念の修養に勤めるものであるから、信者の彼等に生活の資料を供給するは一は彼等の徳風を仰ぎ、自分等の道徳の模範たることに對して謝恩の意を表し、一は彼等の枯淡なる生活振りに對して同情の意を表するためである。
佛法僧の三寶を讚仰するには一定の文句があつて聖典中には所所に出て居るが、その中僧寶を讚仰する文句を此處に引いて見ると、
「世尊の弟子衆は善く行き、正しく行き、直く行き、完うして行く。この四の人雙、八の人輩、この世尊の弟子衆は貴ぶべく尊ぶべく供養すべく合掌禮を行ふべし。これ世界に於ける無上の福田なり」
と斯うである。それを可なりに意譯したものと見らるべき『增一阿含』二卷の文は
「如來の聖衆は善業成就し、質直義に順ひ、邪業あるなし。上下和穆法法成就す。如來の聖衆は戒成就し、三昧成就し、智慧成就し、解脱成就し、解脱智見成就す。聖衆は所謂四雙八輩、是を如來の聖衆と謂ふ。應に恭敬承事禮順すべし。然る所以は是れ世の福田なるが故なり」
である。つまり佛及び法と共に讚仰さるべき僧伽とは預流向上の人たち、四雙八輩、八福田と稱せられる人たちばかりであることがこれで判る。巴利文長阿含の『大會經』には
「林中に大會集あり、天人群集まれり、吾等この法會に來れり、勝たれざる衆を見んがために」
といふ文句がある。この文は此處に集まつた天人群が佛と同じく僧伽衆をも崇敬歸仰するの意を示せるものと見ることが出來よう。漢文長阿含十二卷の『大會經』には
「禮敬如來及比丘僧」
とあるが、これは皆阿羅漢たちであつたといつてある。しかし向果以下の比丘衆といふものもなくてはならない。それを假の僧伽と呼ぶのである。さういふ人たちでもそれが勝友であり、善知識であり、「能令衆生出離生死證大菩提」るものであり、「代佛宣揚」するものであればそれは佛又は法と同じく信者の歸依の對象である。
佛は曾て準陀(チュンダ)の問に答へて世に四種の沙門あることを説かれた。四種の沙門とは勝道、説道、活道、汚道の四であつて、沙門をその言行によりて四種に區別したものである。沙門とあるから必ずしも佛教の沙門には限らないと思ふが、序を以て此處に記することにする。これは巴利文では『諸經要集』の準陀經(チュンダスッタ、國譯大藏經、經部十三卷)に出て居り、漢譯では長阿含三卷『遊行經』、『倶舍論』十五卷、『根本説一切有部毘奈耶雜事』三十七卷、『瑜伽師地論』二十九卷など所所に出て居る。第一の勝道沙門とは「疑を超え、苦を離れ、涅槃を樂み、貪欲を除き、人天兩界の導師たるもので、斯る沙門は道によりて邪惡に勝つものであると云ふ意味から勝道沙門といふ。」とある。第二の説道沙門とはこの「世の中に於て最勝の法を最勝の法なりと知り、此處に法を宣説し、分別し、疑惑を斷ち、貪欲を滅する智者をいふ」とあり、第三の活道の沙門とは「よく説かれたる法句の上に生活し、自ら制し正念を失はず、過なき道に則るもの」をいひ、第四の汚道沙門とは「禁戒に己を蔽護して比丘の中に交り、卒暴⑤恣にして信者の家を亂すもの、虚僞心を懷き、自制心なく、籾糠の如くなるもの」といつてある。勝道説道活道の三種の沙門は善僧であり、反之汚道の沙門は惡僧である。法燈の明滅は一に係りてこの四種の沙門の消長によるのであらう。
前前回「佛身」の事を述べ、前回「僧伽」の事を述べたから、此度は殿堂、聖像及び僧院の事を述べなければならない。これも原始佛教と禪宗と特に似て居る點の一つであると信ずる。原始佛教時代では比丘の止住所は毘訶羅(ヴィーハラ、vihara)即ち「精舍」、又は阿羅麼(アーラーマ、arama)即ち「園」と稱したが、此處には「殿堂」即ち英語のshrine又はtempleと名へべきものはなかつた。佛教の神聖なる物體、例へば塔、寶輪、菩提樹、佛足、佛座を禮拜し、又は佛の形像を造つてこれを禮拜することは、佛滅後大分時間の經つてから、即ち西紀前三世紀以後になつてから漸次に出來た習慣で、原始佛教時代には全く或は殆どないものであつた。佛在世時代の精舍は單に「僧院」monasteryのみであつて、その中には聖像を安置する殿堂を含まなかつた。精舍は唯比丘僧の止住して入定觀念し、道念に勤むべき修道の道場だけであつたのである。
但佛在世の佛の形像に就ては『增一阿含』二八卷に下のやうな造佛の因縁といふものが傳はつて居る。佛母摩耶夫人は佛誕生の後間もなく沒し、三十三天中に往生して居られるので、佛は夫人に説法のため時時其處へ赴かれた。この世界の四衆の弟子たちはこの間久しく佛を拜することを得ざるがため、渇仰思慕の情に堪へず、一同阿難陀尊者の所に行つてこれを訴へた。拘薩羅(コーサラー)國の波斯匿(パセイナディ)王も抜蹉(ワッザ)國の優填(ウディナ)王も同じく阿難陀尊者の所に行つて佛の在所を問うたが、尊者もこれを知らなかつた。兩王はこれが本となつて病気に罹つた、優填王の群臣はこれを憂慮して王のために如來の形像を造らんことを議し、國内の奇巧師匠を集めて牛頭栴檀を以て高さ五尺の像を造らせた。波斯匿王も亦これを聞き、同じく國内の奇巧師匠を集め紫磨金を以て高さ五尺の像を造らせた。これで閻浮提の中に如來の形像二つあることになつたといふのである。
造像に關するこの傳説が單にこれだけであるならば、吾吾はこれを否定すべき理由を見出さない。優填王が牛頭栴檀を以て、波斯匿王が紫磨金を以て佛の形像を造り、又佛がその形像を造るの福徳を讚説されたといふことも必ずしもなかつたことでもなからうと思ふ。但この時代の人の造像の目的はこの經にもいつてある通り、「恭敬承事作禮」即ち唯肉身の佛に對しても恭敬尊重奉事供養の意を致すが如く、この像に對しても恭敬尊重奉事供養の意を致すといふことであつて、これを神聖の物體として禮拜するの意は毫もなかつた。これを一種の聖像禮拜と見ることを得るとするも、それは極めて素朴な聖像禮拜であつた。佛が造物の功徳を讚説されたといふのも、それは唯優填王や波斯匿王の如き在家の信者の佛像を造るの意を嘉賞されただけで、出家者のことでは勿論なかつた。
「若しは形色を以て吾を見き
若しは音聲を以て吾を求めき
是等邪斷を行ずる諸人は吾を見ざるなり」
は一見したばかりで誰も『金剛經』中の「若以色見我、以音聲求我、是人行邪道、不能見如來」の原文の譯であることに気がつくであらう。これは形式や音聲を以てしては如來を見、又は求むること難きの意を述べたものであるが、これと同じ見識は原始佛教時代の比丘もそれを有つて居た。即ちラクンタカ・バッヂャ長老は
「或は形色を以て吾を量りき
或は音聲を以て吾を求めき
これ等欲貪に制せられたる輩は
吾を知ることなし」(『長老偈』四六九)
といつて居る。形相を以て佛を見んとするの不合理なるは斯うして原始佛教者の眼にも後世發達佛教者の眼にも同樣であつた。これからして吾人は佛教の原始時代に佛像があつたとしてもそれは重要視されなかつた。少くも比丘たちはこれを聖像視しなかつた、隨つてそれを容るべき殿堂もなかつたと信ずるものである。
それで今日吾吾が呼ぶ所の神聖なる殿堂及びその殿堂の内で禮拜する禮拜の對象物即ち聖像は原始佛教時代には全然知られて居なかつたといつてよからう。佛陀伽耶、サーンチ、バルート、アマラヴァチーの玉垣には上に擧げた塔、寶輪その他のものを彫刻し、それを信者たちが禮拜する風俗をも示してある。しかし佛身そのものは示してない。これを自由に示すやうになつたのは、ガンダーラ地方にギリシヤの藝術が入つて來て所謂ギリシヤ・ガンダーラ藝術なるものの發達した後のことであつたらうといはれて居る。即ち年代の上からいへば西紀前一世紀後のことである。この頃に至つて斯ういふものが造られるやうになつたのは一は肉身を消して寂滅の境界に入られた佛の人格に對する追懷が時の經つに隨ひ、在家出家の弟子たちの念頭から次第に消え失せるので、佛を何か形に現はして追慕の資としようとする彼等の切なる願望によるものであらうが、一は斯うして外國から入り來つた藝術がその祖國で神や人を形像に表はしたと同じ心持ちでそれまで土地の佛敎徒が形に表はすには畏れ多しとして居た佛をわけもなく形像に表はしたことにもよるであらう。
巴利文『大般涅槃經』漢譯長阿含の『遊行經』の中には佛がその四大遺跡を憶念追慕するの功徳あることを説かれた有名な話が載つて居る。その時阿難陀と佛との間の問答を記すると
「爾時、阿難陀は右の肩を露はし右の膝を地に著け、而して佛に白して言へり『世尊よ現在四方の沙門耆舊多智にして明かに經律を解し、清徳高行なるもの、來つて世尊を觀る。我因みに禮敬親覲問訊を得。佛滅度したまへる後は彼等復來らじ、瞻對する所なけん。當にこれを如何にすべきや。』佛阿難に告げたまはく『汝憂ふることなかれ、諸の族姓子、常に四念あり、何等をか四となす、一に曰く佛の生處を念じ、歡喜して見んと欲し、憶念して忘れず、戀慕心を生ず。二に曰く佛の初得道處を念じ、三に曰く佛の轉法輪處を念じ、四に曰く佛の般泥⑥處を念じ、歡喜して見んと欲し、憶念して忘れず、戀慕心を生ず』云云」
と斯うなつて居るが、この中にも佛は一語も殿堂の事には言及されなかつた。隨つてその中に佛像その他神聖なる物體を安置してそれを禮拜するなどの考は毫末も佛の念頭になかつたことは素よりいふまでもないことと信ずる。
『寶慶記』の中に堂頭和尚の埀示として
「參禪者身心脱落也、不用燒香禮拜念佛修懺看經祗管打坐而已」
といふ文があり、『辯道話』の中に
「宗門の正傳にいはく、この單傳正直の佛法は最上のなかに最上なり、參見知識のはじめより、さらに燒香禮拜念佛修懺看經をもちゐず、ただし打坐して身心脱落することを得よ」
といふ文がある。これが私は禪宗の本面目であらうと考へて居る。即ち禪宗の本面目の上から云へば、佛前に出て佛に向つて燒香禮拜念佛修懺看經するの必要はない。唯打坐してそれによつて身心脱落を得ればよいのである。外に向つて外にある佛を禮拜せずして自己本心の佛を禮拜し、自己本心の佛を求め、自己本心の佛に相見しなければならぬといふのがこの文句の意味であると思ふ。『少室六門』血脈論には
「若し見性せざれば念佛誦經持齋持戒も亦益する處なし」
といつてある。これに就ては上に引いた金剛經の頌文の意をも併せ考ふべきである。
高祖大師が斯う仰せられたからとて、ご自身は佛前に燒香禮拜看經されなかつたとも思へぬ。それは大に行られたらうと思ふ。私も亦決してこれを不要のこととも無益のこととも云はぬ。しかし禪宗の本旨からいへば外にある形相に表はされた佛を禮拜したり、その前で燒香看經したりすることは無用の事、少くも不急の事で、祗管打坐、即ち坐禪さへして居ればよい筈である。この點は原始佛教とても同樣で、事實佛の時代には比丘が佛像に向つて燒香禮拜したとか、修懺看經したとかいふことを聞かぬ。念佛念法念僧の三念、六念又は十念といふことはあつたが、これは今の念佛とは全く趣を異にして居るし、高祖の意味せられた念佛も恐くこれとは違つて居ようかと思ふ。それでこの打坐の一行が修養の最高目的を果たすべき方便であるといふ點に於ても原始佛教と禪宗とはその揆を一にして居るといつてよからう。「打坐の一行」といつても勿論唯坐つて居ることばかりではない。これは行住坐臥に禪を離れないこととでも云つてお射たらからう。彼の永嘉の玄覺大師の
「行亦禪、坐亦禪、語默動静體安然」
なる語はこの行住坐臥に禪を離れざる意味を表はせる語として遍く人口に膾炙せる所であるが、中阿含『龍象經』には
「住善息出入、内心至善定、龍行止倶定、坐定臥亦定、龍一切時定」
とあり、『長老偈』(六九六‐七)には
「彼の禪思者は入息を樂とし、内心善く定に住す、那伽は行くにも定に住し、那伽はたつにも定に住す、那伽は臥すにも定に住し、坐すにも定に住し、那伽はあらゆる場合に防護す」
とある。『長老偈』に「那伽」といへるは「龍」又は「象」の意であるから、この兩文は或同一原典から譯されたものであることは何人と雖もこれを看るに難しとせざる所でらうし、同時に又行住坐臥の禪(これを那伽大定といふ)を説くことは獨り後世の大乘の禪家ばかりでなくして原始佛教時代の禪思者もこれを説き且つ實行したといふことが了解されるであらう。
日本及び支那の禪宗寺院には佛殿=殿堂もあれば僧院もある。この禪宗寺院の佛殿と僧院と何れが主であるかといへば私は僧院が主であると思ふ。つまり、佛殿があつて其處へ佛像その他の神聖なる禮拜の主體が安置されて居り、そこへ出家人は勿論、在家人が來て禮拜をする、祈祷をする、僧侶はその間に立つて禮拜祈祷の仲介をする。といふやうでなくして、禪宗寺院は僧院が主であるが、これに付屬して佛殿があり、其處に佛像その他神聖なる形が安置されて居るといふのである。こは勿論單に在家の人のために設けられたのではなくして僧院内にある出家者がその修養の一助として佛を禮拜し、思念し、その盛徳に肖からうとする、佛の語を借りていへば「〔佛を〕憶念して忘れず、戀慕心を生ぜんがため」の目的の爲に設けられたのである。隨つて禪宗寺院では僧院が主で、佛殿は寧ろその付屬物と見るべきものである。尤も支那にせよ日本にせよ、今ではこの主從の地位が殆ど顛倒されて佛殿あつての僧院といふやうな外觀もないではない。しかし禪宗の本旨から見れば僧院が主で佛殿はこれに付屬せるものであるべき筈である。但し佛殿は人間よりも尊まれる佛菩薩の形像を安置する所であるから、僧院と同一境内にありながら、比較的形勝の位置に建てられることはあり得る。しかしそれかといつて決して僧院主佛殿從といふ説を破壞することにはならない。それで禪宗寺院では僧院が主である、語を換へて言へば禪宗寺院は僧侶の修行を目的として建てられたもので、禮拜祈祷を目的として建てられたものではない。而してこの點が禪宗の原始佛教と一致する今一の點であると信ずるのである。
寒岩枯木といはふか古廟香爐といはふか、一切の情謂を忘却し去つて、吾吾の所謂人間味といふものは少しもない、唯主觀的にのみ生きて居るといふ。これが吾吾が古昔の阿羅漢に就て描き出す第一の觀念である。彼等は自内證の法樂を自分獨りで味はひ、その中に自分獨りで滿足を見出し、自分以外には非常界に對しては尚更のこと、有情界に對してさへも、少しの興味をも感じない、宛然あれどもなきが如き態度を取つたかのやうに思はれる。斯ういふ阿羅漢たちに自然を見て樂しむだけの情味があつたであらうか、或は又其處にインスピレーションを見出すだけ彼等に自然との神秘的な交感があつたであらうか、今度はこれを吟味して見たいと思ふのである。
中阿含四十八卷『牛角娑羅林經』によると、佛の跋耆(バッヂー)國の牛角娑羅林(ゴーシンガサーラバナ)中にお住ひの頃、佛弟子中最も優れたる人たち、舍利弗、目⑦連、大迦葉、大迦旃延、阿那律、離越多、阿難といふやうな歴歴即ち同經に『諸多の知識上尊の比丘大弟子』といつてある人たちも同じくその林中に、唯佛とは少しく所を異にして住んで居た。或月明の夜平旦を過ぎた頃目⑦連以下の六長老は一同揃つて舍利弗長老の所に往詣した。舍利弗は常に佛弟子中の第一位に推されたる人だけに大迦葉を初め斯うした歴歴がわざわざ揃つて訪うたのであろう。舍利弗は主人役として且つ一座の長老として、問を發するは自然のことである。彼は先づ阿難陀を初め七人のものに一一問を發した。『善來賢者阿難陀、善來賢者阿難陀、(汝は)世尊の侍者にして世尊の意を解す、常に世尊のために稱譽せられ、及び諸智梵行の人に(稱譽せらる)、我今賢者阿難陀に問ふ、この牛角娑羅林は甚だ愛樂すべく夜は明月あり、諸の娑羅樹皆(花を著け)妙香を敷くこと猶天花の若し。尊者阿難陀、何等の比丘か牛角娑羅林を起發す。』この最後の一句は巴利文によれば『如何いふ比丘によりて牛角娑羅林は美しう見えるでせう。如何いふ比丘が此處に住んだらこの林園は特に光彩を放つでせう』といふ意味だとある。同じやうに他の六人のものにも問うと、彼等は各各その得意とする立場からして説明を試みた。即ち阿難陀は多聞第一の人といはれるだけに、廣學多聞の比丘こそはこの樹林に一段の光彩を添へるでせうといひ、離越多は禪定を廃せず、觀念を成就した比丘、阿那律は天眼を成就したるもの、大迦旃延は二比丘法師の共に甚深の阿毘曇を問答論議するもの、大迦葉は無事少欲知足等十箇條の事柄の上に自らこれを行ひ、他のこれを行ふを稱説するもの、而して大目⑦連は大如意足、大威徳あるものこそはこの樹林に住んで、それに一段の光彩を添へるでせうといつた。
『如何いふ比丘がこの樹林をしてますます光彩あらしめるか。』斯うして自然が人事と結びつけられて經典中の一の題目となれることは原始聖典では類の少い例であるが、當時の比丘の多く林園の中に生活したことは明かな事實で、迦尸(カーシー)國婆羅奈斯(バーラーナシー)城附近の鹿野苑を初め、拘薩羅(コーサラー)國の祇陀林(ゼーダバナ)、摩掲陀(マガタ)國の竹林(ベールバナ)、毘舍離(ベーサーリ)國の大林(マハーバナ)の如き、釋尊の多く錫を駐められた箇所は皆大なる精舍のあつた所として知られて居るが、その實は廣大な樹林であつた。彼等は斯うして自然界と親しみ、ケルンがいへるやうに自然界からして一種のインスピレーションを得たのである。
佛が曾て摩企(マヒー)河畔を遊化された時、陀尼耶(ダニヤ)といつてその一族と共にその河の畔に住んで居た牧牛士があつたが、彼は牧牛者としてのその家庭生活の平和なる気分を六首の偈に現はして見せた。その一は
『我は食を煮、乳を搾り、摩企河の畔に一族と共に住めるもの、我が屋は葺かれ、火は點されたり、されば天若し雨を降さんと欲せばこれを降せ。』(『諸經要集』一八)
といふのである。折から雨を催して來たのであらう。しかし食物も煮て了つた。乳も搾るだけは搾つた。屋根も葺いてあるし、燈火も點してある。何時大雨が降り出しても心配することはない。斯うした時俄に詩興が湧いて來たので彼はこれを口號んだのである。或は雨催ひの空合の時、佛が其處に來かかられたので、自分が家の内も外も總手の準備を調へて何時降り出し來ても差支へないまでにして居るのに、佛が三衣一鉢の身輕いといへば身輕いが、異端外道の輩の眼には哀れな見窄らしい風をして其處等を徘徊して居られるので、この六首の偈を誦したかと思はれる。彼一首を誦すれば佛また一首を誦せられ、斯くて佛が六首を誦し終られる時は彼は既に歸佛者となつて居た。雨は斯うして陀尼耶の歸佛の因縁となつた。
自然の情趣を添ふるものとしては雨はまた至極適當なものである。家を廻つてしとしとと降る雨の音はよし詩人でないものでもその趣を味はふことが出來よう。ソーローはその名著『森林生活』の中に
『穩やかな雨のさ中に雨滴のぽたりぽたりするその音にも、自分の家の回りに音を聞き物を見るにつけても、自然界の快よく惠みある親しみを俄に感じた』
といつて居る。昔の阿羅漢たちの中にもこの風趣を詩にするだけの情味を有する人はあつた。
『雨降りてその音恰も律に調へり。我が屋舍は葺かれ、風を防ぎて樂しく、我が心また定に住す、されば天若し雨を降さんと欲せばこれを降せ。』
『雨降りてその音恰も律に調へり。……心は亦身に於て善定に住せり……
『雨降りてその音恰も律に調へり。……此處に我精勤にして住す……
『雨降りてその音恰も律に調へり。……我此處に第二人者なくして住す……』(『長老偈』五一‐五四)
しかし同じ雨といつても印度の雨は日本や支那のそれとは違つて、降り方が至つて猛烈である。細雨又は微雨といふやうなものは少い。多くは急雨強雨猛雨である。外には斯うして烈しい雨が降りしきり強い風が吹きすさんで居るのに家の中にある比丘は静に禪想に耽つて居るといふ、この著しい對照を詩に示したものが『長老偈』中には澤山ある。その一をあぐれば、
『我が屋舍は葺かれ、風を防ぎて樂しし。天思のままに雨を降せ、我が心は善定に住し離脱したり、我は專心にして住す、されば天雨を降せ』(一)
雨もその音が律に調うて居る間は詩味もあるといへようが、その勢が少し募ると強雨となり、それに風が加はつて暴風雨となり、或は更に雷電までも加はつて雷雨となり出すと、詩味も何もあつたものではない。唯凄い恐ろしいものとなつて來る。
『雨降り、雷鳴り、我は獨り恐ろしき凹地に住す、此の獨り凹地の中に住せる我に怖畏なく驚悸なく、身毛竪立するなし。』
『我が獨り恐ろしき凹地に住して怖畏なく、驚悸なく、身毛竪立することなき、これ我が性なり。』(一八九、一九〇)
『大地は雨に注がれ風吹き雷は空に走る。我が疑惑は止息し。我が心はよく定に住せり。』(五〇)
『雷は毘婆羅山と槃荼婆山の岩窟に墜つ、斯の比倫なき佛の兒は山窟に入りて禪思す。』(四一、一一六七)
『空中に雲鼓響き鳥路に四方より豪雨來る。比丘はまた山窟に入りてぞ禪思する。この時人はこれに優れる樂を得ることなし。』(五二二)
斯うして荒れすさぶ風雨の音を聞き、物凄き雷の光を浴びながら泰然として晏坐し禪心を練るのも彼等に取りては修養の一方法であつたらうし、彼等はこの中に他の人人の味ひ得ざる一種の禪樂を見出し得たことと思ふ。
しかし自然との眞實の接觸は主觀客觀共に平和の状態にある時でなくてはならぬ。
『碧雲の色ありて美はしく冷にして清き水を湛へ、インダゴーパカ虫に掩はれたる、こり等の岩山は我をして樂しましむ。』(一三、一〇六三)
前の強雨暴風又は雷雨を記せる偈に比して何たる静かな叙景の詩であらう。山の上に碧色の冷たく清んだ水の池があつて、その山はまた一面にインダゴーパカ虫のために掩はれて居る。インダゴーパカとは因陀羅即ち帝釋天の牛群を保護するものといひ、或はまた帝釋天に保護されるものともいふ意。臙脂虫、赤色の甲虫、又は螢と註してある雨後夥しく出る虫の一種とあるから、これは雨後の叙景なることを思はしめる。景色に對しては印度人は支那人日本人とはよほど違つて居るものであるが、この詩に見るが如き景趣は吾吾の感情にも訴へぬこともなからう。池と山とは必ずなくてはならぬものか、二長老の
『清みたる水あり、大なる磐石あり、黑面猿と鹿と群り、水草セーバーラに覆はる、これ等の岩山は我をして樂しましむ。』(一一三、六〇一)
と歌つたものがある。樹林に關する偈は『長老偈』中には至つて少い。ウサバ長老は、
『樹は新に喜雨を濺がれて山嶺に繁茂す、遠離を欲し、念を森林に掛けるウサバにはますます善事來る。』(一一〇)
といつた。迦留陀夷(カールダーイ)長老は佛の父なる淨飯王より佛をその郷里なる迦毘羅衛城へ誘ひ來るべき使命を帶びて竹林精舍へ來て留つて居た。彼はひさしくその時機の來るを待つて居たが、パッグナ月‐今の陽暦二月の末‐になつて時候も追追心地よくなり、佛が郷里を訪ひたまふべき時機も到來したことを知つて彼は次なる偈を誦した。
『大徳尊、葉を捨て果を求むるこれ等の樹樹は今や紅色となり、火焔の如く光り輝く。大雄尊、今は法味を分ちたまふべき時なり、
『樹と花とは愛すべく、四方普く葉を捨て果を求めて香気を吹き來る、雄尊、これより出立ちたまふべき時なり、
『寒きに過ぎず、暑きに過ぎず、大徳尊、今や樂しき時節の中にあり、釋迦族民と拘利族民と、尊の西に向ひてローヒニー河を渡らせたまふを見たてまつらんことを。』(五二七‐五二九)
これとは意味は稍稍違ふやうだが、やはり優陀夷(ウダーイ、迦留陀夷(カールダーイ)とは黑き優陀夷の意)が佛に入郷を勸むる時の偈とされて居るもので、『佛本行集經』五十一卷に左の數句がある、
『譬如非時諸樹木 欲著花果待其時 非時花果無光麗 尊今可渡恒伽河 樹木紛葩花正開 其花香遍十方刹 花既開敷結果實 尊向生地正是時 此時最妙最爲勝 清流香潔泉池水 百鳥林中出好響 諸欣悦事是其時』
後者の洗練され文飾されたる點は前者の粗朴にして而も率直なる點と比して到底同日に論ぜらるべきものではない。これ一分はこれを譯した人の修辞の結果であらうかと思ふ。
禪僧に取つては自然は一切である。彼等に精神的の糧を供するものとしては生きた教師も無用であり、黄卷赤軸も亦無用である。自然は彼等に向つて微妙の法門を説いてくれるし無上の大法輪を轉じてくれる。單に自然といへば吾吾は山川風物、水鳥樹林といふやうな多少審美的鑑賞の値あるもののみを思ふのが常であるが、禪僧の教師としての自然はもつともつと廣い。審美價といつては全然持合せない燈籠でも露柱でも、麻でも米でも、牆壁瓦礫でも唯『物』でさへあればよい。或は形あつて眼に見られるものばかりではない、音でも香でも味でも宜しからう。隨つて谿聲は廣大長舌となり、山色は清淨法身となる。佛ともなれば法ともなる。『一色一香無非中道』と『法華經』にいへる語は禪僧の接した自然界の事事物物に就ていへるものとも見ることが出來る。凡そ事物は禪僧の眼に映じた時ほど高價なことはない。撃竹も桃花も聽く耳を有ち視る眼を有つて人にはそれが常恒不斷に説法をして居るわけだが、悲しむべし吾吾凡夫はそれを聞き又は見ることが出來ぬのは、唯唯禪的機智の缺けて居るがためで、いはば天津橋上に杜宇の聲を聞いても天下の大に亂れんとするを察することが出來ず、林檎の落つるのを見ても地球に引力あることを察することの出來ぬのと同一徹である。單にそればかりではない、即ち禪僧は自然を師としてそれより教を受けるばかりではない、彼等は自然に同化し、自然と冥合して一枚となることができる。つまりその教ふる所の汎神説を自然の上に體驗するのである。禪僧に取りては自然は斯うして深秘的な幽玄な而して廣大無邊な意義を有てるものである。
一方原始僧はといへば、彼等は自然を自然と見てこれを友とした、それに親しみを感じた、又自然に詩味を見出した。自然の與ふるインスピレーションに動かされて、彼等がその修養に進境を得、人格の向上に大なる助けを得たこともあるであらう。しかし自然の示す禪味を味はうたり、自然の語る説法を聞いたりするだけの力量は彼等は有たなかつた。况んや自然と冥合するなどといふことは彼等の夢想だにもなし得ざりし所であらう。
原始佛教時代の出家の佛弟子は皆阿羅漢になることを目標として進んだ。迷を捨てて悟を獲る、迷を轉じて悟を開く、惑を斷じて理を證る。これが原始佛教の教ふる佛道修業の終局の目的であり、同樣に又最上善であつた。而してこの目的を果すに就て取るべき秩序ある道は何であるかといへば、それは所謂四向四果の八階級である。今少しく詳しく言うと、『雜阿含』一五卷の二九經によれば第一預流向に於て、身見、疑、戒禁取の三結を除いて初果に入り、次にこれ等三結を除くの外、貪、瞋、癡の三毒を薄くして第二果に入る。それから有身見、疑、戒禁取、欲界繋の貪及び瞋恚の五下分結といふものを斷じ盡して第三果に入り、最後には貪瞋癡の三毒は勿論のこと、煩惱といふ煩惱をば總て斷じ盡し『現法中に於て自ら知り、自ら覺り、自ら作證し、成就して遊ぶ。生已に盡き、梵行已に立ち、所作已に辯じ、更に有を受けず、如眞を知る。』これが第四果即ち阿羅漢果に達した人たちの境界で、斯うなると佛道修行の目的は完全に果されたといふことになる。これを梵行者の階梯と呼ぶが、この八級の階梯を經て羅漢果を獲ようとするには、在家の生活を營んで居てはこれを果すことが出來ない。それにはやはり出家生活を營むの必要がある。中阿含の『迦⑧那經』に
『我我時に於て少しの財物及び多くの財物を捨て、少しの親族及び多くの親族を捨て、鬚髪を剃除し、袈裟衣を著け、至信に家を捨て家なくして學道す』
といつてあるやうに、家族生活を捨て出家沙門の身となり沙彌としては十戒、比丘としては二百五十戒を持ち、四無量心、十不淨觀、十遍處、十念、四禪四無色定などを觀念し、四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七等覺支、八正道の三十七菩提分法(又はこれを三十七助道品とも呼ぶ)を修行し、四向四果を經て阿羅漢果に達するといふのが順序である。彼等は斯うして修行し、斯うして悟を開くことを得たものであつた。
しかし修行者は總て斯ういふ順序を經て悟に辿りつくものであるかと、いうと必ずしもさうでない。佛在世の佛弟子たちは四向四果の階級を踏まず、佛から四諦の教を聽いた刹那に悟を開いた人が多いやうである。鹿野苑の初轉法輪の座で悟を開いた⑤陳如を初め他の佛弟子たちは法門を聽き終ると同時に即座に悟を開いた。『雜阿含』一五卷の一五經には
『爾時世尊、是の法を説く時、尊者⑤陳如及び八萬の諸天、塵を遠ざけ、垢を離れ、法淨眼を得』
といつてある。塵を遠ざけ垢を離るとは煩惱を斷ずること、捨てること、又はそれより離れることであり、法淨眼を得とは悟を開くことを指すものである。即ち斯うして佛の説法を聽いて即時に悟を開いたもので、四向四果の階級を經て順次に上つて行くといふやうな面倒はなかつた。前の階級を經て得る悟が漸悟であるといへたら、これは頓悟であるといへよう。佛時代の弟子たちは多くこの流の悟り方をしたもので『法淨眼を得』といふ文字は到る所に見出される。
但この『法淨眼を得』といふことは必ずしも羅漢果に達したことを指せるものでもないらしい。それは此處で法淨眼を得た⑤陳如以下五人の比丘は何れも世尊に對して出家を求め、後世尊が無常無我苦の三特相に就て法門を説かれると、彼等は佛の所説を悦んで受け入れ、その心は取著なくして諸漏より解脱したといつてあるからである。この取著なくして諸漏より解脱したといふ時が正しく悟を開いて阿羅漢となつた時であらう。
五人の比丘に續いて出家となつた耶舍(ヤシャ)に就ても、遠塵離垢得法淨眼の文字を使つてある(『大品』一の七の六)が、これもこの時彼はまだ在家人であつた。但耶舍はまだ出家しない中にその心を諸漏より解脱せしめたといつてあるが、これは同人が再び還俗して昔時在家人たりし時のやうに諸欲を享けることがない程十分下地が出來て居たからである。つまり耶舍が出家をすることは既定の事實であつた。この時の耶舍は出家も同然であつたのである。それで彼の事を得法淨眼といつたのだと解することも出來る。然るに耶舍の父母及び舊妻は出家はしなかつたがやはり遠塵離垢得法淨眼といはれて居る。それで得法淨眼は必ずしも羅漢果を得たことを指すものではない。後佛は象頭山に於て摩掲陀國の頻毘沙羅王に會せられたが、『過去現在因果經』四卷にはこの時座にあつた十二萬の摩掲陀國の婆羅門居士等は佛の法門を説かれるのを聞いて皆塵を遠ざけ垢を離れて法淨眼を得たといつてある。而して又『雜阿含』三二卷の九經に掲曇聚落主(ガンダガタ)は『塵を遠ざけ垢を離れ法淨眼を得、法を見、深く法に入つた』と云つてあるが、この文を見ると、聚落主はこの時悟を開いて阿羅漢となつたやうに思はれるが、彼は『我今日より佛に歸し、法に歸し、比丘僧に歸し、其の壽命を盡すまで優婆塞とならん。唯我を憶持せよ』といつて優婆塞となつただけである。比丘にもならないし、羅漢果を獲たわけでは勿論ない。これで以て得法淨眼の常に開悟を意味するものでないことが判らうかと思ふ。要するに私が此處で言はんと欲することは阿羅漢の悟は必ずしも四向四果の階級を通過せず法門を聞くと同時に得られた例の至つて多いこと、それから得法淨眼は常に必ずしも得阿羅漢果の意味ではないといふことである。
在家の生活を營めるもので羅漢となれるであらうかというと、それは不可能のやうである。これに就ては色色經説上の證據を擧げることが出來るが、先づ第一手近にあるものから擧げて見ると『雜阿含』二〇卷の一八經(同一四經參照)には世尊の弟子中の出家と在家とを明かに區別して前者は隨順行を行うて四向四果を得べく、後者は戒を持ち、施を行ひ、天を念じ、死後はその果報として自分が念じた天界に生れ出ると斯ういうてある。この經は摩訶迦旃延長老と訶梨聚落主長者との問答となつて居るが、終り頃に長者が『我常に念佛の功徳、念法念僧念戒念施念天を修習すべし』というと、長老は『善い哉長者、能く自ら記説し阿那含を得よ』といつた。同經三三卷の一〇經、三二卷の一四經にも優婆塞の阿那含果まで成じ得ることが記してある。同四四卷一六經には佛が大梵天王に阿那含果を得ることを記別せられたといつてある。大梵天王でも未出家の身であるから出家者には一歩を讓るものとされて居る點は頗る興味あることと思ふ。しかし阿那含は第三果のことで、この位は第四の阿羅漢果に比すれば唯一位不足なるだけである。且つこれは不還果といつてこの果に達したものは再び欲界に還ることなくして阿羅漢果を成ずるものとされて居る。されば不還果に達したものは必ず阿羅漢果にも達する。在家の人が不還果まで達することを得と許されるのは阿羅漢果に達し得と許されるも同然で、事實上在家と出家との區別はない、兩方とも阿羅漢になれる、と斯ういふ人もあるのである。
しかしこの經(二〇卷一八經)には在家のものが阿羅漢果を成じ得とはいつてなく、唯率直にいつてあるのは四王天、三十三天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天を念ずると死後はその人が念じた天上の世界に生れ出ることを得といふだけである。斯うして原始佛教では在家道と出家道とは画然と區別されて居ると見るのが最も正しい見方であると私は信じて居る。なるほど巴利文『小品』六の九に佛は給孤獨長者が祇園精舍を供養したことを稱揚して
『彼らはこの人のためにあらゆる苦痛を除くべき法を説き、彼はこの處にこの方を知り無漏にして涅槃に入らん』
といはれ、『諸經要集』二六七には
『苦行と梵行とあり。聖諦を見、涅槃を證知する、これ最上の吉祥なり』
といつてある。(この偈の漢譯は『法句經』卷下吉祥品の
『持齋修梵行、常欲見賢聖、依附明智者、是爲最吉祥』
にあたるが、この偈の中に『涅槃を證知する』の文を見出し得ざるは遺憾である)。これは共に在家の人に就ていつたのであるが、しかしまた巴利文中阿含經(一卷の四八三頁)『Maha-vacchagotta-sutta』(大跋蹉姓經)には
『ヴァッチャよ、如何なる在家者と雖も、在家の繋縛を棄てずしては身壞の後苦際を盡すものこれあるなし』
といつてある。私は原始佛教の正しい見方からすればこの在家の生活を棄てないものは涅槃に入ることが出來ないと言ふのが本當であると思うて居る。つまり上に引いた『雜阿含』その他處處の經文に見るやうに在家の生活を營むものは四果中の三果まではこれに達することを得るが、第四の阿羅漢果はこれに達することが出來ない。それは唯家を捨てて出家した出家者にのみ約せられる所の特權である。高祖は正法眼藏の『菩提分法卷』に
『おほよそ佛法東漸よりこのかた、出家人の得道は稻麻竹葦のごとし、在家ながら得道せるもの一人もいまだあらず』
といはれ『出家卷』、『出家功徳卷』には『大論』より
『出家の破戒は猶ほ在家の持戒に勝れり』
の語を引き、更に『菩提分法卷』には
『出家人の破戒不修なるは得道す、在家人の得道いまだあらず』
といつて、一には在家生活と出家生活との優劣を比較し、二には極度に出家生活を讚歎される。これ全く原始佛教家の口吻である。
原始佛教に現はれた菩薩は大體これを二つに分類することが出來る。一は釋尊なり他の佛なりがまだ佛果を得られない前の身を指せるもので、一はそれを更に引延ばして單に現身の佛果成就前の佛ばかりでなく、前なる生生の佛をも指すものである。『阿含文學』中に現はれる菩薩は總て前者で、 後者は『本生文學』の中に入つて初めて現はれる。一括して『阿含文學』といつたが、此處に注意を要するのは『增一阿含』である。それはその序品中にも彌勒、大乘、菩薩、六度、三乘などの如き非原始佛教的の言句の雜れるに徴しても解る通り、よほど大乘化された點があるやうである。これ等の點を除けば他の阿含と同樣に見ることは勿論妨げるものではない。
菩薩は詳しくは菩提薩⑨Bodhisattaで、菩提は覺であり、薩⑨は有情であるから、通常これを覺有情と譯し、「上諸佛に對しては覺を求め、下有情に對しては化を埀れる」と解するのが常である。この語に就てはいろいろの解釋を下すことが可能であるが、『枳橘易土集』に引ける『華嚴疏鈔』一下の『菩提薩⑨』の三釋は最も要領を得た解釋であると思ふから、それを此處に引くこととする。三種の解釋とは先づ
『(一)には菩提とは所求の佛果、薩⑨は所化の衆生、即ち悲智所縁の境、境に隨つて名を立つ。故に菩薩と名く』
といつてある。これは菩薩に對する通常の解釋として上に擧げたものに當るかと思ふ。即ち菩薩は一方に於ては佛果菩提即ち覺を求め、一方に於ては衆生即ち有情を教化する。上求菩提下化衆生である。それで覺有情といふ。次に
『(二)には菩提はこれ所求の果、薩⑨はこれ能求の人、能所合目、故に菩薩と名く』
といつてある。この解釋によれば菩薩は覺有情即ち菩提の覺を求める有情である。教化すべき有情があるか否かはまだ眼中にない。單に菩提を求尋する人である。求菩提人である。羅漢果とても菩提である。隨つて羅漢果を求めるものでも菩提人である譯だが、佛果は特に菩提である。それで佛果を求める人を特に菩提人と呼ぶのであらう。終りに
『(三)には薩⑨は此に勇猛といふ、謂く大菩提に於て勇猛に求むるが故に』
とある。これはSattaに『力、勢、豪勇』などの意味の含まれて居るより引き出した解釋で、若しこの種の解釋が可能であるとすれば、まだ他に幾多のこれに類した解釋の仕方が出てくるであらうと思ふ。しかしこれよりも興味あり、且つ菩薩の性質から推して意味のある解釋と思はれるのは第一第二の兩種の解釋である。即ち上求菩提下化薩⑨と、求菩提の薩⑨との二であるが、私はこの二の中、二が根本的で、一はこの菩薩思想の大分發達してから出て來た解釋であらうと思ふ。即ち本來の菩薩は菩提を求むるだけの人で、他の有情を教化することを念としなかつた。少くもその尋求菩提の間は教化衆生の意はなかつた。隨つて構成の佛教家がこれに與ふるやうな一切衆生を教化し盡さぬ間は誓つて正覺を取らずとか自未得度先度他といふやうな切なる教化心はなく、單に求菩提の心のみがあつた。其處へ利他の思想がよほど加はつて來て、菩薩の全目的は唯利他であるかのやうに説かれるやうになつた。これは勿論大乘家が加へた菩薩の意義であり、且つその實行道である。通常呼ぶ所の菩薩道又は菩薩の行願とは即ちこれである。
上に既に述べた通り、菩薩は第一には釋尊なり他の佛なりで、現身に菩提を求めて居られる間の名稱であつた。巴利阿含文學に見ゆる菩薩は大方この意味のものである。此處に『巴利文の阿含』と特に一言を加へたのは漢譯阿含には『菩薩』の語をこの意味に用ひてあるのは見當らないからである。即ち巴利中阿含Ariyapariyesana-suttaには
『比丘等よ、余も亦正菩提の前、未正覺の菩薩にして云云』
とあるが、その譯本たる漢文『羅摩經』には單に
『我本未覺無上正盡覺時』
とあり、巴利文『雜阿含』三六の二四には
『毘婆尸世尊應求正偏智者は正菩提の前、未成正覺の菩薩にして云云』
とあるが、漢文『雜阿含』一六卷の二〇經には
『毘婆尸佛未成正覺時』
とある。斯うして中雜兩阿とも菩薩の文字を除いてある。初めはこの今生一世現身の佛が菩提を求めながら未だそれを成ぜざる間を稱して菩薩といつたのであつたが、それが第二には啻に現身ばかりでなく、遠き過去の世に現はれ‐釋尊が四阿僧祇十萬劫の昔、善慧(スメーダ)行者として燃燈佛(ヂーパンカラ)の座下でされたやうに‐未來成佛の誓願を起して以來、一生補處の身として兜率天に生れ出で、次にその成佛の誓願を果さんがため人間として生れ出るまでの間の幾多生生の身をも菩薩と稱せられるやうになつた。これが巴利文『本生物語』五百四十七篇の本文及び註釋書中に現はれた菩薩思想であらう。余は此處に一括して『本文及び註釋書』といつたが、この兩文學中には菩薩は(一)もと單に古き物語の主人公であつたものが(二)佛教の菩薩となり、それが(三)釋尊の前生と結びつけられて、その過去生生の身となつたと、斯う三段の發達をして居ると云はねばならぬと思ふ。
『本生物語』に現はれた菩薩の地位は至つて卑い。これは第一在家人即ち俗人で、出家の身である阿羅漢又は阿羅漢果を目的として進める比丘たちに比すればその地位は至つて卑い。吾人大乘家は菩薩を阿羅漢の上に置いて、菩薩の前では阿羅漢は共に齒ひすることを許されざるほど下劣な根性の持主として、これを貶すのが常であるが、原始佛教ではさうではなくして、その地位は全然顛倒して居た。義淨三藏の『南海寄歸傳』の中に
『若し菩薩を禮し、大乘經を讀めば之を名けて大と爲す。斯の事を行はざれば之を號して小と爲す。』
といつてある通り、小乘の比丘は菩薩は未出家の身としてこれを拜することを肯じなかつた。即ち菩薩の地位は羅漢又は羅漢果を求むる人人のそれに比しては遙に卑かつたのである。『本生物語』の中では慈悲喜捨の四梵住を修し、梵天の世界に生れることを菩薩の最上の成效として描き出してあることが往往ある。菩薩は世間の人、阿羅漢は出世間の人である。今日の語を以て云へば菩薩はまだ道徳界の人で善惡正邪の差別ある境界の外に脱出することを得ざる人であるが、羅漢は超脱の宗教界の人で、既に道徳の差別を脱出して涅槃の無差別界に入れるひとである(第五章參照)。佛教の修養は道徳界より宗教界に入るが順序である。されば宗教界にある人が道徳界にある人よりも高き地位に居るとされるのは素より當然のことでなければならない。
所が此處にこの菩薩思想に一轉化が起つた。それは釋尊又は他の佛の經歴の上でも察し得られる通り、菩薩は將來(又は遠き未來世には)佛となれる可能性を有つて居るといふがためで、一方には菩薩は佛となれる資格があり、自他二利の念の中、特に利他の念、即ち自未得度先度他の切なる念願を有つて居るのに、一方の羅漢は唯自利、或は利他心はありとしても菩薩ほど強き利他心は有たない(とされて居る)。斯ういふ事情から一は慕はれ一は疎んぜられ、一はその地位を高められ一はその地位を低くされて大乘佛教で見るやうな兩者の地位の顛倒となつて了つた。大乘に入つてからの菩薩は道徳宗教は勿論、文學藝術その他あらゆるものの主題として取扱はれ‐これは巴利佛教でも或程度までは勿論さうであつたが‐單に修養の上からいつても、生活全般の上からいつても殆ど佛者の理想と見られるに至つた。斯うなると菩薩は後佛となれる人であるから尊いといふのではなくしてやはり獨立した一人格者として尊いのである。
羅漢にも利他心はある。『雜阿含』四卷の七經には
『是故に比丘當に自利利他を觀すべし、自他倶に利し、精勤修學すべし』
といひ、『衆許摩訶帝經』八卷には
『是時(耶舍の父なる)長者は耶舍の出家の形となれるを見、復漏盡きて無學果を證せるを知り、乃ち是の言を作す。我が子快なる哉、初めてよく自ら利し、又能く他を利す。我をして殊妙の法を聞くことを得しむ』
といつてある。巴利文『增一阿含』二卷九五經には唯自利、唯利他、自他倶不利、自他倶利の四種の中、最後の自他倶利即ち自利利他併せ行ふを最上となすといつてある。
『本行集經』三十七品下によれば鹿野苑初説法の時佛は五人群の比丘のため先づ苦樂の二邊を離るべきことを説かれたが、苦の捨つべきことを説き明す場合に佛は
『第二の捨とは自身を困め、苦を受くるは聖の歎ずる所に非ず、自利を得ず、利他を得ず、この法須く捨つべし』
といはれたとある。羅漢に利他心のあるは素より論なきことで、唯自利と利他とを以て小乘と大乘とを區別せんとするは大なる誤りであると云はねばならない。但強ひて差別をつけるとすれば羅漢は專ら法施を行ふ、隨つてその利他は主として精神的であり、菩薩の利他は多くは物質的の財施である。羅漢が慈悲喜捨の四無量心を修行し、菩薩が布施愛語利行同事の四攝法を修するは大體この差別を示して居る。即ち羅漢道では慈悲は一種の觀念と見られて居るが、菩薩道ではそれは實行の上に示されなくてはならぬ。それは沙門婆羅門、貧窮困苦、行路乞者に衣服飮食錢財帛穀花香嚴具床臥燈明の類を施すことである。鳥獸の類でさへ菩薩の利他心には漏されなかつた。『增一阿含』四卷一五經によれば給孤獨長者が曾て佛に向ひ、野獸飛鳥猪狗の屬に食を施すことは如何でせうかと問うと、佛はこれを稱揚し、
『長者よ、汝乃ち菩薩心を以て專精意を一にし、而して廣く惠施せよ』
といはれたとある。菩薩道では斯うして慈愛を實際に示さなくてはならぬ。英語のチャリチーなる語は初めは『隣人の愛』の意であつたが、今は多く『慈善』の意を有する語として知られて居る。羅漢の利他は前者に類し、菩薩の利他は後者に類しはしまいか。これは勿論主として未發達の佛教中の羅漢と菩薩との比較であるが、兩者のこの特異の性格は後世發達の佛教の中でもよほどまだ保持されて居るかと思へる。或は後世發達の大乘佛教では菩薩は原始佛教時代の羅漢菩薩の兩者の有した理想實際兩方面の利他心を併せ有し利他人としては何れの方面から見ても完全圓滿の性格を有たされるやうになつたといつて宜からう。
禪宗は羅漢道菩薩道、何れを取つて居るか。これは頗る興味ある問題である。吾人は上の戒學を論じた場合(第八章)に禪宗の小乘戒を見る見方に二種ある、一は『禪戒鈔』などのやうに小乘戒を貶しつける方で、一は支那及び日本の清規家のやうに必ずしも小乘戒を排斥しない方であることをいつた。前者では『聲聞ノ持戒ハ菩薩ノ破戒ナリ』といひ、『オロカナル族ハ五戒十善二百五十戒等ヲ受持スル小乘ノ行人アレバ此名相ノ砂石ヲ以テ一句ノ聞法ヨリ功徳多シト思ヘリ』といつて、徹頭徹尾小乘戒及び小乘の行人を排斥し、一方には菩薩道及び菩薩の大戒を高揚した。然るに支那の百丈懷海禪師初め日本の吾が高祖に至るまで、清規派と稱せられるべきものは一方には菩薩戒を用ひながら、一方には小乘戒をも必ずしも排斥しない。『禪苑清規』の
『既受聲聞戒、應受菩薩戒』
といふ文は正法眼藏の『受戒卷』に引かれ、同書の
『毘尼を嚴淨するを以て方に能く三界に洪範たり。然れば即ち參禪問道戒律を先となす』
の文は『受戒卷』、『出家卷』及び榮西禪師の『興禪護國論』にも引いてある。斯うしてこの一派は小乘道必ずしも捨つべしとはなさない。即ち此處には羅漢道菩薩道竝び行はれて居るわけである。吾吾は好んで菩薩戒菩薩道の文字を用ふるが、高祖あたりの見識によればこれ等は素より可として聲聞戒羅漢道をも同じやうに認められるといふことになる。
次に禪宗流通の跡についても穿鑿すべき必要がある。語を換へて言へば支那日本の禪宗僧侶は羅漢道菩薩道の中何れを多く踏み來つたかといふことである。私は彼等は大體羅漢道を踏んで來たといはねばならぬかと思ふ。それは如何いふ理由であるかといふと、先づ第一に支那日本の禪宗は出世間的である。山林の宗教、道院の宗教、僧侶の宗教であつて村落世間俗間の宗教ではない。吾吾は原始佛教も禪宗も共に實行の宗教であるといふ(第十六章參照)が、この實行たるや原始佛教禪宗何れにしても大體からいへば共に坐禪又は觀念によりて悟を開くことといふ實行で、慈愛の心を實際の事實即ち布施や利行の形に示すことではなかつた。勿論多數の禪宗僧侶の中にはこの具體的の利他行、『船を置き橋を渡す』ようなことを行うたものもないではないが、その數は至つて少い。尚又在家の人で禪門大徳の爐鞴に投じ、鉗鎚を受けて自己本來の面目を打開したものも多少はあつたであらう。しかしそれも極少數で、大體からいへば支那日本の禪宗は僧侶が僧侶を教へることを主として來た。
一體僧侶の本面目は法施を行ふこと、即ち法を説いて衆生を度することであるか、それとも財施即ち物質的の施を行ふこと、今日の所謂慈善事業社會事業のやうなことを行ふことであるかは問題である。原始佛教時代の僧侶は慈善事業社會事業の如きことは絶えて行はず、唯法施一點張出厚田。今日では慈善事業社會事業は僧侶としては當然行はねばならぬことと思はれて居るやうであるが、これ果して僧侶の本面目であるか否かは疑問であらう。若し僧侶のこれを行ふことが肯定されるとすれば、それは出世間の僧侶としてではなく、在家の菩薩としてであらう。斯ういふ意味では僧侶のこれを行ふことは勿論妨ぐる所はない。妨げない所ではない、是非とも行はねばならぬことであらう。しかし僧侶としての僧侶の本面目は法施を行ふこと、即ち人のために法を説くことでなくてはならぬ。要するに支那日本の禪宗僧侶は在家の人も教へて來たであらう。しかし大體からいへばその教は僧侶間に限られて居た。又物質的利他行も行うたであらう。しかし大體からいへばその施せるものは精神的の法施であつた。即ちこの二の意味からして禪宗は主として羅漢道を取つて來たといはねばならぬかと思ふ。即ち理想の上では菩薩の大道を標榜して居ながら、實際取つて來た道は羅漢道であつたのである。
私は第十章に巴利文『大般涅槃經』の文を引いて、佛が入滅の少し前阿難陀長老のため種々の法を説かれた中に、佛自身入滅した後比丘は各各自己を燈明歸依所とし、法を燈明歸依所とし他を燈明歸依所としてはならぬと誡められたといつた。其處では私は肉身の佛は入滅して世に亡きものとなられるが、佛の説かれた法と律、即ち一代の言教は比丘や信者の記憶の中に留まるべきものであるから、佛亡き後の佛教徒たるものは、これを佛の口から聞くと同樣に心得て、これを燈明とし、歸依所としなければならぬ。それで佛は法燈明法歸依所といはれたのである。比丘自身を燈明とし歸依所とせよといふのは比丘は三寶の隨一として佛に倣うて修行するもの、佛の依られた道に依つて進み、佛の獲られた悟と同じ悟を獲んと努力するものであるから、いはば一一一人の佛である。それで佛は自分が涅槃に入つた後は比丘は各各自己を燈明とし歸依所としなければならぬ意を述べられたものと解して置いた。これは現前三寶の中現身の佛寶だけはなくなるが、法僧の二寶だけは後に殘る意を力説したものと見たのであつた。これと同一の文句は『雜阿含』には(一)二卷四經(二)二四卷三四經、(三)同卷三五經の三箇所に出て居るが、(一)は『大般涅槃經』の場合と同じく、佛自身の入滅に連關して、(二)は舍利弗目連兩長老の入滅に連關して説かれたものであることより察すると、これはまた勿論自力主義を高調せるものと見ることが出來よう。舍利弗目連の二大長老は佛自身も
『我が聲聞、唯此の二人よく説法教誡教授辯説滿足せり、(世に)二種の財あり、錢財及び法財なり、錢財は世人より求め、法財は舍利弗大目⑦連より求む、如來既に施財及び法財より離る』
といつて、その死を惜まれたのに徴しても解る通り、佛に取つてはその雙腕の如きものであつた。それが相踵いで而も佛に先つて亡くなつたのであるから佛の惜まれるのも無理はなからう。さて『大般涅槃經』及び(一)の場合のやうに佛自身の入滅される時は勿論、(二)及び(三)の場合のやうに舍利弗目連の如き佛の高弟が入滅して見ると、比丘は燈明を失ひ歸依所を失ふことは云ふまでもないから、佛はこれ等の場合特に彼等を教誡して一方自己を燈明とし歸依所とし、一方は遺教を燈明とし歸依所とすべきことを教へられた。これは自己燈法燈、自己歸依法歸依と、自己と法とを對立せしめた邊からは法僧二寶の對照を明かにするものであるが、これが佛自身竝に舍利弗目連の入滅に關連して説かれた所を見るとこれはまた自力救濟、即ち比丘各個が師や兄長老の力を賴らず自己の力を以て自己を救ふべきの意を高調したものであることは明白である。斯うして私はこの數箇所に現はれて居る同一文句より推して原始佛敎の自力教なることを斷定してよいと信ずるものである。
これに連關して私は聲聞の意義とその立場とを明にして置くべき必要があると思ふ。
聲聞といふ語は佛教徒間には偏く知られて居る所であるが、動もすればこは賤むべき厭ふべき人人の類を指す語として記憶されて居る。聲聞根性といへば他人を利することを知らない利己一邊の閑道人の我利我利心を意味するやうに解せられて居るが、聲聞の自利一邊の人でないことは原始佛教を少しく研究した人の容易く了解し得る所である(第十三章)。
聲聞(Savaka)とは本來『聽聞者』の意を含める語で、今日の言葉でいへば弟子又は門人の意である。『雜阿含』二四卷八經に『如來四種聲聞』の語あるは佛の四種の弟子、即ち比丘比丘尼、優婆塞優婆夷を指せるものである。佛典中には斯うして佛の直弟子を聲聞と呼び、外道各派の隨徒をも同じく聲聞と呼んである。師の教を聽くものの意で、師の許にあつて師の教を受くるものは佛教徒たると外道たるとを問はず皆聲聞である。佛の直弟子を聖聲聞Ariya-savaka又は佛弟子Buddha-savakaと呼びたるに對し、外道の隨徒を外道聲聞Titthiya-savaka、Annatitthiy-savakaと呼んだ。繰返していふが聲聞といふ語には自利一方の佛徒といふが如き意味は少しも含まれて居らない。且つこれは佛教徒專用の語でもなくして婆羅門教徒又は他の外道の間にも用ひられた語である。
一體印度は昔から傳統を重んずる國だけあつて師資相承Acariya-paramparaといふやうな事は古來極めて重く見られて居た。隨つて教師、弟子、教徒又は聖典などを表はす言葉にはこの關係を示す語が非常に多いのである。例之、和尚は梵語ではUpadhyaya巴利語ではUpajjhaya又はUpajjhaであるが、これはUpa+adhi+iから出來たもので『近く傍に於て學ばしむるもの』の意と解してある。即ち弟子を自分の傍近く置いてヴェーダ以下の聖經賢傳を學ばしむる人の謂である。これがこの語本來の意義であつたが佛教でもそれをそのまま採用して弟子に對して和尚といふ語を用ひた。而してこの語に對する弟子を表はす語はSaddhiviharika『共に住するもの』である。和尚と共に住する人の意味であらう。師の家に止住してその教を受くる意味であらう。師の家に止住してその教を受くる人の謂である。師の意を表はす語で、今一つ阿闍梨Acariyaといふのがある。これは『行』に關する意味の語であるから、その行を以て人の師となるものの意であらう。或は『アーパスタンバ』一の一三や『マヌ』二の六九に解してあるやうに、こはa+ci『集む、積む』の意の語根から出た語で、弟子が法即ち宗教的義務に關する智識を師から得て、それを蓄積するからだとしてもこの阿闍梨の意に副はぬことはない。この阿闍梨なる師に對する弟子はAntevasinであるが、こは『境界附近に住するもの、近隣に住するもの、師の家に住するもの』の意と解してある。即ち上のSaddiviharikaと略同一義の語である。優婆塞の原語はUpasakaであるが、これはupa+sa『近く坐す、侍坐す』から來た語で、奉事者、崇拜者、教徒、信者の意味である。これを『近事』又は『近宿』と譯してあるによつてもだいたいその意味は察せられよう。或はまた彼のウパニシャッド(Upanisad)といふ語にしても同樣で、これはUpa+ni+sad即ち近く坐す侍坐す對坐すなどの意味ある語根(ルート)プラス前添詞(プレフィクス)から出來た語であるが、つまり教を受けるものが師たる人の近くに坐り、即ちその人に侍坐して受くる教の意で、これは一面にはその教を傳へることが秘密を要し、教の他に漏れることを恐れるの意味から、なるだけ師に接近してその教を受けるの意味もあるが、一面には尊敬の意を表示するため師の近くに坐するの意味もあつた。或はまた婆羅門教で小童が初めて師に就くこと、即ち入門式をUpanayana近く持ち來すことといつた。斯うして教師弟子教徒などの意を表はす語には近く傍にありて教を傳へ、又これを受ける、口から耳へ傳へる、以心傳心とまでは行かぬかも知れぬが、他の媒介を用ひずして直接人から人へ授受するといふ意味の語を常に用ひてある。佛教では出家の原語はPabbajja=pa+vraj(出で行く、自ら放つ)であるが、受戒はUpasampada(近圓戒、具足戒)である。これはupa+sam+padの語根プラス前添詞から出來たもので、本來『近づく、獲る、身に受く』などの意義が含まれて居るから、このウパナヤナと多少縁故のないこともなからうと思ふ。
加之婆羅門教でヴェーダ、ブラーフマナ、ウパニシャッド及びスートラの四を聞經(Isruti)即ち天啓經と呼ぶが、これは聞くこと、聞かれるもの、古昔より聞かれ又は傳へられたるもの、仙士(リシ)が神より聞き傳へたるものの意と解してある。上の四を聞經と呼ぶに對して、マヌ又はヤジニヤヴァルキヤなどの如き法典その他のものを指して傳經(Smriti)と呼ぶ。これは記憶すること、記憶、師の記憶によりて傳へたるもの、傳説の意で共に聽くとか傳へるとか兎に角此處にも面授面稟的の意味が含まれて居る。『聲聞』が弟子の意となるのも全くこれと同じであらう。然るをこの語が何故に唯自利を目的とする佛教徒を意味するものと解されるやうになつたかといふに、上に引いた『雜阿含』の文にもある通り、原始時代では在家出家の別なく、佛弟子を總て『佛の聲聞』と呼んだ。後世の佛教徒は自分たちを彼等より區別せんがため、後者を指して聲聞と呼び、彼等のよれる道を聲聞道、而して彼等の設ける教を聲聞乘と呼んだのであつたが、自利と利他とは後世の佛教徒の解する所に隨へば原始僧と後世僧とを區別する一大要點であるので、この意味が自然に轉じて聲聞は自利を主とする佛教徒の意と解せられるに至つたのである。しかしこの語には本來は唯『聞者』の意味あるのみで、後世の佛教徒が與へたやうな唯自利の輩といふ意味はなかつた(第十三章參照)。而してこの語は單に佛教徒のみならず、婆羅門教徒や耆那教徒の間にも用ひられたものである、寧ろその方が先であつたことを併せ記して置く必要がある。
聲聞を自利の人と解するに就て唯一つ尤もと同意される點がある。それは上に述べた通り、聲聞とは弟子の意である、聲聞はまだ弟子の分際である、自分まだ修行中の弟子の分際であるから、他人のために教を説くことは出來ないと云ふことである。これにはまた舍利弗目連の如きもやはり聲聞‐二人は特に首聲聞(アッガサーバカ)と呼ばれた‐であつたに拘らず、佛に代って法を説いたことがあるといふ矛盾も出て來るが、其處は多數決によるとして、聲聞は弟子である、自身修行者であるから他人のために法を説くといふ意志がないではないが、まだそれが出來ない身分のものと解して置かう。さうすると『雜阿含』三卷一七經に佛に就て言つてある次の文句がよく生きて來ることになる、曰く
『如來應等正覺は未だ曾て法を聞かず、能く自ら法を覺り、無上菩提に通達す、未來世に於て聲聞を開覺し、而もために説法す。』
この文でも判る通り佛は他から法を聽かず、自分獨りで法を覺り、無上菩提を成就する。而して次には聲聞を教へて彼等のために法門を説かれる方である。即ち無師獨悟の人であり、自覺覺他、自利利他の人である。然るに聲聞は師を要して悟を開くから無師獨悟でもなく、且つその多數のものはまだ弟子の身分であつて、利他の經驗がないから、或はその經驗が少いから、唯自利の人と呼ばれる。但し獨覺とは違つて聲聞は利他の意志が全然ないではない。唯その多くは利他を事實に示すべき時機に達せず、その機會を得ざる人たちである。こは聲聞をまだ修行中の弟子の群と解して、大乘家が聲聞を貶す意を釋明して見たものであるが、要するに自利一邊、唯利己の閑道人でないことは勿論いふまでもない。
原始佛教の自力主義は假に(一)倫理的(二)宗教的の二種に分けて見ることが出來よう。自力他力と似た語で自律他律といふ語が倫理學の上に用ひられて居る。この語はカント學派の如き直覺派とミル、ベンザムの如き功利派との間にはその意義が大分違へて用ひられて居るが、此處には功利派の自律他律を説明する必要はないから、しばらくカント派の説に隨ふとすると、自律的道徳生活とは吾吾各個が自己の意志を以て内心に立法したる道徳的法則に從つて生活することをいふので、各個が自己の良心の命によつて自分自らを律して行く道徳的生活である。一方に於て他律的道徳生活とは、必ずしも自己の良心の命令によらず、外にある權威、即ち神の意志(と思はれるもの)、在來の道徳、風俗習慣、父母長上の教訓、言行などを標準として營む道徳的生活をいふのである。勿論人間は生れながらにして自己獨特の道徳法を有つて居るものでもなければ環境、與論、風潮、時勢の如何を顧みずして離れ島のロビンソン・クルーソーのやうな孤獨の生活を行うて行けるものでもない。從つて自律といつても純然たる自律といふものはあり得ない。自律的といふも他律的といふも要するに比較的の言方たるに過ぎないことになる。
倫理としての佛教はその善惡因果説に於いて、善いことをすれば修羅道人間道天上道に生れ、惡いことをすれば地獄道餓鬼道に墜ちるといつたやうに常に未來世に受ける結果に重きを置くからして通常結果論、功利説と解せられて居るやうであるが、佛教の倫理は動機を全然無視するものともいへなからうと思ふ。彼の『法句經』の第一第二の偈文に
『諸法は心に導かれ心に統べられ心に作らる。人若し汚れたる心を以て言ひ又は行はばそれよりして苦の彼に隨ふこと、車輪のこれを挽けるものの跡に隨ふが如し。』
『諸法は心に・・・人若し淨き心を以て言ひ又は行はば、それよりして樂の彼に隨ふこと猶ほ影の形を離れざるが如し』
といつてあるは私は動機を意味するものと見て居る。この偈の旨意は言を發し、或行をなすに先ちてその心を清くすべきことを勸めたものである。『諸惡莫作、衆善奉行、自淨其意、是諸佛教』の偈もこれと併せ考ふべきである。
一方佛教の業感縁起説では一の有情はそれが涅槃に入らざる限り、未來永劫轉生を繼續し、その間に作す所の業の性質に應じて善處又は惡處に生れると説くからして、これは又一種異つた意味の個人説である。それで吾吾が善い事を行うて惡い事を行はないわけは、吾吾が神の面前で義とされんがためでなく、他の人に是認されたり稱讚されたりせんがためでもない。唯自身の力で自己を救はんがため、即ち先づ人間天上の如き善處に生れるやうにするため‐これは主觀的にいへば自己の人格を向上させるため‐次にはこの輪廻界を超えて涅槃の彼岸に至るやうにするためである。而してこの結果は他人の力を以てなし得られるものではなく徹頭徹尾自分の力に待たなければならない。彼の回向即ち功徳の轉向、更に詳しく言へば一人の人が供養や他の善事によつて積んだ功徳を他の人に轉施しそれによつて惡趣の轉生を免れしめるといふ思想は佛教の思想史上大分後になつてから起つたもの(これは巴利佛教にもある)で、原始佛教時代では懺悔の教もなければ方便説もないと同樣、この回向の思想もなかつた。吾吾は自分が蒔いた通りに自分で刈り入れるものであるといふ考は原始佛教ほど徹底的に教へられた所はなかつた。即ちその道徳教の上では原始佛教は極度の自力主義であるといふことになる。
第二の宗教的の自力主義とはいふまでもなく解脱即ち悟を求める上の事で、悟を獲るに就ては無師獨悟の佛でない以上、或程度まで他人の指導を要することは勿論のことであるが、悟そのものは自己の力に依らなければならないし、而してクリスト教や淨土教の如き他力教とは違つてこの悟を開くことが佛道修行の終局の目的であるから、原始佛教は宗教としてもやはり自力主義のものであるといふことになる。
この二の點に就て自力主義を主張することは我が禪宗も同じであらう。禪宗の不昧因果説で因果の法則の必然なること、善因に善果あり、惡因に惡果ありと教ふることは今更説明を要しない。吾人は下(第十五章)に禪宗はその現世主義なる點に於ては三世六道の要はないといふが、これは所謂不落因果の大修行底の人に取つての談で、禪の倫理教の上では三世も六道も因果輪廻、勸善懲惡皆必要である。正法眼藏の『三時業卷』に
『今の世に因果を知らず、業報をあきらめず、三世を知らず、善惡をわきまへざる邪見のともがらには群すべからず』
といへる文を見れば、この意自ら了解されようかと思ふ。
次に禪の宗教的の自力主義はといへばこれは説明するまでもなく、禪宗は自力宗中の自力宗といはれるだけ、この意味を説き明せる語は非常に多いのである。大慧は
『方に信ず、此の一段の因縁は傳ふべからず學すべからず、須く自證自悟自肯自休して方に始めて徹頭すべし』
といひ又
『須く是れ當人自ら見得し自ら悟得し自然にして古人の言句に轉ぜられざるべし』
といつた。或は
『一一自己の胸襟より流出し持ち來り、我がために蓋天蓋地し去れ』
といつた語といひ、
『汝若し自己の面目を返照せば密は却つて汝が邊にあり』
といへる語といひ、唖子の苦瓜を喫するの喩、魚の水を飮んで冷暖自治知するの喩といひ、總てこれ等は禪宗の唯獨自明了余人所不見の教を高調せるものに外なからう。要するに禪宗は倫理的にも宗教的にも共に自力主義なる教であり、而して又通常いはれて居る通り、禪宗ほど極度に自力主義を高調する教もないのである。
原始佛教と禪宗と今一つ共通に有すると思はれることは現世主義である。禪宗といつても現在南部支那及び安南に行はれて居るやうな禪宗ではない。これは禪宗と稱しながら一方には念佛を唱へ未來極樂往生を願ふべきことを教へるもので禪としては極めて不純なものである。これは『參禪の人念念自の本心を究むと雖も而も發願して命終の時極樂に往生せんことを願ふを妨げず』といつた彼の明末の株宏や藕益の流を汲めるもので、禪と念佛とを混淆するものであるから、正系の禪宗としてこれを取扱ふことは素より許されない。正系の禪宗には高祖が『學道用心集』の中に
『或は人をして心外の正覺を求めしめ、或は人をして他土の往生を願はしむ。惑亂此に起り、邪念此を職とす』
といつて指摘して居られるやうに、淨土教の教ふる他土の往生は心外の正覺と同じく惑亂邪念の原となるものとして排斥する。他土の往生といへば主として阿彌陀如來の極樂世界に生れること、尚更に彌勒菩薩の兜率天に生れることも意味していると思はれるが、これ等の外に人天有漏の善業の結果として期待せられる他の天上界への上生‐例には巴利文『本生物語』の中に際際でるやうな、慈悲喜捨の四梵住即ち四無量心を修して梵天の世界に生れるが如き、或は又『雜阿含』三三卷一二經にいへるやうな、
『念佛念法念僧の果報としてこの身は假令火に燒かれ、塚間に棄てられ、風に漂はされ、日に曝され、久しくして塵末となるとも心意識は久遠長夜に正信に薰ぜられ、戒施聞慧薰ぜられ、神識は上昇して安樂處に向ひ未來は天に生れる』
が如き、‐も亦これに含まれて居るものと見て差支へなからう。禪者が極樂や兜率天や他の天上界に生れることを目的とする。斯ういふ目的を以て禪を修するといはば、そは外道禪、世間禪、又は有漏禪として極力排斥さるべきものであらう。勿論三世因果を説き六道輪廻を説く所の佛教の一部である以上、禪にも三世や六道を説かないことはない。しかし吾が禪門の禪の本旨は即心即佛であり、直下承當である。隨つて實際をいへば禪には三世も六道も必要はない。唯現在の一世と人間の一道とあれば足りる。株宏の『竹窓二筆』に
『裴丞相謂ふ、六道の中、以て心慮を整へ菩提に趣くべきもの、唯人道を能となすのみ』
といへる通り、禪は人間一道主義である。黄檗の希運禪師は
『直下に頓に了ずれば三世のために拘繋せられず、便ち是れ出世の人なり』
といはれた。『あるべきやうは』といふ書は世に傳ふるやうに明惠上人の書であるか否かは知らぬが、その中に
『われは後世たすからんと云ふ者にあらず、ただ現世に先づあるべきやうにてあらんといふ者なり』
といふ語がある。共に禪の現世主義なることを示せるものと見て宜しからうと思ふ。要するに禪は現世一世主義である。『極樂に往生して蓮花の上に坐るとか、天國に登つて神の玉座に侍する』とかいふことは禪者の目的とする所ではない。
この點は原始佛教とてやはり同じことで、巴利聖典中によく現はれる文句に『現法に於て自ら覺知し、實現し、逮達して止住す』といふのがあるが、現法とはいふまでもなく現在世のことで、この現在世に於て何物かを覺知し、實現し、又これに逮達して時を過すの意味で、これは阿羅漢果を得た人たちの境界を記する文句として巴利聖典中頻繁に反覆される文句である。中阿含の『賴②和羅經』には
『彼此の世に於て・・・自ら知り、自ら證り、自ら作證し成就して遊ぶ』
といふ文句になつて居る。長阿含の『裸形梵志經』に
『佛迦葉に告ぐ、若し如來至眞世に出現すれば、乃至四禪現法中に於て快樂を得』
といふ文があるが、これはまたいふまでもなく、如來の現法樂住の有樣を述べたものである。斯うして佛果又は羅漢果を成就した人たちは悟を開くと、その自得の法門の妙樂を耽味するといふのか、凡人の經驗し能はざる禪境の妙趣を味うて悠悠自適の中に時を送つたものである。
誰でも知つて居る通り、原始佛教では涅槃に二種あることを説く、二種の涅槃とは有餘涅槃と無餘涅槃とである。前者を又煩惱涅槃ともいふ、現身に證せられる涅槃である。後者を五蘊涅槃とも呼ぶ、死と同時に達せられるもので、通常灰身滅智とか一有情都滅とか呼べるもので、これを五蘊涅槃といふのはこの無餘涅槃に入れば五蘊所成の身、身も心も併せて全然滅無に歸する‐と信ぜられて居る‐からである。この二種の涅槃を佛の説き教へられたことは事實で、人が原始佛教、廣くは小乘佛教全體を灰身滅智の教として貶すのも誠に無理のないことである。これに就ては勿論問題ない。唯併し佛はこの二種の涅槃の中何れを重要視されたかといふことになれば問題は又別に起つて來る。一體涅槃といふ語は古くヴェーダ時代から用ひられたもので、これは『吹き消す(ニルヴァー)』nir+vaといふ前添詞(プレフィクス)及語根(ルート)、又は『包み覆ふ(ニルヴリ)』nir+vriといふ前添詞及び語根から來た語である。即ち風又は息のために火が吹き消されるが如く、或は(更に一層佛教的なる譬喩を用ふれば)法華經の『安樂行品』に『後當に涅槃に入ること、煙の盡きて燈の滅するが如くなるべし』といつてあるやうに、或は又『雜阿含』二九卷に『身壞れて命終り、煙の盡きて火の滅するが如し』といつてあるやうに、薪か油かがなくなつたために、煙が盡き火が自ら消えるやうに或は物を以て火を包み覆うたやうに、未來に生を受くべき善惡の有漏業がないために、又はその善惡の有漏業が作用を起すことを妨げられるがために、その阿羅漢は涅槃に入ると同時に身心共に空無に歸して更に再び世に出ることがなくなる。それでこれを無餘涅槃といふ。阿羅漢を形容する語として、漢譯聖典中に『更不受後有』とか『我生既盡』とか『於未來世、更不復生』とかいつてあるのはこの事を指していふのである。佛はこの涅槃も勿論説かれたが、しかし余の考ではこれは唯當時印度一般の説に順じて説かれたまでの事で、佛の特に力説されたのは恐くこれではなかつた。佛の特に力説されたのはこの涅槃ではなくして寧ろ有餘涅槃であつたらう。
涅槃と同意義の語として頻繁に經典中に現はれる一連の語がある。たとへば巴利長阿含『Mahagovinda-sutta』(『大典尊經』)の中に、佛は
『余はその時マハーゴーヴィンダ婆羅門であつた。余はこれ等弟子のため梵世界に上生するの道を説いた。しかしこの梵行は梵世界に生れるだけで、厭嫌、離欲、滅、寂静、上智、正覺、涅槃に導くものではない。今この余の梵行は人を眞實の厭嫌、離欲・・・に導くものである。それは賢聖八支道で、即ち正見正思惟正語正業正命正精進正念正定である。云云』
といつて居られる。即ち涅槃に達せんがために八支聖道を修するといふのである。八支聖道は大體からいへば倫理的のものであるが、これを修して涅槃に達することを得る。上の一連の文句は一見して判る通り、死後の涅槃の意義を含まず、唯現身涅槃の意義を含んで居る。
佛が無餘涅槃を先に説かず、且つ多く説かずして倫理的修養の結果として達せらるべき有餘涅槃を先きに、且つ主として説かれたのは、佛が前者よりも後者を重要せられたことを語るものではなからうか。勿論上にも述べた通り佛が再再用ひられた文句に『更不受後有』とか『我生既盡』とか『之は余が最後身である』とかいふやうな文句はある。これ等は皆無餘涅槃の意を寓する語であることは勿論である。『法句經』の中で、無餘涅槃を説けりと見らるるものは一五三、一五四偈(『增』一一一の三)の
『屋舍の工人を求めて、これを看出さず、多生輪廻界を奔馳して轉た苦の生死を經たり。屋工、汝今看出さる、再び屋を構ふることあらじ、汝の桷材は總て破られ、棟梁は毀たる。滅に至れる心は諸愛の滅盡に達せり』
といへるが最も著しいものであらう。しかしこれとても有餘涅槃を説けるものと見られぬでもない。尚ほ有餘涅槃を説ける文としては同經六九偈に『淫怒癡を除かば是を泥⑥となす』といひ、一二六偈に『善行の人は天に生れ、煩惱なき人は涅槃に至る』といひ、二三偈に『精勤は不死=涅槃=の道なり』といへるなど、一一枚擧に遑なきほどである。『雜阿含』一八卷の一經には『閻浮車(ジャンブカーダカ)舍利弗に問ふ、謂ゆる涅槃とは、云何なるを涅槃となす。舍利弗言ふ、涅槃とは貪欲永く盡き、瞋恚永く盡き、愚癡永く盡き、一切諸惱煩永く盡く、是を涅槃と名く』といつてあり(同經一八卷一〇經參照)。この境遇に赴くには正見乃至正定の八正道によるべきことをも記してある。斯うして貪瞋癡三毒の火が消え盡きて清涼寂静の境界に達したのが涅槃の人である。要するに佛が一代説法の間に特に力説されたのは無餘涅槃でなくして有餘涅槃であつた。而して繰返していふが無餘涅槃は當時の一般思想に順じて説かれたまでで、佛はこれよりも寧ろ有餘涅槃を重要視されたと信ずる。即ち佛の教はその最上の目標の上に於てすらも現世的であつたといふのである。禪も現世的であることは勿論、原始佛教もやはり現世的である。
禪及び原始佛教の修養の目的が現在世にあることを更に一層明かにするため余はサー・チヤールス・ヱリオツトの『印度教及佛教』一卷二二一‐二二二頁から左の一段を譯出することにした。これは八正道の中の正定を説明する文であるが、禪定の解釋であると見て差支へない。
『八正道の第八即ち最後のものは正定、正しき凝念、正しき恍惚である。三昧(サマーヂ)は此處彼處に快樂を求むるものとして往往非難せられる漂泊的欲望と反對するもので、これに必要缺くべからざるものは精神の統一である。しかし三昧は單なる凝念ではない、又静觀でもない。それ以上のもので恍惚又忘我の語を以て譯すべきものである、但多くの佛教の述語と同樣、歐州の言葉ではきちんとこれに當てはまるものはない。佛教の三昧は他の宗教の祈祷、即ち神靈的存在者と忘我的に交通する祈祷の位置を占めて居る。佛が阿闍世王のため沙門生活の效果に就いて説かれた説教は三昧の喜に就て雄辯なる物語を與へて居る。佛は沙門が樹木の下又は山窟の中に坐りその身體を眞直にして、その知慧を敏活に專一にし、その精神より貪欲、瞋恚、懈怠、忿怒、疑惑を除くことを述べられた。これが終わると沙門は獄舍から出たもののやうに、又は負債から免れたもののやうに喜悦がその心に湧いて出る。而して沙門は次第に四禪即ち静觀の四個の階段を通つて行く。次にその精神全體、而して又その身體までも清淨と平和の感情が浸み通る。彼はその思想を集中し自ら選ぶに任せてその思想を大なる問題の上に適用することが出來る。彼は超自然的力の受用に耽ることが出來る。こは吾吾は吾吾が有つて居る一番古い記録に聖者には神通力‐縱令記録は神通力をあまり重要視して居らぬにせよ‐があると認めてあるのを否定することの出來ぬからである。或は又沙門は佛が自ら大悟を成ぜられた思想の連續を追うて行くことも出來よう。彼はその前生を思ひ考へて、遠く散歩をした人が一日の終わり自分が過ぎ通つた村村を記憶するやうに、明かにその前生を記憶する。彼は他の生物の生死を思ひ考へて、恰も家の屋根の上に立てる人が下なる街路を通りつつある人を見るやうに、明かにこれを見る。彼は四種の眞理の意義を十分に理解し、三の大なる害惡の起滅、快樂の愛、生存の愛及び無智を了解する。而して斯く彼が見且つ知ると、その心は自由になる。斯の如く自由になると自由の知識が出て來、彼は生は既に斷たれ、高尚なる生活は營まれ、爲さるべきことは爲され了つたと知る。ちやうど、山の砦の中に池があつてその水が澄んで透き通つて静かである、其處に一人の見る眼を有つた人が岸の上に立つて池の中なる貝、砂、小石又は魚の群の動いたり、横になつたりしてるのを見るやうなものである。』
『佛の目的は深遠なる哲理を宣明することではなくして人をして實行的修養に進ましむるにあつた。』
これは姉崎博士の『根本佛教』(八頁)から取つた一文であるが、原始佛教の徹頭徹尾實踐的にして深遠幽玄なる學理を説くを目的とせざる宗教であることはこの一文に明にされて居ると云つてよい。隨つてこの上更に蛇足を加ふるの必要はないかと思はれるが、此處に吾吾は『實行主義』の一項目を設けて更に少しくこの意味を明瞭にし、これによりて原始佛教と禪宗とを結びつけたいと思ふのである。
佛が『世界』、『我』、又は『死後の生活』に關して兎や角と議論することを弟子たちに誡められた例は原始聖典中所所に發見する所である。前(第七章)にも一寸述べた通り、『世界は常住なりや、世界は有邊なりや無邊なりや、命(ヂーヴ、精神)は身(サリーラ、身體)と同なりや異なりや、如來は終ありや終なきや、終あり且終なきや、或は又終あるに非ず終なきに非るや』(『雜阿含』三四卷、二四經、中阿含六〇卷『箭喩經』その他所所に出づ)
といふやうな問題は實踐躬行を重しとされたる世尊の眼から見れば、比丘の實際修行上何等の效果のない無用の閑問題である。而して又永久結果を見ることのない、人間生活には直接用のない戲論である。『箭喩經』によれば鬘童子比丘(マールンキヤプツタ)はこれ等の問題に就て疑義を起し、世尊はこれに答ふるの能なき人と斷じた。世尊を難詰して若し世尊がこれは眞諦で他は悉く虚妄の言なりと説かれなければ自分は世尊を捨てて去らうといふ意気込で佛の所へやつて來た。佛は童子に向つて、汝の余に隨つて梵行を修するは余が汝がために世界は常住とか無常とか、有邊とか無邊とか、精神と身體は同一とか不同一とか、如來は終ありとか終なしとかいふことを説くが故であるかと問はれると、童子は否然らずと答へた。佛は童子を訶責し、斯ういふことに就て十分究め盡した後梵行を初めようといふのは、譬へば身に毒箭を射られたものが、その箭を抜き醫師を求めてその傷を癒すことをせずに、先づ箭を射た人の姓名、人物、素性、箭の來た方角、箭を作るに用ひた材料などを詳しく調べた上でこれを抜こうとするのと同じ態度であるといはれた。佛の使命は要するに深遠な哲理を宣明することではなくして、人をして實行的修養に勤ましめることであつた。それ故に教といへば四諦であり、道といへば八正道である。
佛の在世時代は古ウパニシャッドの末期で、哲學的思索の盛な時代であつた(第五章參照)。弟子たちが斯ういふ問題の討究に關して佛の態度の至つて冷淡な事に不滿を抱いたといふことはありさうな事でもあり、且つそれがあるのも道理あることと思はれる。しかし佛の著眼點は全く別處にある。佛の眼から見れば斯る事柄は無用の閑事であつた。『行へ、行へ』といふのは佛が日常口を極めて弟子等に説き勸められた語であつた。要するに佛の目的は當時或一部の印度人が特に力を用ひたやうに深遠なる哲理を宣明することではなくして、只管人を實踐躬行に勤ましむることであつたのである。
吾が佛教は何處までも實際的宗教で、徒に空理空論を談ずるを以て目的とするものではない。この點は獨り禪宗ばかりでなく、何れの宗派と雖も同じことである、しかし吾が禪宗は特に『行解相應』といひ、『行持綿密』といひ、『威儀即佛法、作法是宗旨』といひて行持を重んずる風あることは禪を知れるものは誰も知れる所である。古來禪門の淨侶といへばこの威儀即佛法の意義をその日用の行持の上に體現せんと努力したものである。支那にせよ日本にせよ、禪院内に於ける禪僧の生活は一進一退悉く規矩準繩に適ひ、一絲紊れざる所があつて、門外の人たちにすら深き印象を與へたといふ話は所所に見出す所である。曾て歐陽修が禪院内に於ける禪僧の威儀を見、感嘆して『三代の禮樂は緇徒の間にあり』といつたといふも誠に道理ある事である。吾吾は上(第十章)に原始佛教は『教の法』たるよりも寧ろ『行の法』であるといつたが、これは吾が禪宗にしても同樣で、『即身説法』の語は、勿論色色異れる意味に解し得られるであらうが、禪僧がその身の行を以て人の師表となるの意と解することも亦可能である。事實禪僧は一言を口にせずともその身の行持を以て人のために法を説いたものである。藥山は説法の座に上りながら一言を埀れずして方丈に歸つた。而して經を説くは經師のすること、論を説くは論師のすること、老僧の與り知る所ではないといつた。維摩は默然として摩竭の室を閉して人のために法を説いたといふ。『默雷の如し』とか、『門を閉ぢて打睡して上上の機を接す』とかいふこともこの意味を表はせるものと見ることも出來よう。法の第一義諦は本來口で説かうとしても説き得られるものではない、説かんと擬すれば二に落ち三に落ちる。故にそれを説かないのだといふが、その實は法の眞面目はこれを口で説くの必要はない。唯從晝至夜行ふべき通りに行へばよい。それが法を説くことになるのである。吾吾は此處で即身説法を斯ういふ意味に取りたい。
生活の簡素主義は原始佛教時代の佛弟子たちに取りては素よりその本分とする所であつた。『衣は以て肩を覆ふに足り、食は以て餓を防ぐに足り、居は以て膝を容るるに足る』といふほどの衣食住の簡素ぶりは彼等に取つては何でもないことであつた。理想の法衣はといへば糞掃衣である。それであるから比丘たちは『塚間より又は街路より塵布を持ち來り、それを僧伽梨衣に縫うて著用した』(『長老偈』五七八)。比丘尼たちも『襤褸を以て衣服を作り、これを纏うて快よく臥した』(『長老尼偈』一、一六)。食は乞食により又は遺穗を拾うて得たものを食ふことであつた。美食を得ても粗食を得ても愛憎の念を起してはならない、多く得ても少く得ても好惡の情を有つてはならぬ。若し食を得たならばそれで可、若し全く得なかつたならば一日食はなくして過さなければならない。されば『美味なる或は不味なる、少き、或は多きを貪らず、惑はず唯生命を繋がんがために受用しぬ』(『長老偈』九二三)といつてある。大迦葉は癩病に罹れる人から施食を受けたといふ話がある。原文を譯したままを此處に出すのが興味があらう。曰く『山間の坐臥處を下り、われは乞食のために都城に入りぬ。癩人の食を取れるを見、われは恭しくこれに近づきぬ。彼は腐り果てたる手を以てわれにその食を薦めぬ。食をわが鉢に投ずるや、指も亦其處に壞れ落ちぬ。井に凭れてわれはその食を食ひぬ。食ひつつありても、食ひ終りても、われに厭嫌の念起らざりき』(『長老偈』一〇五四‐六)。
『一切衆生依食住』といふ語は佛典の中では極めてあり觸れた語である。衣食住の三は人間の生活に必要缺くべからざる物件であるが、三者中最も必要なるものはといへばそれは食物であらう。即ち衣服もなしで‐特に印度の如き熱帶國では‐通すことは出來ようし、住宅も有たずにやつて行くことは出來よう、しかし食物は、それが旨いとか拙いとかは別問題として、なしでは生物は生きて行けるものではない。斷食といふことはあるがそれも或期間内だけのことで、一定の限度を過ぎることは到底出來るものではない。
『一切衆生皆由食得存、無食不存』
と波斯匿王がいつた(『增一阿含』一三卷四經)のは至言である。しかし僧侶は自身食物の生産に與はるものでなく、この點に於ては信者の布施に賴るより外はないから、僧侶たるものは自分の生存の他人(即ち信者)の力に依れることを日夜に反省して極度に謙虚の心を養ひ、且つなるだけ乏しき資料によりて生活しなければならぬと教へられた。比丘が乞食によりて生活することは大體は印度在來の習慣に倣うて設けた制度であるが、これは又比丘の慢心を挫くためには一種の都合よき方便となつたものであつた。
住所はといへば家屋、岩窟、深林、河岸、樹下、石上可なりであつた。『律』の示す所によると、もと比丘たちは夜分になると、林間樹下山中洞穴山窟塚間森林野外藁堆など思ひ思ひに勝手な所に寝とまりをなし、朝になるとこれ等の諸所から出て來た。それが見にくく見えたので王舍城の長者が精舍を供養せんことを申し出た。その序でに佛は精舍、兩房一戸、樓閣、別房、洞窟等五種の住所を用ふることを許された(『小品』六の一)とある。この長者の供養をしたといふ精舍は如何なものであつたらうか、彼は一日に六十の精舍を作つて出したとあるから、それは至つて粗末なもので、今の東京のバラツクにも劣つた粗造家屋であつたらうかと思はれる。併し佛弟子たちはそれでも勿論滿足して居た。粗造家屋ところではない、一長老は『林中に樹下に岩窟の間に幽静の情を長じつつ』(『長老偈』二九五)といひ、一長老は『われは森林、岩峽、洞窟、邊鄙の坐臥處、猛獸の往來する所に住し來れり』(同六〇二)といつて居る。二人の長老は『深林大林の中に於て虻又は蚊に螫され、而も戰場に臨める象の如く、正念を失はずしてその所に往せん』(同三一、六八四)といつて居る。今一人の長老は『恒河の岸邊に於て、われ三多羅葉の茅舍を構へたり、わが鉢は屍に乳を濺ぐの器、また衣服は襤褸なり』(同一二七)といつて衣食住の上に簡素ぶりを十分發揮して居る。
男子は斯うして自然界を家とし、深林、岩岫、洞窟、岩邊、石上、到る所として可ならざるはなく、蚊虻、毒蛇、猛獸の難に堪へつつ、勇猛に精進努力したものであつたが、流石に女子はこれをよくせなかつた。男僧の生活ぶり修行ぶりと女僧のそれ等とを比較して興味ありと思はれることは男子は斯うして自由に屋外の生活をなし、野外に曝露して毒蛇毒虫猛獸の襲來をも意とせずにやつて行くことを得たが、女子はさうは行かなかつたことである。これは勿論自然のことであらう。比丘尼が『襤褸を以て衣服を作り、これを纏うて快よく臥した』(『長老尼偈』一、一六)とか、『力弱く杖に凭りて食を乞ひ廻り、四肢震ひて地上に倒れぬ』(同一七)とか『杖に凭れて山を登つた』(同二七、二九)とか、或は『日中住のために靈鷲山に登つた』(同四八、一〇八)とかいふ程度のことはいつてあるが、大體からして極めて女性的で、此處には上(第十二章)に述べたやうな風雨雷電の凄まじい音を聞きながらの禪思や、深林内又は岩窟中の起臥や、毒蛇惡獸の襲來をも意とせざる底の大膽さは示されて居らない。隨つて自然界との親しみも至つて少いといふことになる。しかしこの長老尼たちの生活ぶり修行ぶりの女性的なるは勿論當然のことで、若しこれが男僧のそれにも劣らず男性的であつたといつたならば、それは明かに虚僞を語れるものと見るべきであらう。
禪僧の生活の簡素ぶりに就ては多くを語るの要はない。遠くは葉縣歸省和尚の枯淡や近くは白隱禪師の貧乏など誰でも知つて居る所である。白隱禪師が『夫れ學は苦學より美なるはなく、道は貧道より尊きはなし』といへる教も實際を見せての教訓であるので、學人の頭には特に深く沁み込んだであらうと察する。桃水和尚の如き大燈國師の如きは身を乞食の群中に投じて居たといふことであるが、桃水和尚は『弊衣破椀亦閑閑』といひ、大燈國師はその遺誡の中に
『一杷茅底折脚鐺内に野菜根を煮て喫して火を過すとも專一に己事を究明する底は老僧と日日相見底の人なり』
といつた。高祖の『行持卷』の中に
『この日本國は王臣の宮殿なほその豐屋あらず、わづかにおろそかなる白屋なり。出家學道のいかでか豐屋に幽棲するあらん。もし豐屋をえたるは邪命にあらざるなし、清淨なるまれなり。もとよりあらんは論にあらず、はじめて更に經營することなかれ、草庵白屋は古聖の所住なり、古聖の所愛なり。晩學したひ參學すべし、たがゆることなかれ』
といつて居られる。禪僧の衣食住の上に簡素であるべきことは斯うして古徳の遺訓の中に明かに示されて居る。
吾人は上十餘章に亘つて原始佛教と禪宗との兩者が共通に有する點十餘條を擧げ、一一簡單な説明を加へた。この問題に就て吾人の言はんと欲することは大抵言ひ盡したと思ふから、吾人はこれを以てこの小論文を結ぶこととする。兩者の共通に有する點は多いがその中で特に顯著なるもの、且つこれ等共有點の歸結とも見らるべき所は共に實行主義なる點にある。つまり原始佛教も禪宗もその極致は修行者なり信者なりに實行を勸めるといふ點にある。これは勿論これ等兩者に限つたことではない。佛教各派は假令深遠幽玄なる世界觀や人生觀を説くにしてもその歸着點は此處にあるといへよう、語を換へて言へば世界人生に關する深遠幽玄なる哲理を説くのも、それは要するにこの實行の歸結を引き出さんがためといふことにならう。而してこれは又單に佛教ばかりではない、論語の『學而篇』には『行に敏にして言に愼しむ』と云ひ、『里人篇』には『君子は言に訥にして行に敏ならんことを欲す』といつてある通り、實行主義は儒教でも決して忘れられる所ではなかつた。實踐躬行といふ文字の出て來るのも決して偶然ではない。實行主義は東洋倫理道徳の特色とする所である。倫理的色彩の特に濃厚なる佛教にこの特色あるは少しも異とするに足らない。唯原始佛教と禪宗とは共に言論を否定してまでも實行を勸むる教であるから言はば實行教であるといはねばならない。
原始佛教と禪宗との兩者が戒定慧の三學の中で戒學を重しとし、佛法僧の三寶の中で特に僧寶を尊しとし、佛身觀の上では法身佛や報身佛を取らずして、語を換へて言へば他の宗教の神の位置にまで高められた法身又は報身の佛陀を措いて、現身佛、即ち歴史上の佛をその第一の佛とする、而して共に神秘的なる儀式を排斥し、哲學的思辯主義を排斥することはこれを約めて實行主義の一語に歸結せしむることができよう。原始佛教で佛がヴェーダの神を無視し、ブラーフマナの儀式萬能主義を排斥し、ウパニシャッドの思辯哲學を取らずして唯『行へ、行へ』と教へられたのも、禪宗で柴を搬び水を運ぶことを妙用神通といひ、鉢を洗ひ瓶を添ふることを法門佛事といふも同じくこれ實行主義を高調するものである。正法眼藏『行持卷』には大慈寰中禪師の語として
『説得一丈不如行取一尺、説得一尺不如行取一寸』
の句を引いてあるが、こは『法句經』一〇一偈の
『千章を誦すと雖も義あらずんば何の益かあらん、一義だも聞き行じて度すべきに如かず』
といへると同巧異曲であらう。高祖は趙州が座下の大衆に告げて一生叢林を離れず、十年又は五年一語を發せずとも唖漢と間違へられることはあるまい云云といへる語を擧げて盛に推稱して居られる。要するに禪宗も原始佛教と同じく不言實行、理屈をいふは經師論師に任せて唯『行へ、行へ』と教へることに歸著すると見て宜しからう。原始佛教と禪宗とは實行主義即ち實地に修行して涅槃の果を體驗する、或は迷を轉じて悟を得ることがその教の歸著點となつて居るといつて宜しいかと思ふ。
原始佛教と禪宗 終
①手偏に過 ②口偏の託 ③人偏に果 ④目遍に侯 ⑤心遍の橋 ⑥さんずいに亘 ⑦牛偏に健 ⑧絲偏に希 ⑨土偏に埀